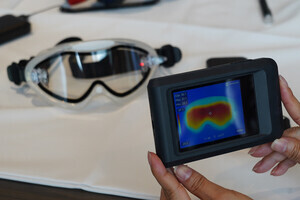ディズニー110周年記念映画「ジョン・カーター」。火星を舞台にした冒険活劇を壮大なスケールと最新の映像技術で描くこの作品の原作は、今年で100周年を迎える有名小説だ。「スター・ウォーズ」や「アバター」に多大なインスピレーションを与え、かつてそのスケールから実現不可能と言われていたこの物語を、100年前の火星観とその科学的な歴史から紐解いてみよう。
多くのクリエイターに影響を与えた「火星のプリンセス」
現代の我々は火星に文明どころか、生命の痕跡すら見つけていない。火星が赤茶けた砂と岩におおわれ、砂嵐が吹き荒れる死の星であると地球人が知ったのは、火星探査機がようやく届くようになったここ50年ほどのことである。 そのさらに50年前、すなわち今から100年前の1912年、アメリカのパルプ雑誌「オール・ストーリー」で『火星の月の下で』と題する連載が始まった。さまざまな職業を転々としてきた、37歳のエドガー・ライス・バローズの遅いデビュー作であった。
南北戦争(1861~1865年)後のアメリカから火星へワープした男、ジョン・カーターが冒険をくり広げる活劇小説である。バルスームと呼ばれている火星には4本の腕と緑の肌を持つ「緑色人」サーク族や、地球人と同じ姿をしている「赤色人」のヘリウム王国とゾダンガ王国の一族が住んでいた。ジョン・カーターはサーク族の皇帝タルス・タルカスと出会い、ヘリウム王国の王女デジャー・ソリスと恋に落ちる。そしてゾダンガ王国との抗争に巻き込まれていく……。
連載は『火星のプリンセス』というタイトルで書籍として刊行され、多くの人々を魅了した。その中にはジョージ・ルーカスやジェームズ・キャメロンもおり、「スター・ウォーズ」や「アバター」にヒントを与えたという。さらに「ジュラシック・パーク」で知られるマイケル・クライトンは医療ドラマ「ER 緊急救命室」で、自身を投影した医学生の登場人物を「ジョン・カーター」と名づけている。 「ファインディング・ニモ」や「ウォーリー」のアンドリュー・スタントン監督もまた、子供のころ『火星のプリンセス』を夢中で読んだ一人だった。そして少年時代の情熱を注いで完成させた映画が「ジョン・カーター」である。
100年前の人々にとっての火星とは
本作で描かれる火星は、100年前の火星の知識にもとづいている。すなわち、地球よりは薄いが空気があり、重力は地球よりずっと小さく、高度な文明を持つ火星人が住んでいるというものだ。火星人が地球よりはるかに進んだ文明を築いていると考えられた理由には、実際の火星観測が関係していた。 火星はおよそ15年おきに地球に大接近し観測のチャンスを迎える。1877年の大接近ではイタリアのジョバンニ・スキャパレリが火星を観測し、たくさんの筋状の模様を見いだした。スキャパレリはこれを「canali(水路)」と呼んだ。この呼称が英語に翻訳された際、「canal(運河)」と誤って伝わった。
運河を建設する火星文明という考え方を一般に広めたのはパーシバル・ローウェルである。資産家の彼は1894年にローウェル天文台を開設し、同じ年に大接近中の火星を観測した。そして火星の「運河」を克明に記録したのである。翌1895年、ローウェルは『火星』という一般向けの本を出版する。もちろん運河とそれを作った文明についても書かれており、火星人が大運河を建設したことを多くの人が信じるようになった。 この当時、火星の極地には氷があり、1日の長さは約24時間、地軸の傾きも地球とほぼ同じで、したがって四季があることもわかっていた。ここまで地球と似ていれば、生命体が火星にもいると考えるのは自然なことだった。
火星人が登場するSF小説の先がけはH.G. ウェルズの『宇宙戦争』である。ローウェルの『火星』の3年後、1898年に発表され、タコのような姿の火星人による地球侵攻が描かれた。火星は重力が小さいため体は柔らかく、薄い大気のせいで呼吸器が発達しているという理屈だった。