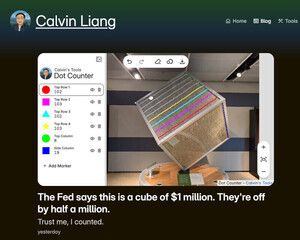松本剛明総務省大臣は、米国時間の2023年1月17日に米国のグレーブス商務副長官らと会談、オープンRANの情報交換や第三国への啓発、オープンRAN(Open Radio Access Network)を含む5G・6Gに関する多国間の場での協力促進などに関する覚書を締結したとのことです。なぜ日米両政府がオープンRANの推進に積極的に動いているのでしょうか。→過去の次世代移動通信システム「5G」とはの回はこちらを参照。
経済安全保障でベンダー依存脱却を推進
米国時間の2023年1月17日、総務大臣の松本剛明氏は訪問先の米国で、グレーブス商務副長官およびデイビッドソン長官と会談。そこでネットワークインフラの強靭化に向けた取り組みとして、総務省と米国商務省国家電気通信情報庁との間で覚書に署名したと、総務省から発表がなされています。
その覚書は「オープンで強靱な電気通信ネットワークに関する日本国総務省とアメリカ合衆国商務省国家電気通信情報庁間の協力覚書」というもの。
その内容はオープンRAN(第20回参照)に関する取り組みが主となるようで、具体的にはオープンRANのテスト関連活動に関する情報交換、第三国におけるオープンRANの啓発・情報伝達活動の協力、そしてオープンRANを含む5G、Beyond 5G/6Gなどに係る多国間の場における協力を促進していくとされています。
また、同日に松本大臣は米国国務省のフィック大使とも会談をしており、そちらでも強靭なネットワークインフラの構築などについて日米が協力していくことが打ち出されています。
そして総務省の発表内容を見ますと、こちらでもやはり「オープンで相互運用可能でありセキュアな5GおよびBeyond 5G(6G)の確保の重要性を踏まえ、第三国におけるオープンインタフェースの推進等について、多面的・具体的な協力関係をより強化していくことで一致」したとされています。
いずれも5G、6Gに向けて日米がオープンRANで協力していく姿勢を示す動きといえますが、そもそもなぜ、両国が国を挙げてオープンRANを推進する必要があるのか?という点が気になるところ。そこに大きく影響しているのは経済安全保障のようです。
米中対立の激化によって注目が高まっている経済安全保障ですが、モバイル通信に関して特に懸念されているのがネットワークインフラに関してです。モバイル通信機器市場は大手による寡占が進んでおり、その一角を中国のファーウェイ・テクノロジーズが占めている状況にあります。
そうしたことから、米国は中国企業の通信機器を自国のネットワークから排除する動きを進めており、2018年には米国の政府機関などが指定された中国企業との取引を禁止する「国防権限法」が成立。
同盟国にもそれら企業の機器を使わないことを求め、それに応じる形で日本政府は2018年12月に「IT調達に係る国の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」を公表しています。
-

内閣サイバーセキュリティセンター「IT調達に係る国の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」より。この申し合わせの対象となる政府調達のIT機器は、サーバなどインフラ向けの機器からスマートフォンまで多岐にわたる
これが事実上、中国企業の通信機器を排除することを示す指針とされ、以後携帯各社も中国企業の通信機器をインフラから排除する動きを進めているのですが、そこで問題となってくるのが、大手ベンダーにすべての通信設備を依存せざるを得ない携帯電話会社の現状です。
4Gや5Gで通信する仕組みの仕様は標準化されているのですが、導入する機器の制御などはベンダーに依存せざるを得ず、携帯電話会社に周波数免許を割り当てている国からしてみれば、クローズドな仕組みに不安があることも確かです。
その点、オープンRANは標準化された仕様に沿った機器やソフトウェアを携帯電話会社側が自由に選択できることから透明性を確保しやすいのです。そこで日米、ひいては他国の経済安全保障を高めるうえでも、対立する国々の特定企業に依存しないオープンRANの導入を推奨するようになったといえるでしょう。
オープンRANで先行する自国ベンダー支援の狙いも
ただ両国がオープンRANを推奨する動きを見せているのには、経済安全保障以外の狙いも大きいと考えられます。そのことを示しているのがモバイル通信機器の市場シェアです。
先にも触れた通りモバイル通信機器市場は寡占状態にあり、中国のファーウェイ・テクノロジーズとスウェーデンのエリクソン、フィンランドのノキアの“3強”で7割近いシェアを獲得。それに韓国のサムスン電子と中国のZTEが続いており、5社で市場の9割以上が占められているのが現状なのです。
そして、重要なポイントは、この中に日本と米国の通信機器ベンダーが存在しないこと。日本では一定のシェアを持つNECや富士通も、事業がほぼ国内にとどまっているため世界シェアは両社合わせて1%程度。
米国の通信機器ベンダーもかつては大きな勢力を誇っていましたが、競合に買収されるなどして現在は有力企業が存在しない状態です。
一方、オープンRANに関しては、国内の携帯電話会社が積極的なことからNECや富士通が先行して取り組んでおり実績も多く挙げています。米国でも楽天グループが買収し楽天シンフォニー傘下となったAltiostar Networksなど、仮想化技術を主体としてオープンRANに積極的に取り組む新興企業が増えています。
-

NECはオープンRANで海外の携帯電話事業者に向けた販路拡大を積極的に進める方針で、2025年度にはオープンRANを主体としたグローバル5G事業で売上1900億円、営業利益10%という意欲的な目標を立てている
そこで、オープンRANの普及とともに、世界のモバイル通信機器市場で自国企業の存在感を高めたいというビジネス的な要素も、日米両政府の取り組みには大きく影響しているのではないかと考えられる訳です。
そうした両国の姿勢が実際の市場に今後どこまで影響してくるかは分かりませんが、5Gのモバイル通信機器を巡る争いがビジネス、安全保障の両面で国家間の勢力争いにも結びつきつつあることは確かだといえるのではないでしょうか。