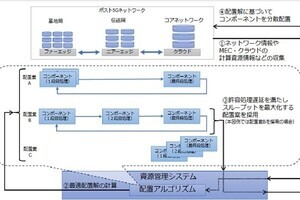ソフトバンクは2024年6月4日、独自のアンテナ技術の活用によって300GHzのテラヘルツ無線を用いた車両向けの通信エリアを構築する実証実験に成功したと発表しました。→過去の「次世代移動通信システム『5G』とは」の回はこちらを参照。
6Gでの活用が期待されるサブテラヘルツ波は、ミリ波以上に電波が遠くに飛ばないことが課題となっていますが、ソフトバンクはどのような技術を用いてその課題をクリアしようとしているのでしょうか。
ターゲットをスマホからコネクテッドカーに
5Gでミリ波の活用がなかなか進まないことが大きな課題となっていますが、その理由は周波数が高いほど電波が遠くに飛びにくく、広いエリアをカバーするのが難しくなるため。
しかし、高い周波数帯ほど空き帯域幅が大きいので、今後必要とされる大容量通信に対応するには高い周波数帯の活用が必要不可欠なのも、また確かです。
そして5Gの次世代となる通信規格の「6G」においては、ミリ波よりさらに高い、100GHz~300GHz前後の「サブテラヘルツ波」と呼ばれる周波数帯の活用が検討されています。ただ、サブテラヘルツ波はミリ波より一層減衰しやすく電波が遠くに飛ばない上、障害物にも弱いことから、実用化に向けては非常に多くの課題を抱えています。
ですが、日本ではサブテラヘルツ波のような高い周波数帯の活用に向けた研究が積極的に実施されており、携帯各社もサブテラヘルツ波の実用化に向けた研究開発を進めています。ソフトバンクもの1社であり、同社ではこれまで、サブテラヘルツ波をスマートフォンにも搭載することを目指して研究を進めてました。
実際、2021年には300GHz帯を用いて無線通信での動画の伝送を実現しているのですが、その通信距離は20cm程度。加えて少しでも電波の射出角度がずれると通信できなくなるなど、通信はできるものの扱いが難しい様子を示していたのも確かです。
それから、およそ3年が経過した2024年。ソフトバンクがサブテラヘルツ波の実用化に向けて新たに取り組んでいるのが、自動車でのサブテラヘルツ波の活用です。サブテラヘルツ波で長距離をカバーするには端末側の電波出力も上げる必要があり、そのためには電力が必要なことから、電力関連の技術向上が進まなければスマートフォンでの活用は難しいといいます。
一方で、自動車であればスマートフォンと比べればはるかにサイズが大きく、電力面での問題は解消しやすい。それでいてコネクテッドカーの需要が今後一層高まると考えられることから、現在は自動車を対象としてサブテラヘルツ波による通信の実現に向けた研究開発を進めているようです。
独自のアンテナ技術で140mのカバーに成功
ただ、屋外でサブテラヘルツ波を活用するには課題が少なからずあり、既存の携帯電話基地局のように面的にエリアを広げようとすると、電力が分散してエリアが狭くなってしまうという問題が発生してしまいます。
そこで、ソフトバンクではサブテラヘルツ波で構築するエリアを、車が走行する直線の道路に絞り電波を射出する幅を狭めることで、電力の分散を防ぎ、より遠くの場所をエリア化することに重点を置いたとのこと。
しかし、単に指向性の強い電波を射出するだけでは、基地局にとても近い場所で逆に電波が弱くなってしまうという問題もあったそうです。
そのため、ソフトバンクは航空レーダーで用いられている、高低差のある送受信アンテナの水平距離にかかわらず、基地局と端末の受信電力が一定になるという「コセカント2乗特性」に着目。独自のアンテナを開発することでコセカント2乗特性を通信でも実現するシステムを開発したとのことです。
実際のアンテナを見ると1~2cm程度の大きさで、スマートフォンに搭載するのは厳しいですが、自動車や基地局に搭載する分には十分小さいサイズに収まっていることが分かります。
ただそのアンテナをより低い周波数、例えば6GHz以下の「サブ6」の周波数帯向けに作るとなると、ゆうに1mは超える大きさになってしまうとのこと。アンテナの小型化が可能なサブテラヘルツ波だからこそ、このサイズに収められたようです。
そしてソフトバンクは、その独自アンテナを用いた実証実験を、ソフトバンク本社付近の直線道路で実施しています。これは基地局側の5G信号を、周波数変換装置で300GHzに変換して射出。それを自動車に搭載した端末で走行しながら受信し、3.9GHzの周波数に変換。復調した上で受信電力を記録し、どこまでカバーできるのかを測定するというものになります。
筆者も実際に、端末を搭載した車に乗車して受信電力の推移を確認したのですが、実証実験のエリア内となる140mの道路内ではおおむね問題なく復調できている様子で、サブテラヘルツ波ながら長い距離をカバーできていることを確認できました。
ちなみにソフトバンク側の説明によると、実証実験の範囲が140mとなっているのは直線で確保できる道路の長さが140mに限られるためで、実際にはもう少し長い距離をカバーできるとのことでした。
ただ、もちろん課題もあり、基地局でカバーする範囲が直線の道路内に限られることから、道を曲がってしまうと途端に電波が届かなくなってしまいます。それゆえ、仮にこの仕組みが実用化したとしても、カーブのある道路などをカバーするには複数の基地局を設置することが求められるでしょう。
また今回はあくまで電力を測定しているだけであり、具体的にデータ通信などを実現している訳ではないとのこと。実際に通信した時の性能がどうなるか、未知数な部分もあるようです。
しかし、スマートフォンより大きなデバイスでの利用に限られるとはいえ、遠方をカバーするのは困難とされていたサブテラヘルツ波で、100mを超える範囲をカバーできる可能性が出てきたことは大きな進歩ともいえます。実用化に向けてまだ多くの課題を抱えているサブテラヘルツ波ですが、各社の努力によってその道筋が開かれることに期待したいところです。