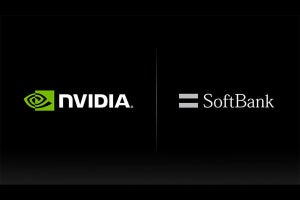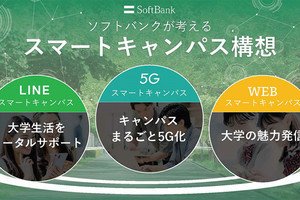ソフトバンクが5Gで力を入れる「Segment Routing IPv6 Mobile User Plane」(SRv6 MUP)。そのSRv6 MUPを、ヤマハのリモート合奏サービス「SYNCROOM」と共同実証実験を実施することが2023年8月7日に発表されました。両社の実証実験の狙いを確認してみましょう。→過去の「次世代移動通信システム『5G』とは」の回はこちらを参照。
リモート合奏の「SYNCROOM」を使った実証
5Gや6Gに向けては、さまざまな技術開発が進められていますが、中でもソフトバンクが力を入れている技術の1つがSRv6 MUPです。
その詳細は第65回で説明していますが、大まかに説明しますと、従来の電話回線に用いられてきた回線交換の技術を、IPベースの技術に置き換えるものになります。
これにより、コアネットワークに汎用のルータなどを活用できるようになるなど低コスト化が実現できるほか、パケットベースでの通信により同時に多数の端末での通信を実現しやすくなることから、5Gの主要技術であるMEC(Multi-access Edge Computing)やネットワークスライシングなども実現しやすくなります。
それゆえ、SRv6 MUPの導入に向けた具体的な取り組みが注目されるところですが、2023年8月7日にソフトバンクは、ヤマハと共同でSRv6 MUPに関する実証実験を開始したことを発表しています。これはSRv6 MUPを適用した5Gの商用ネットワークで、ヤマハの「SYNCROOM」を使った実証をするというものになります。
SYNCROOMとはヤマハが提供しているリモート合奏サービスの1つであり、最大5拠点のユーザーをつなぎ、SYNCROOMを通じてオンライン合奏ができるというもの。離れた場所にいる人同士でセッションができるというだけでなく、コロナ禍にあった2020年にサービスを開始していることもあって、集まってバンドなどの練習ができない人たちにも役立つサービスとなっているようです。
しかし、遠隔での合奏には通信が途切れないことやずれが生じないことなどが求められるだけに、SYNCROOMを快適に利用するにはネットワーク側に安定、高速、そして遅延が少ないことが重視されます。それゆえ現状、SYNCROOMを快適に利用するには光回線が必要とされ、モバイル回線では快適な利用が難しい状況にありました。
そうしたことから、低遅延を実現しやすいSRv6 MUPを用いた商用のネットワークを用いることで、SYNCROOMを快適かつモバイル回線でより手軽に利用できることを確認するべく、実証実験を実施するに至ったとのことです。
ソフトバンク側としてもSYNCROOMがSRv6 MUPのポテンシャルを生かせるサービスであるのに加え、提供元のヤマハ自体がルーターを開発しておりネットワークに詳しい技術や知見を持つことから、共同で実証をする相手として最適と見ているようです。
一層商用に近い環境での実証が重要なポイント
ただ実は、SYNCROOMは5Gと浅からぬ縁があるサービスでもあります。今回のソフトバンクとの実証実験以前にも、ヤマハはSYNCROOMの前身となる「NETDUETTO」を用い、NTTドコモと5Gネットワークを用いたリアルタイムでのセッション演奏に関する実証実験を実施しているのです。
-

ヤマハはNTTドコモと、SYNCROOMの前身となる「NETDUETTO」を用い、5Gネットワークを活用したリモートでのリアルタイムセッションに関する実証実験を実施。NTTドコモは2019年に実施された「MWC19 Barcelona」でもそのデモを披露している
では、その時と今回の実証実験とは何が違っているのでしょうか。ヤマハ ミュージックコネクト推進部 サービス企画・開発グループ 主幹の原貴洋氏によりますと、以前の実証実験は5Gの商用化以前の実証実験ということもあって、非常に整った5Gのネットワーク環境を確保した上で実証を実施していたといいます。
しかし、実際にサービスを提供するうえでは、必ずしも環境が整っている訳ではない商用の環境でも快適に利用できることが求められます。それだけに今回の実証実験は、より商用環境に近い環境で実証できることがメリットとなるようです。
実際のところ、今回使用するネットワークはどこまで商用環境に近いものなのでしょうか。ソフトバンク IT統括 IT&アーキテクト本部 担当部長である松嶋聡氏によると、今回の実証実験のために専用の基地局を用意する訳ではなく、実際に商用で稼働している5Gのネットワークを用い、そこにSRv6 MUPを導入して実証をする形になるそうです。
ただし、実際のユーザーがSRv6 MUPのネットワークに接続できる訳ではなく、あくまで実証実験用のユーザーが用いる端末のみが接続する形になるとのこと。とはいえ実際に稼働している基地局などを経由する形となるため、以前の実証実験と比べればより商用の環境に近いことは確かでしょう。
なお、今回の発表はあくまで実証実験を開始したことであり、今後は実際に実証を進めて、その成果を確認していくとのこと。両社ともに成果を確認するには1~2年程度の時間がかかると見ているようですが、実際にSRv6 MUPが成果を出し低遅延など5Gのポテンシャルを有効に生かせる存在となることに期待がかかるところです。