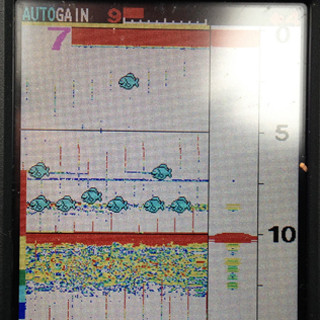ワカサギは都心近郊の湖にも放流されているケースが多い。ほとんどの場合、しっかりと管理されて育つのでコンディションの良い魚体に会えるのもうれしいところ。もちろん、その年の気象条件などにもよるが、初めて行く人でもきちんと知識を身に着けておけば、その日の晩に食べる分ぐらいは確保できるはずだ。そこで、ここからは初めての人でもワカサギ釣りが楽しめるよう、わたしが通っている都心からほど近い湖を例に、一日釣りを楽しむ手順を解説していこうと思う。
ワカサギ仕掛け選びのコツ
では、さっそく準備する道具から見ていこう。まずこれが無いと始まらないというのが竿とリール、そして仕掛けと重りだ。重りに関しては釣り場の水深や魚の棚(泳層)によって使い分けるので、いくつかバリエーションを持たせておこう。最初は3g~7gぐらいを中心に予備を持っていれば安心だ。竿とリールについてはすでに説明した通りなので割愛するが、仕掛けも専用のものをそろえておく必要がある。ワカサギの仕掛けはすでに出来合いのものが釣具店に並んでいる。ただし、その種類は数十種類以上あり、最初は選ぶのが大変だと思う。
仕掛けの選び方のコツは「針の数」と「針の種類と大きさ」で見ると分かりやすい。針の数は多ければ多いほど、一度に釣れるワカサギの量も多くなる。当たり前だが、10本針と5本針では、倍もチャンスが違うのだから当然といえる。しかし、ここで間違えると大変なことになる。10本の針がついていると仕掛けの全長も長くなり、餌を付けるのも一苦労だ。例え、10本針に10匹のワカサギが掛かっても、絡まないように外して、餌をチェックしていると、扱いが楽な5本針のほうは3回ぐらい手返ししているというケースだってある。
なので、最初は5本針の仕掛けから始めるのがオススメだ。わたしも通常使う仕掛けは5本針もしくは6本針がメインだ。それより多い針数の仕掛けは、よほどのことが無ければ使わない。自分が手返し重視の釣り方をしていることもあって、5本針だからといって釣果が落ちるようなこともない。この辺りは個人差もあるので、増やしたい人は慣れてきたと感じたら1本ずつ増やしていくとよいだろう。
また、ワカサギ釣りに使われる針は大きく2つの種類が存在している。一つはオーソドックスな袖針と呼ばれるもので、ある意味万能タイプといえる種類。もう一つは狐針といって、袖針に比べて針先が短く懐も細くなっているものがある。こちらは、ワカサギにとって吸い込みやすく、逆に吐き出しやすい。なので、アタリがあったら積極的に合わせていく釣り方にマッチする針だ。
針の種類については、まずは袖針をメインにしながら、ワカサギのアタリが出にくいようなときに狐針にしてみるという感じで、違いを試しながら自分の釣り方に合ったものを選ぶようにしていくのがよいだろう。わたしの場合は、狐針をメインロッドに、置き竿を追加するような場合に袖針といった使い方がメインだ。しかし、ワカサギ釣りになれてくるとその日、その時間の活性や状態によって、針もどんどん変えていくことになる。あまり難しく考えずに、両方用意しておくのが最適だ。ちなみに、一日に使う仕掛けは竿1本に対して、予備も含めて2~4個ぐらいは準備しておいたほうが良い。釣具店のバーゲンを利用してまとめ買いしておくのがオススメだ。

|

|
|
左が狐針、右が袖針。狐針は細身なので吸い込みが良い反面、きちんと合わせないとバレやすくなる。袖針はふっくらしているので、狐針に比べて吸い込みは悪いがバレにくい特長だある。その日の活性に合わせた使い分けが大切だが、慣れないうちは袖針だけでもオッケーだ |
|
また、針のサイズは湖に住んでいるワカサギのサイズによって選ぶのがベスト。7cm程度の小型が主流なら1~1.5号。10cm前後が混ざる場合は1.5号~2号。12cm以上が釣れるような湖では2号~3号といった具合だ。関東近郊の場合は、1.5号を中心に1号と2号をいくつか大目に持っていれば安心できる。
針の種類と合わせると相当な数を用意しなければならないが、最初は5本針の袖針、狐針ともに1.5号の仕掛けをそれぞれ4つ、計8個も買っておけばよいだろう。
小物にこだわれば一人前
また、釣れたワカサギを入れるクーラーと、生簀代わりのカゴ付きボウル、ハサミ、餌を入れるタッパー、などなど小物類も必要になる。釣れたワカサギは少しの間で構わないので、水を張ったボウルなどに入れて生かしておく。そうすると泥や胃の内容物を吐き出すので、臭みの無い食味になるのだ。それをクーラーボックスへ移すので、カゴ付きボウルが使いやすいというわけだ。クーラーは一番小型のもので構わないが、冷却材か氷を入れておくようにしたい。ワカサギは小魚なので痛むのが早く、真冬の日中でも気温が上がるような日にはなるべくマメにワカサギをクーラーに入れてあげよう。

|

|
100円ショップで手に入るカゴ付きボウル。半分ぐらい水を入れておき、釣れたワカサギをここで泳がせておく。泥を吐くのでおいしくなるのだ |
わたしはボートのへりにハリガネで固定するイケスを自作している。プラスチック製の小さなゴミ箱が材料で、底と四辺の下方に小さな穴をたくさん空けてある。水が循環するので、たくさんのワカサギを活かしたままにしておくことができるのだ |
ハサミはこの釣りでは特によく使う小道具のひとつ。仕掛けを切ったりするのはもちろん、餌を二つに割るのもこれがないと話にならないのだ。わたしは一番安いタイプを2個道具入れに放り込んでおき、もう一つ予備としてバッグの中に忍ばせている。寒い時期に手がかじかんでうっかり水の中に落とすこともあるし、仲間がハサミを忘れてきてもわたしが予備を大目に持っていれば安心できる。みなさんも最低2個は用意しておくと良いだろう。
餌については、また実釣編の際に詳しく解説するが、ワカサギ釣りでは「サシ」と呼ばれるハエの幼虫、すなわちウジムシをメインに使う。寒くても生きているし、体液や内臓の匂いがワカサギの食欲を誘うので非常に効果的な餌だ。「サシ」にはサイズがあってワカサギ釣りには「小」が最適。釣具屋で買うときには小を選んでいただきたい。
このほか、食紅で染めた「赤サシ」、ウサギのふんに寄生することで知られる「ラビット」などのほか、ユスリカの幼虫である「赤虫」、ブドウの木に卵を産み付けられる「ブドウ虫」も効果的な餌となる。使い分けは別の機会に説明するが、最初は「サシ」と「赤虫」の2種類を用意すればよいだろう。湖のボート屋にも売っていることもあるが、なるべく事前に釣具屋で買っておくと安心だ。
このほか、必須ではないがリールを竿べりにおけるようにするたたき台やロッドホルダーもあると便利な道具になる。餌を付け替えるときにロッドから手を放せるので手返しも早くなる。自分の竿とリールにマッチするものを釣具店のスタッフに選んでもらうようにすると失敗が少ない。また、狭いボートで釣ることが多くなるので、あぐら椅子や座布団なども準備しておくと良い。小物類も含めて一覧にしておくので参考にしていただきたい。