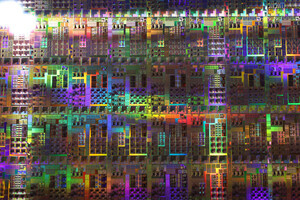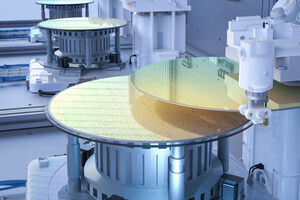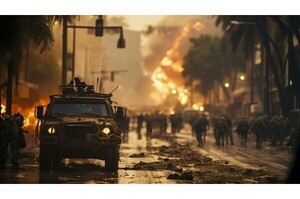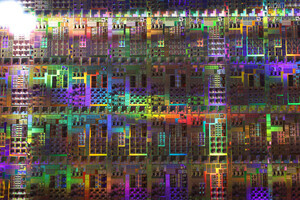トランプ大統領がTemuやSHEINなど中国発のオンライン通販業者を標的にした大統領令に署名しました。米国の通販業者に歓迎されるかと思いきや、一部の業者からは懸念の声が上がっています。「テックトピア:米国のテクノロジー業界の舞台裏」の過去回はこちらを参照。
これは、中国系の低価格オンライン販売業者の成長によって注目されるようになった米国の関税制度の「抜け穴」を、今や米国のビジネスも積極的に活用し始めているためです。
TikTokの規制強化を巡って、プラットフォームを収入源とする多くのクリエイターが反対の声を上げたのと同様に、米中間の緊張の高まりには、米国のビジネスにとって痛しかゆしの側面があります。中国企業への規制強化は必要だと考えながらも、その規制によって自社のビジネスモデルや収益に影響が出ることを懸念する米国企業は少なくありません。
抜け穴と指摘されるデミニミスルール
現在、米国の関税制度の「抜け穴」となっているのは、「1930年関税法」の改正で1952年に制定されたデミニミス(de minimis)ルールです。個々の輸入品の価値が800ドル(約12万1000円)未満であれば、関税やその他の税金が免除されます。
デミニミスは、通関手続きの簡素化と関税徴収コストの削減を目的とした貿易円滑化措置として導入された制度ですが、SHEINやTemuといった中国発のオンライン通販は関税を回避する手段として利用し始めました。個別の荷物として国外から個人に発送することで、実質的に購入者が輸入者となり、非課税の対象となるのです。
米下院特別委員会がまとめた報告書では、TemuとSHEINはデミニミス・ルールを利用して1日平均60万個の小包を米国に配送しています。米国税関・国境警備局のデータでは、2024年に13億件以上のデミニミスによる出荷が処理されており、これは2015年の1億3900万件から約10倍の増加です。
米国企業による「抜け穴」の活用
バイデン前政権もデミニミスルールの問題を認識していましたが、トランプ大統領は就任後、関税策でデミニミスルールに大鉈を振るいました。2月1日に署名したメキシコ、カナダ、中国からの輸入品に追加関税をかける大統領令では、800ドル以下の小口輸入品も課税対象に含めることが明記されました。
表向きは、簡易な通関手続きを悪用したフェンタニルなど違法薬物の流入を防ぐためとされていますが、実際にはデミニミスを利用するアジアの低価格販売業者を規制する狙いが明白です。
しかし、デミニミスを利用しているのはアジアの業者だけではありません。SHEINなどの成功を受け、米国のオンライン販売業者の一部も国外の製造拠点(中国、ベトナム、インドなど)から直接、航空便で商品を輸送する手法を採用しています。
例えば、Portlessという物流・貿易業務の効率化を目的としたプラットフォームを提供するスタートアップは、オンライン通販業者のデミニミス活用を支援するサービスを提供しており、約60の米国ブランドが利用しています。
ただし、航空便は輸送コストが高く、衣類のような軽量な商品には適していますが、サイズや重量が大きくなると非課税のメリットは薄れます。
そこで、大量の貨物をまず米国内の港で通関手続きし、そのままメキシコやカナダの倉庫へ再輸出する手法が広がりつつあります。通関・再輸出されることで、その後国外から米国に個別発送される各荷物が「再輸入」として扱われ、実質的にデミニミスの条件を満たすことが可能になります。
海運大手のMaerskがメキシコのティファナ地域にクロスボーダー貿易をターゲットとした物流施設を建設。XB Fulfillment、ShipBobやShipHeroといった物流企業が越境物流サービスを強化するなど、中国の通販業者だけではなく米国企業も利益を増やすたえにデミニミスを利用し始めています。そうした中でのトランプ関税騒動です。
米国内にとどまらず、日本を含む世界に波及
デミニミスの抜け穴が塞がれると、通関手続きが複雑化し、短期的には国外から大量に送られてくる格安商品の大渋滞が発生するでしょう。その後、増加するコストが商品価格に上乗せされ、低価格オンライン通販の買い物体験が悪化する負のスパイラルが予想されています。
デミニミス貨物については、制度の「悪用」と言われることもありますが、企業は法の枠内でビジネスモデルを構築し、利益を追求しているに過ぎません。その点で、デミニミスの活用は合理的な企業戦略といえます。
そもそも、デミニミス・ルールの非課税上限は2016年まで200ドルでした。それが国際貿易促進と米国経済活性化のために800ドルに引き上げられ、結果としてデミニミス貨物が爆発的に増加しました。
「De Minimis」とはラテン語で「最小限のもの」や「取るに足りないもの」という意味を持ちます。法律の分野では「de minimis non curat lex(法律は些細なことを取り扱わない)」という原則があり、影響の小さい事象を法的規制の対象としない考え方を示しています。
しかし、この10年、本来些細なものであるべきデミニミスは自由貿易促進や自国への産業回帰を訴える政治家に大きく振り回されてきました。輸出入に関わる企業は、その都度サプライチェーンの組み換えを迫られます。
特に今回は、貿易取引を円滑化する緩和から自国優先の規制強化への大きな変化となる可能性があります。それに伴う物流プロセスの再編の余波は米国内にとどまらず、日本を含む世界に波及することになりそうです。