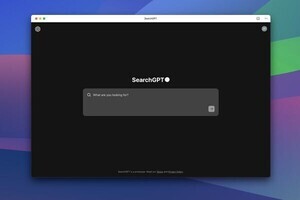iPhone 16/16 Proシリーズが発売されました。Apple(アップル)ファンの間でカメラコントロールが話題になる一方で、開発者の注目を集めるのはAppleが「iPhone 16シリーズの心臓部」と明言する「Apple Intelligence」と、その可能性です。
生成AIに対する消費者の心理
iPhone 16シリーズが発表された後、家族に「Apple Intelligenceって何ができるの?」と聞かれました。
「メールの文章を整えてくれたり、『子供が6歳の時に行ったディズニーランドの写真』みたいに話しかけると、その写真を見つけてくれたりとか...。今の検索だと『子供が6歳の時』と言っても、誰のどの写真か理解ってくれないでしょ」。
「ふ〜〜ん」と反応しているけど、全く興味なさそう。
「しばらくはそんなに役に立たないかもしれないけど、2〜3年後にはこれでスマホの使い方ががらっと変わるよ」と続けると...。
「それって、バブルに踊らされてるだけなんじゃないの。今だってSiriを天気予報と照明を点ける時にしか使ってないじゃん」。
「……」。
ChatGPTなど生成AIツールは、AIブームでよく認知されているものの、話題性に反して普及は伸び悩んでいます。ある調査結果では、生成AIツールを毎日利用している人はナレッジワーカーでも10%程度。一般消費者が日常生活で利用している割合はさらに低くなります。
Notionのようなテキストを扱うサービスが生成AIを導入する場合、多くは、要約、文章の提案やリライト、校正などを提供しています。しばらく前のAIモデルへのアクセスは無料、高性能な最新モデルの利用は有料というフリーミアム型のサービスモデルが多い中、消費者に有料プランを契約させるような力があるかというと、そうした需要は呼び起こされていません。「使えるなら使うけど、なければないでかまわない」が、生成AIに対する今の消費者の典型的な心理といえます。
Apple Intelligenceのベータ提供を開始
そんなニワトリと卵の問題に陥りつつある状況で、Appleが「Apple Intelligenceのために一から設計した」というiPhone 16/16 Proを発売し、10月にはApple Intelligenceのベータ提供を開始します。AppleはApple Intelligenceで生成AIの利用を普及させることができるでしょうか。
おそらく、最初は「Appleでもダメなのか」という反応は避けられないと思います。というのも、最初の機能セットは、文章作成ヘルパー、要約ツール、AI画像生成ツール、写真から不要なものを消去する機能など、すでに他で実現されている機能ばかり。使ってすぐに新味を感じられなさそうだからです。
でも、それだけでApple Intelligenceを判断するのは早計です。その強みは別のところ、生成AIモデルをAppleがプラットフォームに組み込んで提供していることにあります。
例えば、Appleは作文ツール(Writing tool)を、iPhoneやiPad、Macでテキスト入力が必要になるほぼすべての場所で利用できるように実装しています。文字入力と同じように、当たり前の機能としてAIライティングツールを提供するのです。
日本で発売されなかった初代iPhone(2007年)には、日本語入力機能がありませんでした。そのため日本語を入力する際には、Webで作成したものをコピペしたり、JavaScriptを駆使したりと本当に苦労しました。
翌年にiPhone 3Gが日本で発売された際には、OSに日本語入力が組み込まれました。当然のことと思うかもしれませんが、そうではないのが、今の生成AIの状況なのです。
ユーザーの生産性を向上させる誰にとっても有用な機能であるにも関わらず、文章をチェックしてもらうために、ChatGPTに移動したり、AIテキスト生成機能を備えたアプリを使ったりと手間がかかります。AIライティングツールがOSに組み込まれることで、「使えるなら使う」という人たちがAIテキスト生成をより活用できるようになります。
また、アプリ開発者が独自にAIテキスト生成機能をアプリやサービスに組み込まなくても、数行のコード追加で機能を提供できるようになります。画像生成については、テキストよりトラブルが起こる可能性が高いためより慎重に展開していますが、基盤技術として組み込んでユーザーや開発者の活用を促すアプローチは同じです。
生成AIモデルが組み込まれた新世代のSiri
これらはほんの始まりに過ぎません。その最初の到達点となるのが、今年6月にWWDC 24で行ったSiriの機能デモです。Siriを呼び出して「母のフライトの到着時間は?」と尋ねると、Siriがそのフライトの着陸予定時間を表示しました。
シンプルなやりとりですが、この背景では、ユーザーが「母」と呼ぶ人が誰であるかをSiriが理解し、母から送られてきたメッセージにあったフライト情報を取得、リアルタイムの運行状況に照らして最新の到着予定時間を表示しています。
スマートフォンは個人情報の塊であり、サードパーティのAIエージェントにそれらへのアクセスを許可することはプライバシーとセキュリティのリスクが発生します。
しかし、プライバシー保護を徹底しているAppleのプラットフォームで、Siriを使ったオンデバイス処理なら、パーソナルな情報を扱うタスクにもAIを活用できます。逆に、広告を収入源にユーザーデータを利用するビジネスモデルの企業はAI戦略においてこの点で不利な立場になります。
もう1つのポイントは、Siriとのやりとりだけですべてが完了していることです。もしこれを自分で調べるなら、メールやメッセージ、Safari、航空会社のアプリなどを行き来しなければなりません。
Siriで利用できるアプリやアクションは限られた範囲から始まりますが、順次拡大していき、サードパーティも利用できるようにします。
例えば、「昨日撮ったツインピークスの写真をDarkroomでシネマティックに仕上げて」と頼めるようになるでしょう。つまり、ユーザーは、アプリの機能を利用するために、アプリを開いてメニューを探し回ることなく、Siriから直接アクションを起こして完了できます。
これは、現在のアプリを中心としたスマートフォンの使い方を大きく変えるものになり得ます。ホーム画面にアプリアイコンを並べてタップする時代の終わりの始まりです。
ただし、乗り越えなければならない、いくつかの課題があります。大きなものとしては、Siriの進化と開発者による対応です。生成AIモデルが組み込まれた新世代のSiriが、本当にユーザーのことを深く理解し、自然言語でスムースにやりとりできる機能にならなければ、Appleが目指すApple Intelligenceの体験は実現できません。
そして、より多くのアプリによる採用が普及のカギとなりますが、この変化は開発者にとってメリットとデメリットの両方があり、デメリットを意識する開発者も動かさなければなりません。
Apple Intelligenceが便利な機能としてユーザーに支持され、その利便性を取り入れるアプリが支持されるという流れを作れるかが成功の分岐点となります。なので、10月のApple Intelligenceとともに登場する新世代のSiri(米国英語)が、Appleがアピールする通りの力を発揮できるかが非常に重要になります。