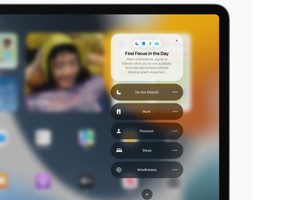大学入学の選考が試験ではなく成績重視で決まるとなったら、今の試験重視の入学選考と比べてどのような学生にとって有利になるだろうか?
カリフォルニア大学(University Of California)がSAT(大学能力評価試験)やACT(American College Testing)といった"共通テスト"を使用せず、「試験のない入学選考」を行っていく決定を下した。SATとACTは大学の入学選考に最も用いられてきた共通テストで、SATは英語力と数学、ACTは英語、読解、エッセイ、数学、科学の5つから成る。米国の大学進学希望者は共通テストを受けて、入学を希望する大学に申請書と共にそれらのスコアを提出してきた。同じ日に集まって同じ試験を受ける日本の大学入学共通テストとは仕組みが異なるが、入学選考を左右するペーパーテストという点では同じである。それを入学選考や奨学金プログラムの審査から除外する。
理由は「共通テストの不公平性」だ。例えば、貧困層の家庭に比べて、裕福な家庭の方が教材を買い与えたり、家庭教師を付けるなどテスト対策に投資できる。共通テストは、日本の入試のように年1回ではなく、SATの場合だと年に7回行われており、何回でも受けることが可能だ。ただし、1回の登録料が55ドルであり、経済的に苦しい家庭だと何度も挑戦させるのは負担である。所得格差のほかにも、母国語が英語ではない場合、複数の言語を使いこなせるスキルを持っていても、英語重視の共通テストでは不利であり、共通テストの結果からその生徒の本当の能力を知るのは難しい。
想像しやすいように誇張した比較例を挙げると、1人は裕福な家庭で、大学進学のための準備教育を施すプレップスクールに通い、1時間100ドル超の人気チューター(Tutor:家庭教師)を雇って、準備万端で臨んだSATで上位10%に入るスコアを獲得した。もう1人は、低所得者が多い地域に住む母子家庭の子供で、通っている地元の公立高校の進学率は低いが、アルバイトをしながら高校をストレートAの成績で卒業。だが、大学進学対策に割ける時間は限られ、1度だけ受けたSATは平均的なスコアだった。裕福な家庭の子供は問題なく希望の大学に進学できるが、共通テストに基づいた選考だと、SATのスコアが低い生徒は希望する大学に進学できない可能性がある。しかし、高校の成績や活動を評価したら学ぶ力と意志があるのは明らかで、その生徒の方が大学で学ぶ機会をより活かせるかもしれない。
共通テスト廃止は最近になって持ち上がってきた提案ではなく、長年議論が積み重ねられてきた。反対派の意見も紹介すると、所得格差で不公平が生じるというなら、高校3年間で優れた成績を維持するのにも所得格差は影響する。むしろ短期集中で試験対策できる共通テストの方が貧困層やマイノリティに逆転の機会をもたらしており、廃止はそのチャンスを奪うことになるとしている。また、共通テストで高スコアを目指す目標がなくなることで、大学進学を目指す高校生の向学心が薄れ、大学でやっていくための知識・学力の準備が整わなくなる可能性も指摘されている。
どちらの言い分にも一理あり、綱引き状態が続いた中で、共通テストを使わない選考を試す大学が現れ始め、そうしたケースから標準化されたテストよりも成績の方が柔軟で公平であるという調査結果が出てくるようになった。例えば、カリフォルニア大学のリバーサイド校は半数近い学生がマイノリティで60%が奨学金を受けているが、学校の成績が良くても平均的なSATスコアしか持っていなかった学生の卒業率が低いかというと、SATで上位スコアだった同級生とほとんど変わらなかった。成績とテストを組み合わせた選考の方が、より多くの学生に大学で学ぶチャンスを与えられ、多様性を取り入れられる。
カリフォルニア大学でも意見が分かれて激しい対立が起こり、一時は訴訟問題に発展した。2020年に当時の学長が共通テストの提出を課すのを2024年まで停止し、平行して平等に選考できる新たなテストを模索する猶予期間を設けることを提案した。しかし、新型コロナ禍で高校生が共通テストを受けるのが困難な状況になったのをきっかけに廃止論の勢いが強まった。新学長の指示で入学選考改革に取り組んでいた学術委員会が、大学での初年度の成績を予測する上でわずかな有効性しか確認できない共通テストを採用するより、小中高のシステムとの緊密なパートナーシップを形成し、大学進学コースへのアクセスをサポートしたり、選考スタッフのトレーニング予算を拡大するといった他の措置を講じるように勧告したことで、今回の判断となった。Los Angles Timesによると、11月の理事会においてMichael Brown副学長が「カリフォルニア大学は、現在、そして将来も、試験のない入学選考を実践し続ける」と宣言したという。
カリフォルニア大学は10校の州立大学から成る米国最大規模の大学システムである。シリコンバレー地域には、最初のキャンパスであるUCバークレー校がある。同校はマンハッタン計画への貢献やフリースピーチムーブメントなど米国の歴史に関わってきた大学であり、UNIX系のBSD(Berkeley Software Distribution)が誕生し、地元のテクノロジー企業からの支援を受けIT・コンピュータ分野で数多くの価値のある成果を生み出している。すでにスミス・カレッジやニューヨーク大学などが先陣を切っているが、規模が大きく、多くの高校生が目標とし、米国の高等教育における権威を持つカリフォルニア大学が共通テスト廃止を選択したことで、入学選考のあり方が変わっていくと見られている。
とはいえ、廃止によって従来の共通テストのデメリットがなくなるだけで、どのように公平な選考を実現するかはこれからであり、先行きはまだ不透明だ。大学ごとの選考の独自性が強まり、大学によっては共通テストの方が公平だったということも起こり得る。個人的には、脱"共通テスト"で野心的な学生が増える可能性に期待したい。IT・コンピュータ分野ではガレージより大学の寮から誕生するスタートアップの方が多いのだ。そうした意味でカリフォルニア大学が今後どのような入学選考を実践していくか注目していきたい。
ただ、これで能力のある子供達が希望の大学に入りやすくなるかというと、米国で高校生の子供を持つ親は今、大学の授業料高騰に頭を悩ませている。最近のインフレの話題でよくガソリンの価格が取り上げられるが、1980年代に1.19ドル/ガロンだったガソリンが今は3.41ドル/ガロンである。年率2.7%の上昇、「高くなった」と思う。だが、4年生大学の授業料はその約3倍のスピードで上昇しており、公立大学は年率6.7%、約1,400%の増加である。
この高等教育における40年におよぶ容赦のないインフレが、米国の中流階級の繁栄の最大の障害になっており、経済的に苦しい学生は条件の悪い奨学金や学生ローンを利用するギャンブルで教育のチャンスをつかまなければならないのが現状だ。高等教育のチャンスをより平等にというなら、そちらの問題も何とかしてほしい。さもなければ、高等教育は次のディスラプションのターゲットになることだろう。