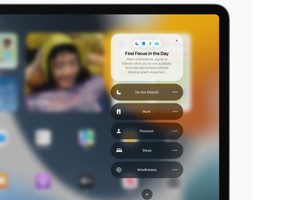しばらく前に、The Vergeに掲載された「ファイルが見つからない:検索エンジン育ちの子供達がSTEM教育を一変させる」というレポートが話題になった。天体物理学者のCatherine Garland氏が大学の講義でシミュレーションソフトを使ってジェットエンジンのタービンをモデル化させたところ、学生達が次々に予想外の助けを求めてきた。「ファイルが見つからない」というエラーメッセージが出るという。そこで、どこにファイルを保存しているか聞いたところ、学生達は一様に不思議そうな顔をした。スマートフォンとクラウドで育ってきた学生達はフォルダやファイルの概念を持っていない。必要な情報やデータは検索で見つけ出す。だから、「プロジェクトをどこに保存したの?」という質問の意味すら分からない。そうした問題は2017年頃から見られ始めていたそうだ。
そんなことでよく大学のエンジニアリングまで辿りつけたと思うが、米国の高校では上位レベルのSTEMコースを取るような生徒以外は、ターミナルでファイルをナビゲートするようなことにはならないそうだ。皮肉なことに今は、デジタル環境で育ってきた子供達ほどエンジニアリング教育におけるコンピュータリテラシーが低い。
でも、そう断じるのはパソコン世代の大人達の言い分ともいえる。教授の1人は「スマートフォンを取り上げて、Windows 98を与えろ」と言うが、それが現実的なソリューションではないのは明らかだ。
学生達の変化に直面して、ディレクトリ構造を当たり前と思っていた教授達は、自分達が時代遅れになるアプローチにしがみついているのではないかと疑い始めている。学生にディレクトリ構造を学ばせる別のコースを用意することも考えたが、それが解決になるか疑う声が上がった。今の若者が成長して自分達でツールを書くようになった時に、今のやり方を引き継いでいくとは思えないからだ。そのツールは全く違ったアプローチに基づいたものになり、それは"進化"という見方ができる。
フォルダ分けすら分からない学生をパソコン世代は不思議に思うが、逆にパソコン世代にSnapchatやTikTokを使わせたらどうなるだろう。シンプルな見た目に最初は「簡単に扱える」と思うだろう。しかし、スマートフォンのジェスチャー操作を前提に作られたUI(ユーザーインターフェイス)に何が何だか分からなくて少なからず混乱するはずだ。でも、今の学生達はSnapchatやTikTokを自然に使いこなす。スマートフォン世代のためにスマートフォン世代が作ったUIを持つアプリだからだ。
米Facebookが社名を「Meta Platforms(Meta)」に変更した。同社がメタバースの企業を目指すのは驚くことではない。5年前に公表した10年間のロードマップですでにそうした方向を示していた。
-

2016年に開発者カンファレンスF8で示したロードマップ。当時から3年後(2019年)までに世界中の人々を結ぶFacebookのミッションをべースとしたエコシステムが形になり、プラットフォームの安定に伴って、5年後(2021年)には「Instagram」や「WhatsApp」といった他のアプリが成長。ネットにおける人々のコミュニケーションの主流がテキストから画像・動画、そしてVR/ARのようなより没入感のある体験へと広がっていく。10年後(2026年)に向けて、VR/AR、AI、コネクティビティといった技術を次の成長ドライバとしていた。
ただ、社名まで変更したのは大きなサプライズであり、「メタバース」という言葉を前面に押し出しているのは気になるところだ。概念でしかない言葉の一人歩きが過ぎると誤解を生み出しかねない。例えば、2007年にiPhoneが登場する前にすでに「スマートフォン」という言葉は存在したが、その頃に「携帯の未来はスマートフォンになる」と言ったら、BlackBerryやTreoのような物理キーボードを備えた携帯電話のことだった。「スマートフォン」という言葉のアピールではなく、iPhoneというスマートフォンが出てきたから、iPhoneから始まるモバイルプラットフォームの歴史が始まった。
Facebookがメタバースの企業を宣言する約80分のビデオを見たが、VR(仮想現実)/AR(拡張現実)、ソーシャル、空間的な体験がどうあるべきかというコンセプトで構成されており、SF的な味付けが濃く、その多くはぎこちないものに思えた。例えば、Webページのリンクのような移動を「テレポート」と呼んでいたが、"中二"感あふれる表現過ぎて、自分が使うのは気恥ずかしい。3Dの世界がどのように見えるかということより、次世代のインターネットでソフトウェアがどのように機能するべきか、SnapchatやTikTokのような新しい時代のソフトウェアが生まれる可能性を確かめたかったのだが、その期待が十分満たされる内容ではなかった。
新型コロナ禍を経て米国のStarbucksでは、スマートフォンでオーダーして店舗で受け取るオンラインオーダーが当たり前になっている。モバイルアプリのStarbucksは仮想的なもう1つのStarbucksであり、すでにStarbucksの前で私達はバーチャルなStarbucksとリアルなStarbucksを行き来している。メタバースという言葉に懐疑的でも、これからそうした変化が加速していくことを否定する人は少ないだろう。
没入感のある体験もその1つであり、VR/ARも重要な存在である。しかし、モバイルに続くインターネットの「次の形」へのドライバになるかというと、Webがプラットフォームとして広く一般に普及する前に人々にネットの価値を伝えたAOL、フィーチャーフォン時代のiPhoneに比べると、今の10~20代の間でVRは積極的に利用されてはいない。
今の若者や子供達に新たなネット体験をもたらしているのは、「Fortnite」、「Minecraft」、「Roblox」といったゲームである。これまでのインターネットの中でゲームは傍流だが、彼らにとってバーチャルなゲームの世界での行動が、友達とのコミュニケーションやインタラクション、クリエーション、そして経済活動を含めて日常になろうとしている。そうして社会に出てきた若者が将来、現実のアイテムの価値が分からずに上司を困惑させるようなことが起こるかもしれない。
その点で、現実世界の全てがインターネットに接続するビジョンを掲げるTencent(中国でRobloxの配信を開始)、それに対抗するByteDanceの方が、未来感は薄いものの、Facebookより地に足をつけてメタバース実現に進んでいるように思う。Facebookについても、Metaへのリブランディングや仮想現実の世界を見せたことより、オープンスタンダードに従った相互運用性をサポートするAPIの構築、そしてクリエイターエコノミーを支援する取り組みを表明したことの方が今回のイベントで重要なポイントだった。