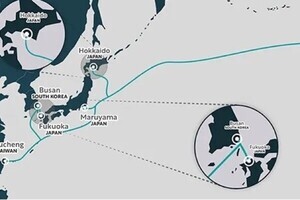前回は、台湾のスタートアップ企業を取り巻く現況についてお伝えした。今回からは、今まさに日本市場進出を目指しているスタートアップ企業たちを紹介していこう。1社目は、e-ラーニングプラットフォーム「hahow」を運営する思哈だ。
オードリー・タン氏も開講
思哈は2015年に設立された、e-ラーニングプラットフォーム「hahow 好学校」を運営するスタートアップ企業である。現在は従業員約150名、2022年に資金調達Bラウンドを完了し、1000万米ドルを調達した。2022年の売上は日本円にして約17億円だ。
hahowにはさまざまな講座があり、イラストの描き方や登山のノウハウといった趣味に寄ったものから、プログラミングやビジネスに特化したものまで、内容は幅広い。以前には、台湾政府とのコラボレーション企画として、デジタル担当大臣を務めるオードリー・タン氏によるデジタルコミュニケーションの講座が無料で開設されたこともある。ユーザー数は現在100万人を超えており、「台湾最大の学校だと言われることもある」と同社 CEOのアーノルド・チャン(Arnold Chiang)氏は言う。では、hahowの特長は何か。
-

思哈 CEOのアーノルド・チャン氏
チャン氏はhahowを「Udemy + Makuakeの新たなモデル」だと説明する。hahowでは専門スキルの有無を問わず、誰でも講座を開講することができる。講座を開講したい人はまず短いプロモーションビデオを作成し、hahow側に提出。講座の内容に関するフィードバックを経て、何名のコースで開講するのかと、そのための資金として目指す目標金額を設定 し、クラウドファンディングを開始する。目標額に達したところで、正式にhahowで講座を開講するための手続きに進むという流れだ。
この仕組みのメリットについてチャン氏は「クラウドファンディング期間中に、受講希望者とやり取りをし、市場が求めているものをしっかりとリサーチできる点にある」と言う。また、開講前にクラウドファンディングで目標額が達成されているため、講師が基本的な収入を確保できるというメリットもある。チャン氏によると、過去には1つのコースで28,000人を集め、日本円で1.6億円程度稼いだ講師もいたそうだ。
-

hahowの講座の一例
「Z世代や、α世代といったセルフラーニングに積極的な世代に対し、誰でも“先生”になれる環境をつくっていきたいのです」(チャン氏)
2020年にはhahowの企業向けサービスとして「hahow for Business」もリリース。現在は約11万人が自社向けにパーソナライズされたトレーニングサービスを利用している。さらに、台湾の金融サービス企業と組み、hahow内の指定の講座を受講すれば、採用試験に一定の加算ポイントを加えるといった取り組みも始まっているという。
日本市場の魅力とeラーニングの可能性
同社は、2024年上半期には「hahow for Japan」をリリースしたいと考えている。チャン氏は日本市場について、1億人以上がいる大きな市場であることに加え、「職人、匠といった文化が日本には根付いており、良いコンテンツがある」と語る。一方で「クリエイターにフレンドリーなプラットフォームはあまりないのではないか」と感じているそうだ。
「だからこそ、我々がそこに立ちたいのです」(チャン氏)
では、日本市場でのベンチマークはあるのか。チャン氏は「Schooが最も近い」としつつも、配信モデルや料金体系の違い、何よりもクラウドファンディングの有無など、差別化を図れる点は多数あると説明した。
すでに多数のサービスが提供されている日本のe-ラーニング市場で、hahowが今後どのような展開をしていくのか、大いに期待したい。