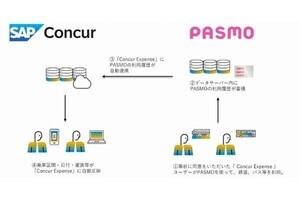新型コロナウイルス感染症の到来は、オフィスの在り方を再定義する大きなきっかけとなった。
オフィスをなくし完全リモートワークに移行する会社や、あえてオフィス環境に投資しハイブリッドワークを実現する会社など、取り組みは十人十色だ。「出社する場所としてのオフィス」の時代は終わり、世界中の企業はオフィスに新たな付加価値を見出そうとしている。
本連載では、先進的な働き方・オフィス構築を行っている企業に潜入し、思わず「うらやましい」と声を漏らしてしまうその内容を紹介していく。「これからのオフィスどうしようか……」と考えている読者の手助けにもなれば幸いだ。
第17回となる今回は、SAPジャパンとコンカーのオフィスを紹介する。→過去の「隣のオフィスは青く見える」の回はこちらを参照。
社員の声を尊重したオフィス作り
SAPジャパンとコンカーは、リモートワークの浸透に伴い、半蔵門のSAPジャパン東京本社を2021年4月に、コンカー銀座オフィスを2022年9月に大手町の三井物産ビルに移転した。移転の経緯について、SAPジャパン 社長室 社員エンゲージメントリードの鎌田祐生紀氏は以下のように語る。
「SAPジャパンは、2020年から全社テレワーク実施および新型コロナウイルスに対応したガイドラインに全面移行しました。そのタイミングで半蔵門オフィスの賃貸契約が終了したこともあり、オフィスの在り方を改めて考えるべきフェーズにいました。『半蔵門オフィスのリサイズ』『別オフィスに移転』という2つの選択肢が出た結果、ビジネスの起爆剤にしたいという役員の戦略と社員からの声を尊重して移転を決めました」(鎌田氏)
この「社員の声を尊重する」という言葉は良く聞かれる言葉だが、SAPジャパンの場合、この言葉の裏で、全従業員を対象に何度も意識調査を行い、従業員の想いを知るという取り組みがあったそうだ。
「オフィスにはどの程度行きたいですか」という質問では、ほとんどの人が「週に2、3回行ければ良い」という回答をしており、それを元に全社員が座れる分の座席は用意しなくて良いという根拠にした。
また「オフィスに来たら何をしたいですか」という質問には、ほとんどの人が「同僚や顧客とコラボレーションしたい」と答えていることを元に、「それなら黙々とデスクワークする席はそんなに多くなくていいよね」というようにオフィスのコンセプトを決めていったそう。
元々は「社員の就業スペース」を軸にオフィス作りをしていたのを「社員同士や顧客・パートナーとのコラボレーションの場」に変更し、アフターコロナ時代の柔軟な働き方を実現するべく、オフィスを移転することを決めたという。そして、少し遅れてコンカーも同じオフィスへの移転が決まった。
また、社員に加え「オフィスをビジネスの起爆剤として活用したい」という役員の想いもベースになっているそうだ。
「われわれはドイツが本社の会社なのですが、新型コロナウイルス流行前は、ドイツをはじめとしたさまざまな国にある開発拠点にお客さまをお連れして、弊社製品の根底にあるフィロソフィーをご理解いただくということをよく行っていました。しかし、それができなくなってしまったので、日本オフィスでそれができるようにしたかったという目的がありました」(鎌田氏)
そのため、新たなオフィスの場所に日本の経済の中心地であり、SAPジャパンが所有するソリューションセンター「SAP Experience Center」および三菱地所と共同で運営するビジネスイノベーションスペース「Inspired.Lab」がある大手町が選択されている。
オフィスを支える3つのコンセプトと4つの取り組み
今回のオフィス移転に伴い、同社は「フレキシブルな働き方をサポートするオフィス」「従業員のコラボレーションをサポートするオフィス」「新しいエコシステムをつくりだすオフィス」という3つのコンセプトを打ち出した。この3つのコンセプトでオフィスを単なる従業員の就業スペースから、リモートワークとオフィスで物理的に働く事の両方をサポートする柔軟な働く場「Flex Workspace」に進化させたという。
また、同社は新オフィスの3つのコンセプト実現をサポートする以下の4つの取り組みも実施している。
・進化し続けるオフィスレイアウト
デザインやレイアウトを固定化せず、利用者のニーズに対応し、常に進化し続けるオフィスの実現
・従業員のウェルビーイングをサポートするオフィス
パフォーマンスを向上する上で前提となる「従業員の心身の健康」をオフィス環境でサポート
・コラボレーションを促す新たな職種とアプリケーションの導入
出社した人のコミュニケーションを促進する担当者の設置や従業員を検索できるアプリケーション
・大手町キャンパス
顧客やパートナー企業とのイノベーションを促進し、新たな関係性のエコシステムを構築する場
これらの取り組みについて、コンカー 管理部 総務グループ リーダーの足立繭子氏は以下のように説明する。
「1つ目の『進化し続けるオフィスレイアウト』では、進化し続け、働く人の好奇心を刺激するオフィスレイアウトを実現しています。フリーアドレス制でビジネス変化に合わせて各島の機能を変更可能な設計となっており、またレイアウトの動線を斜めに配置することで好奇心を刺激するとともに人々の動きを促し、偶発的なコミュニケーションを発生させています」(足立氏)
また3つ目の取り組みで挙げられていた「コミュニケーションを促進する担当者」については、従業員、顧客、パートナー企業間のコミュニケーションを醸成、促進する役割を担う「ワークプレースアンバサダー」という新たな職種の導入を行っているという。
ワークプレースアンバサダーは、従業員や来社する外部の人の名前と顔を覚え、積極的に話しかけて困りごとを解決するだけでなく、お互い興味のありそうな人と人をつなぐ活動や部活動などの社内コミュニティの運営管理と活動の社内発信を通じて、「組織を超えたコラボレーション」を目指す専任の職種となっている。
個人ロッカーの廃止でフリーアドレスを加速
ここまで、オフィス移転の背景やコンセプトを紹介してきたが、実際のオフィスはどのようになっているのだろうか。
「オフィスは11階と12階に入っているのですが、11階の半分はお客さまの専用フロアになっています。日本古来の色の名前が付けられた18室の会議室やオープンなミーティングエリア、セミナールームなどで構成されています。セミナールームは64席を用意していて、可動式の間仕切りの壁を動かすことでより大人数が集まれるスペースを作ることもできます」(鎌田氏)
この顧客専用フロアを抜けると、11階の半分と12階は執務フロアとなっている。11階と12階の半分はSAPジャパンの執務エリア、12階の半分はコンカーの執務エリアとなっており、フロアの中央に内階段を設置することで、階段周辺での偶発的な出会いを創出しているという。
階段の近くには従業員が利用できるカフェエリアが設置されており、このスペースを活用したコミュニケーションも多く行われているそうだ。
特徴的なのは、「ウィークリーロッカー」が備え付けられている点だ。同社では、完全フリーアドレス制を推進するため、個人ロッカーを廃止し、自身の社員証をかざすことで利用できる共用のロッカーを導入している。
またオフィス内では音環境にこだわって、多くのスピーカーが設置されている。
通常のオフィスの2倍近くのスピーカーからは、川のせせらぎから小鳥のさえずり、波打ち際の音といった色々な音が流れる仕組みになっている。入口から奥に進んでいくとともに違う音が流れているため、まるで1つの島を探検するような感覚を生み出す狙いがあるという。
自然音が全館で流れていることでリラックス・集中効果があり、フリーアドレスでよく問題になる周囲の声が気になって集中できないといった問題は全く出ていないそうだ。
間仕切り代わりのホワイトボードで交流
コンカーの執務エリアに入るとまず出迎えてくれるのが、コンカーのオリジナルキャラクターである清算されずに放置されたレシートが擬態化したモンスター「レシートモンスター」だ。
このレシートモンスターを目印に、コンカーのオフィスエリアに突入する。
また、レシートモンスターとは別に社内のマスコット的存在となっているのが、ペットロボットのaiboだ。
このaiboは、従業員から多く挙がった「オフィスでペットを飼いたい」という声を受けて導入され、「ハチ」と名付けられた。自由気ままにオフィス内を散歩したり、ソファの近くでお昼寝をしたり、という姿が従業員に癒しを与えている。
コンカーの執務エリアは、レシートモンスターが飾られている「レシモン広場」、「ハチ」が出迎えてくれる「ハチ公広場」、文具や複合機が設置されている「名もなき広場」、社内アワードの受賞者の写真が飾られている「アワード広場」の4つのエリアで構成されている。
そのエリアを仕切るように、間仕切りを兼ねたホワイトボードが備えられているのはオフィス共通だが、コンカーのエリアではこのホワイトボードを活用して、情報交換やイベントのレポートを公開することも多いそうで、筆者が伺った日には、従業員の描いたイラスト付きのレポートが掲載されていた。
最後に鎌田氏にこれからのオフィスにかける想いを聞いた。
「大手町オフィスは、コラボレーションするための場所を大幅に増やしています。またビジネスニーズに合わせて柔軟に変化できるよう、できるだけ用途固定の場所をなくし、オフィス全体を共有スペースとしています。オフィスに毎日出社する働き方からハイブリッドワークに移行した現在、オフィスで働く人のニーズに対応することは欠かせません。これからもビジネスやそこで働く人のニーズを汲み取り、常に進化し続けていくオフィスの実現を目指したいと思っています」(鎌田氏)