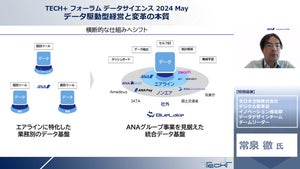先日発表されたMM総研の調査によると、2010年上期(4~9月)の携帯電話端末の総出荷台数のうち、スマートフォンの比率は11.7%を占める223万台で、前年同期比の106万台から約2倍の伸びとのこと。今年に入って爆発的に伸びているとも言えますが、逆に、流通している全携帯電話端末の1割強でしかないという見方もできます。今後、携帯端末市場におけるスマートフォンのシェアはどのように推移するのでしょうか?
キャズム理論の「16%」の境界線
|
|
有名なマーケティング理論である「キャズム理論」によると、発売されて間もない時期に購入するイノベーター層(2.5%)、次いで情報感度の高いオピニオンリーダーと呼ばれる層(13.5%)が購入し、この2つの層の合計である16%のシェアを超えるか否かがヒット商品になるかならないかの境界線(キャズム)であるとされています。
携帯電話端末全体の契約数を仮に1億1300万とすると、この16%の境界線は約1800万台。正確な台数は公表されていないので推測になりますが、直近の販売台数を見る限り、ようやくこの境界線(キャズム)に到達するかどうか……といったところではないでしょうか。
当研究所がスマートフォンに詳しい有識者に対して実施した10月度の調査では、75%の有識者が「2015年までにスマートフォンの販売台数が通常携帯電話端末(フィーチャーフォン)の販売台数を追い抜く」と予測しています。この予測通りにスマートフォンが販売シェアを伸ばせば、シェア16%のキャズムを超えて大ヒット商品に……ということになるのですが、そうなるにはまだいくつかの課題が残っているように思います。
キャズム理論(イノベーター理論)では、シェア16%の壁を超えてヒットするには、上述のような「オピニオンリーダー層」にいかに支持されるかが重要だとされています。他の消費者への影響力を持つとされるオピニオンリーダーたちの支持が得られない場合、その後のクチコミネットワークが形成されず、市場拡大にストップがかかるというのがその理由です。
では、現在発売されているスマートフォンは、これらオピニオンリーダーの支持を得られるだけのベネフィットを有しているでしょうか。
「スマートフォン」は「ケータイ」よりも優秀か?
海外ではすでに大ヒットとなっているスマートフォンですが、日本国内での普及が海外に比べて遅いのは、日本の国内市場が鈍感だったからではなく、独自の機能を持った優秀な携帯電話端末がすでに普及していたからだと筆者は考えています。事実、当初日本国内で発売されていたスマートフォンは、既存の携帯電話端末に比べて非常に使いづらいものでした。
では現在のスマートフォンはどうでしょうか。
当研究所の調査では、iPhoneが登場してマルチタッチが標準となってから、使ったことがないユーザーから「使い方がわからない」という意見はあるものの、利用ユーザーからスマートフォンに対する「使いづらい」という声はほとんど聞かれなくなりました。ユーザーインタフェースや使用感は、以前に比べて格段に進化していると言えるでしょう。
ただ、そのほかの機能比較ではどうでしょうか。
Webサイトの閲覧や情報収集、エンターテインメント、ゲームなどの充実した専用コンテンツ、デコレーションメールやムービーメールなどの豊富なコミュニケーション手段、おサイフケータイ機能などの付加機能など、日本の携帯電話端末はすでに充実した機能を多数有しています。むしろ、「ようやくケータイの機能がスマートフォンに搭載され始めた」というのが正直なところでしょう。唯一、大きく異なる点は、スマートフォンには「Wi-Fi(無線LAN)」への接続機能があるという点ですが、これも首都圏でさえ、外出先でそのメリットを思う存分発揮できるほどインフラが整備されているというわけではないので、そのベネフィットを享受できるのは一部の消費者層のみだと考えられます。
現在のスマートフォンは、料金面で特に家計に優しい(コストダウンになる)わけでもなく、飛びぬけてデザインがカワイイわけでもなく、通信環境が既存の携帯に比べて特につながりやすいというわけでもありません。現在各社が放映しているTVCMを見ても、「新しい」「これからの携帯端末」という漠然としたイメージの訴求ばかりです。中には「ケータイ端末の機能を一部搭載しました」というCMもあるくらいで、既存の携帯端末とは異なる消費者にとってのベネフィットが明確に提示されていないのが現状です。
普及のカギを握る主婦層の反応は?
この10月に当研究所が主婦のSNSサイト「ママイコ」と共同で実施した調査では、「スマートフォンに興味がある」と回答した主婦は全体の約4割弱でした。
今年の5月に実施した同様の調査では、スマートフォンという名称を「理解している」と回答した主婦が14.9%、「なんとなく知っている」と回答した主婦が34.9%であったことを考えると、これでも格段に注目度は高まっていると言えると思います。
スマートフォンが爆発的に普及するには、今後このような「興味を持ち始めた層」に対し、どんなベネフィットを提示できるかが課題になってくるのではないでしょうか。
これから登場する国内メーカーのスマートフォン端末が待ち遠しいですね。
今回引用した調査データは下記のMMD研究所Webサイトで公開しています。
スマートフォン、携帯キャリア関連の調査データ一覧 - MMD研究所
<本稿執筆担当: 田川悟郎>
著者紹介
MMD研究所
![]()
MMD研究所(モバイル・マーケティング・データ研究所)は、モバイルユーザーマーケットのリアルな動向を調査・分析し、社会へ提供することを目的として2006年9月に設立されたマーケティングリサーチ機関(運営は株式会社アップデイト)。本コラムでは、同研究所による調査データをもとに、ヒットにつながる効果的なマーケティング手法について考察していきます。