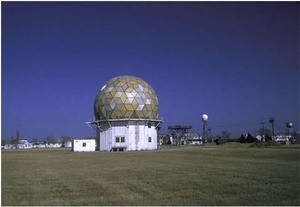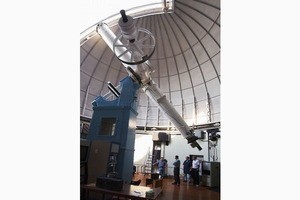旅行に行く時、つい心配になって「あれも必要ではないか、これも必要ではないか」といって荷物が膨らみ、重くなってしまうのはよくある話。ただ、旅行だと「いざとなったら現地調達すればよいか」と開き直って持ち物を減らす手があるが、戦場に赴く兵士だと、そうも行かない。
歩兵の持ち物は多い
朝霞駐屯地にある陸上自衛隊広報センターに行くと、「装具装着体験コーナー」というのがあって、そこで背嚢を背負ってみる経験ができる。これが重いのである。
もともと、着るもの、食べるもの、そして武器弾薬と荷物が多いのに、近年になって「ハイテク化」が進んだおかげで、さらに荷物が増えた。コンピュータ機器に通信機器、暗視装置、そしてそれらを作動させるためのバッテリ。
今や、歩兵が持ち歩く荷物の重量は40~50kgに達しているといわれる(もちろん、任務様態によって違いはあるだろうけれど)。機関銃の担当なら、機関銃は自動小銃よりも重い上に、弾の数が一挙に増える。これが、迫撃砲や対戦車ミサイルの担当だと、いったいどうなることか。
いくら身体を鍛えていても、重い荷物を背負って歩いて、戦闘任務に入る前に疲弊してしまったのでは具合が良くない。そんな事情もあり、歩兵の負荷軽減は各国で厄介な課題になっている。そこでアメリカ陸軍では考えた。「自分で背負って歩く代わりに、荷物運びが随伴すれば良いのではないか?」
といっても、生身の人間を随伴させるのでは人手が余分に必要になる。しかも、歩兵に随伴すれば最前線まで出て行くことになるが、そこに荷物運び専門の素人を送り込むことはできない。そこで考え出されたのがロボットやUGV(Unmanned Ground Vehicle)の活用だった。
四足歩行ロボット
日本でも知られている、ボストン・ダイナミクスという会社がある。ここが2010年に米国防高等研究計画局(DARPA : Defense Advanced Research Projects Agency)から3,200万ドルの契約を得て開発に乗り出したのが、荷物運び専門の四足歩行ロボット・LS3(Legged Squad Support System)。DARPAのTTO(Tactical Technology Office)と海兵隊のMCWL(Marine Corps Warfighting Lab) が組んだ案件である。
LS3はその名の通り、分隊(squad)レベルで配備するもので、足が生えていて自力で歩く。これに荷物を背負わせて、歩兵に随伴させればいいというわけだ。搭載量は最大400ポンド(約182kg)というから、4~5人分の荷物を引き受けられそうだ。
なぜ四足歩行にしたのか。それは「車両が入れないような地形のところでも入り込めるように」という理由だという。歩兵の荷物を歩兵の代わりに運ぶのだから、歩兵が行けるところならどこでもついて行けないと具合が悪い。
そして実際に、四本の足で歩くLS3が出来上がり、デモンストレーションも行われた。最初に屋外で走行(いや歩行か)のテストを実施したのは、2012年2月のこと。ちなみに航続性能は24時間・20マイル(約32km)だという。
ただ、この四足歩行ロボットの計画は沙汰止みになってしまった。「騒音が大きすぎる」という理由だ。確かに、四本足をガチャコンガチャコン動かすのだから、あまり静かにはなりそうにない。隠密裏に的に忍び寄らなければならない場面で、随伴してきた荷物運びが騒音を出すのでは、お話にならない。技術的なチャレンジとしては面白いのだが。
ちなみに、同じボストン・ダイナミクスがDARPAから別口の契約を得て開発した四足歩行ロボットが「チーター」。M3(Maximum Mobility and Manipulation)計画の下で開発したもので、時速18マイル(約29km/h)の速度記録を作った。
六輪駆動の無人車両
一方、ロッキード・マーティン社が開発して2010年にデモンストレーションを実施したのが、6×6の無人車両SMSS(Squad Mission Support System)。こちらも名前の通り、分隊レベルでの運用を想定しているが、搭載量はLS3の3倍・1,200ポンドもある。全長3.6m、全幅1.8m、全高2.1m、自重1,724kg。
こちらは試作した車両をアフガニスタンに持ち込んで、現場で評価試験を実施したことがある。また、イギリス軍が評価試験を実施したこともある。
SMSSで面白いのは「移動充電器」としての機能を持たせるテストが行われたところ。PPE(Portable Power Excursion)と題し、充電用の「走る電源車」を務めた。また、荷物運びだけでなく、衛星通信経由で遠隔操作できるようにして「無人監視プラットフォーム」に仕立てる実験を行ったこともある。
SMSSには笑い話(?)がある。SMSSの搭載量は1,200ポンド(540kg)なのに、現場で4,000ポンド分の土嚢を積んで傾斜30度の急斜面を登らせたことがあり、それを聞いたメーカーが「2度とやらないで」と止めたのだそうだ(スキーやスノボの経験者ならおわかりの通り、30度といえば相当な急斜面である)。
このSMSSと同種の「荷物運び用の無人車両」としては、ノースロップ・グラマン社のCaMEL(Carry-all Modular Equipment Landrover)もあった。
また、オーストラリアでも同種の車両が登場した。それが、演習「タリスマン・セイバー2019」に持ち込まれたMAPS(Mission Adaptable Platform System)。全長2.33m、全幅1.86m、全高0.98m、重量950kgというから、SMSSと似たサイズだ。電動式で最高速度は8km/h、搭載量は500kg、航続時間6時間だという。
無人荷物運びの課題
個人的には、この手の無人荷物運びについて回る課題として、ナビゲーションがあると考えている。といっても、測位・航法の話ではなくて、「誰について行くか」という話。
歩兵分隊に随伴して荷物を運ぶのだから、随伴すべき兵士を間違えたら洒落にならない。間違って、無関係の民間人や敵兵について行ってしまったら、もっと洒落にならない。すると、兵士の側で識別用のデバイスを何か持って歩く必要があるのではないだろうか。常に車両を見ているわけではないのだから、顔認識というわけにもいかないのだ。
それだけが理由というわけでもないだろうし、分隊単位で配備するとなれば数が多くなるから、コストも問題になる。そして車両の数が増えれば、それを整備する手間も問題になる。そうした理由によるのか、目下のところ、この手の装備を大々的に実戦配備するには至っていない。しかし、課題はあっても実験してみることには価値がある。
著者プロフィール
井上孝司
鉄道・航空といった各種交通機関や軍事分野で、技術分野を中心とする著述活動を展開中のテクニカルライター。
マイクロソフト株式会社を経て1999年春に独立。『戦うコンピュータ(V)3』(潮書房光人社)のように情報通信技術を切口にする展開に加えて、さまざまな分野の記事を手掛ける。マイナビニュースに加えて『軍事研究』『丸』『Jwings』『航空ファン』『世界の艦船』『新幹線EX』などにも寄稿している。