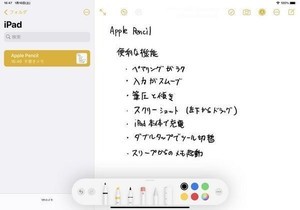新入社員がスマートフォンを使う姿を見て、どう思うだろうか。彼らのスマホ活用が仕事の効率化にどれほど寄与しているかを見極めることが、時代に即したカッコいいのおじさんビジネスマンの姿だ。
スマートフォンはPCではできないことを可能にする強力なツールであり、適材適所で活用することで業務の効率が大きくアップする。まずはiPhoneの標準アプリを使いこなして、新たなスキルアップの一歩を踏み出そう。
若手社員のスマホ利用を見直すべき?
若手社員が仕事中にiPhoneを使って調べ物をしたりメモを取ったり、スケジュール管理をしていたりする姿を見て眉をしかめているのであれば、考えをあらためたほうがよいかもしれない。
現代のビジネス環境において、スマートフォンは単なる娯楽の道具ではなく、効率的に情報を収集し、タスクを管理するための重要なツールだ。新入社員にとって、メモを取ることやスケジュールを整理することは、業務を適切に理解し、成果を出すための基本的な行動だ。スマートフォンを活用することで、迅速かつ的確に情報を取得し、整理することがスピーディーに行えるようになり、否定することは、彼らの成長や仕事の効率を妨げることにつながりかねない。
スマートフォンを使っている姿だけで判断するのではなく、その行動が仕事の効率化や成果にどのように貢献しているのかを見極めることが重要だ。
そして、スマートフォンを使っている若手社員の姿を見て感じた違和感は、あなたがスマートフォンをまるで使いこなせていないという事実を裏付けているという可能性がある。
PC至上主義からの脱却が必要かも
PCが仕事で役立つと強調する中年世代は多いが、それはあくまでPCの前に座っている時に限られる。確かに、PCは大きな画面と優れた操作性を備え、多くの業務を効率的に行うには理想的なツールだ。しかし、PCにアクセスできない状況では、その存在は無力に等しい。
一方、iPhoneは体から離れることがほとんどなく、いつでも持ち歩き、どこでも利用することができる。たとえ電車内や会議の合間であっても、情報収集やメモ、スケジュール管理など、多くのタスクを瞬時にこなせる。
仕事において重要なことは、PCかスマートフォンかという二者択一ではなく、それぞれの特性を最大限に生かすことにある。PCが優れている点もあれば、スマートフォンが圧倒的に有利な点もある。PCとiPhoneの両方を使いこなすことで、より柔軟かつ効率的に仕事に取り組める。
これまでの働き方といった固定観念にとらわれず、どちらも有効な仕事のツールとして見直すことが、これからの時代における働き方のカギになる。
画像加工やOCRもiPhoneのほうが便利? 適材適所のデバイス活用法
PCとiPhoneが同時に使える環境において、PCのアプリケーションが常に便利であるとは限らない。例えば、特定の画像加工に関しては、iPhoneのアプリで処理した方ほうはるかに手軽であることも多い。直感的な操作が可能なiPhoneアプリは、タッチ操作による素早い編集が可能であり、特に複雑でない画像処理には最適だ。
さらに、物理的な資料の取り込みやOCR(光学文字認識)のような処理に関しても、iPhoneのカメラを使えば、PCよりもはるかにスムーズに作業を進めることができる。紙の書類をその場で撮影してデジタル化したり、手書きのメモを瞬時にテキスト化したりする作業は、iPhoneの高性能なカメラとアプリの組み合わせによって、驚くほど簡単に行える。
このように、PCとiPhoneの両方を使える状況においても、どちらを使うべきかは作業内容に応じて適切に判断したほうがよい。それぞれのデバイスには独自の強みがあり、それを理解して適材適所で活用することが、現代の効率的な働き方を実現するうえで重要だ。
仕事でiPhoneが活用できない理由は「機能不足」ではない
ここまでのロジックを吟味して一理あると感じ、iPhoneを仕事に活用していこうとアクションを起こしたとしよう。しかし、その結果として直面するのは、いざ使おうとした瞬間に「できることが少ない」という現実だ。
ここで誤解してはいけないのは、iPhoneが仕事に使えないのではなく、iPhoneをどう使えばいいのかがわからないことが真実という点だ。
iPhoneは、確かに仕事に役立つ多くの機能やアプリを備えているが、それらを効果的に活用するためには、使い方を理解し、適切なシチュエーションでの活用法を知っている必要がある。例えば、メモを取るのか、画像を加工するのか、スケジュールを管理するのか、それぞれに最適なアプリや操作方法が存在する。しかし、その具体的な手法や活用方法がわからないままでは、ただのスマートフォンに過ぎず、せっかくの機能を使いこなすことができない。
つまり、iPhoneを仕事で使うためには、まずそれをどう使うかを学ぶことが重要だ。機能やアプリの知識を持ち、それを状況に応じて使い分けるスキルがあれば、iPhoneは強力な仕事のパートナーとなる。しかし、それを知らずにただ手に持つだけでは、どんなに優れたツールであっても役には立たないのだ。このようにして、「iPhoneは仕事に使えない」のではなく、「iPhoneを仕事に使う方法を知らない」ことが、実際の障害であることに気づくことが重要だ。
子供から学ぶ親たち、中年世代が直面するデジタル格差と若者に学ぶ姿勢の重要性
若者たちは学生時代にアプリの使い方を情報交換しながら学んでいく。どのアプリをどう使うと便利に活用できるのか、どのサードパーティー製アプリが便利なのか、どの機能をどう使えば最大限に手を抜けるのかといった情報は、学生間の積極的な共有によって絶えず更新され、成長していく。
その結果、若者たちはアプリを使いこなすスキルを自然に身に付けていくことができる。このような情報共有のネットワークが、彼らのデジタルスキルを飛躍的に向上させている。
一方で、こうした情報源を持たない中年のサラリーマンたちは、アプリの使い方を独力で学ばなければならず、スタート地点からして大変不利な立場にある。どのアプリが便利か、どう使うべきかという情報は、自ら調べるか、限られた友人から得るしかないため、その結果としてデジタル技術の活用に大きな差が生まれてしまう。
子供が使っているiPhoneの使い方を見て、それを真似して覚える親も少なくない状況を考えると、いかに中年世代が情報源として乏しい環境に置かれているかが理解できる。
このように、中年世代は若者たちが持つような豊富な情報ネットワークにアクセスできないことから、デジタルツールの活用において初めからハンディキャップを負っているといえる。この格差を埋めるためには、自ら進んで情報を取りに行き、学んでいく姿勢が必要になる。若手社員と仲良くなって教えてもらうのも効果的な方法だ。