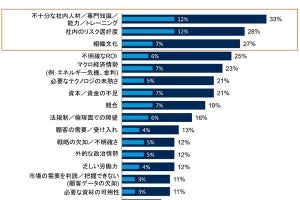今回は組織の能力や個人のスキルをどのように上げていくかについて、そのヒントを提供します。筆者がよく使うのは、成熟度をベースとしたアセスメント&プランです。成熟度の「成熟(Maturity)」は、海外では「あの人はMatureだ(成熟している)」のように使われる場合が多いです。最近、筆者の双子の孫に『新幹線変形ロボ シンカリオン』の玩具をあげるのですが、どんどん進化していくので、あれも一種の成熟かと思います。
組織のスキルを測る「成熟度」
成熟度といえば、有名なのは「CMMI(Capability Maturity Model Integration:能力成熟度モデル統合)」です。CMMIとは、組織のプロジェクトマネジメント能力の成熟度を5段階評価で表したものです。もともとは1980年に発表されたソフトウェア開発を対象にした「CMM(能力成熟度モデル)」でした。IT業界の中にはご存じの方も多いと思います。CMMIは次のように5段階で成熟度が定義されています。
| 成熟度レベル1 | 初期 | 通常、プロセスは場当たり的で無秩序である。このレベルでは、通常、組織はプロセスを支援するための安定した環境を提供しない。 |
| 成熟度レベル2 | 管理された | プロジェクトは以下のことを行うようにする。プロセスは、方針に従って計画され実施され、制御された出力を作成するためにプロジェクトが必要十分な資源を持つ熟練した人員を利用し、直接の利害関係者を関与させ、監視され制御されかつレビューされ、そしてプロセス記述に対する忠実さが評価される。 |
| 成熟度レベル3 | 定義された | プロセスは、特性が十分に明確化され理解され、そして標準、手順、ツール、および手法の中で記述される。成熟度レベル3の基盤となる「組織の標準プロセス群の集合」が確立され、時間の経過とともに改善される。 |
| 成熟度レベル4 | 定量的に管理された | 組織およびプロジェクトは、「品質およびプロセス実績の定量的目標」を確立し、プロジェクトを管理する基準として使用する。定量的目標は、顧客、最終利用者、組織、およびプロセス実装者のニーズに基づく。 |
| 成熟度レベル5 | 最適化している | 組織は、その事業目標および実績のニーズに関する定量的な理解に基づいて、プロセスを継続的に改善する。組織は、プロセスに本来、備わっている変動およびプロセスの実施結果の原因を理解するために、定量的なアプローチを使用する。 |
(出典:Software Engineering Institute『開発のためのCMMI 1.3版』より筆者が一部抜粋)
その後エンジニアリングやソフトウェア調達、人材開発などさまざまな分野向けにこのモデルが派生しています。
マーケティング組織版の「CMMI」を紹介
筆者はこの成熟度のモデルを使い、組織と人のスキルを上げる試みをしています。「測れないものは改善できない」という格言があるように、しっかりとした成熟度という定規を持ち、今の位置を理解して次にどうステップアップをするかを考える必要があります。そうしないと、現状に留まってしまうのです。
最近、別の組織の人に「私の描く戦略を実現するために、もっと組織力をアップしてほしいんだけど」と言ったところ、「大丈夫です。対応できます!」という答えが返ってきました。これを聞いて、明らかに今の能力の位置とどう組織を成長させるべきかが見えていないのだと感じました。これはなんとかすべきと、成熟度を提案中です。
成熟度を分解すると、キャパシティ(対応できるリソース)とケーパビリティ(対応できる能力)になります。ここでは主にケーパビリティについて考えます。組織や役割ごとに、この成熟度を5段階で定義するのです。CMMIの成熟度1(初期)から成熟度レベル5(最適化している)までをうまく使うと定義がしやすいと思います。たとえば、筆者がマーケティング組織のために作ったものが、次の表です。
| 成熟度レベル | マーケティング組織 |
|---|---|
| 成熟度レベル1 | 広報・宣伝を中心にしたマーケティングコミュニケーションのチームがある。そのチームで、都度、展示会や自社イベントの実行や、最低限のWebサイトのメンテナンスを行っている。 |
| 成熟度レベル2 | プロダクトマーケティングの機能があり、製品のメッセージングや市場フィードバックの製品開発へのフィードバックを行っている。マーケティングコミュニケーションチームは、ブランドとPR/AR/ソーシャルに分かれる。主にリード作成がKPIになっている。MAが導入されてキャンペーンを実施する。 |
| 成熟度レベル3 | レベル2に加えて、マーケティング内もしくは事業部や営業組織内に、セールスをサポートするフィールドマーケティング(実態は営業支援)、BDRの機能がある。フィールドマーケティングでは、キャンペーンの企画・実行、コンテンツの作成を行う。マーケティング組織内にオペレーションの担当やチームをもち、MAとCRMを中心にしたプロセスを構築。 ジョブディスクリプションが、ロールごとに定義される。作成するパイプラインのゴールが、営業の売上から逆算されて決められている。KPIが明確化されており、ダッシュボードで管理されている。 |
| 成熟度レベル4 | レベル3に加えて、コテンテンツ作成に責任をもつ、デザインを行う機能をもち、製品またはインダストリーマーケーティングと連携してキャンペーンのコンテンツを開発する。パイプラインからの実際に成約される案件の金額のゴールをもち、それを達成するメトリックも定義する。ブランドキャンペーンを実行する。 |
| 成熟度レベル5 | Marketing Transformationが起き、ブランドやフィールドマーケティングをサポートするCoE(Center of Excellence:各チャネルの実行責任)、キャンペーン、コンテンツやオペレーションなどの機能をもつセントラルマーケティングと、キャンペーンを企画し説明責任を有するフィールドマーケティングから組織が構成される。経営レベルに入り込み、ブランド戦略を経営戦略の一部として取り入れている。 |
筆者はこれを、フィールドマーケティング、BDR(Business Development Representative)、ブランドなどのマーケティングの役割すべてで定義しています。
どのように使うかというと、関連するすべての組織や役割で、現在の成熟度レベルをアセスメントします。関係者でワイワイ評価するのがいいと思います。能力のレベルが散らばることもありますが、その場合はなるべく下を取ります。そして、その1つ上の成熟レベルに行くためには、どのような能力を獲得する必要があるかを話し会います。スキルアップが必要かもしれませんし、新しいプロセスやアプリケーションの導入が必要になるかもしれません。
なぜ、このようなことをするかというと、組織の能力は一飛びに成熟度マックスまでにいくことはなく、段階的に上げていく必要があるからです。これはイメージしやすいですよね。その際に、次に行くべきところを明確にすることで、階段のように上がっていけるのです。もちろん、HR Transformationのように、人事組織がごろっと変わるような変革もあります。ただ、そんなことはめったにあるものではないです。
ここでの大きなチャレンジは、最高位の成熟度レベル5が分からないと、このレベルを定義できないことです。大衆車しか作ったことがないのにスーパーカーを作るようなものです。自社でその知見がない場合は、コンサルティングに頼るのもよいかもしれません。
筆者は、せっかく仕事をするのですから、成熟度レベル5になるように構想を練って、組織を成熟させています。筆者の口癖は「World-Classになる(=成熟度レベル5)」です。部下は迷惑かもしれませんが。
個人のスキルも「成熟度」で可視化しよう
ここまでの話は組織の成熟度についてです。同じように、個人のスキルにおいても成熟度を定義できます。ジョブ型組織が日本でも増えてきましたね。このジョブ型組織では、役割ごとに等級を作ると思います。これが実は成熟度レベルなのです。各等級では、どのようなスキルや知識が必要で、どのような行動をするべきかを定義します。そうすると次の等級に行くためには、どのような成熟をすればいいのかがよくわかります。
海外ではこのような仕組みを「ジョブラダー(仕事の階段)」ともいいます。組織の成熟度と違って、まっすぐ階段を上る場合も、横の階段を上る(職種変更)をする場合もあります。ジョブ型を導入していてもそのような仕組みがない場合は、組織で相談して定義するのがよいと思います。
また、今後3年間の方向性を作るのもいいと思います。1枚のスライドに3年分の箱を作り、それぞれの年のテーマと目指す成熟度、そして、どのような状態にするかを箇条書きにします。
組織と個人のスキルを高めるための「成熟度」、便利なのでぜひマスターしてみてください。