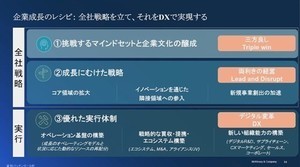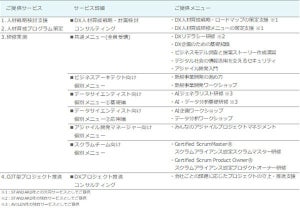ITの内製化は不可欠
ガートナージャパンは2023年1月18日、日本国内のユーザー企業でソフトウェア開発に従事する個人を対象にした「日本におけるソフトウェア開発の内製化に関する調査結果」を発表しました。この発表によると「今後の内製化 / 外製化の方針について、回答者が所属する企業の方針と回答者自身の見解を尋ねたところ、企業の方針が内製化の方向という回答は54.4%、外製化の方向にあるとの回答が35.4%となり、内製化の方が高い割合でした。一方、回答者自身の見解でも内製化を推進している回答者の方が多い結果となりました(内製化推進が56.4%、外製化推進が40.7%)」とのことです。
内製化やクラウド化は今後のITには不可欠だと思いますので、とても良い傾向です。なぜ内製化が必要かというと、ビジネスの現場の近いところでシステムの開発を迅速にすることが、企業の成長に不可欠だからです。日本はITだけでなく、有名な電通モデルが浸透したマーケティングや建築業など、国全体が発注を繰り返す外製化やアウトソースで効率化を追求してきました。
その結果、一時は良かったものの、今日の国の競争力低下につながってしまったのかもしれません。ビジネスを支えるITが遠いところで開発できるなんて、やはりありえないのです。特に、DXを含む企業の競争力を左右するITはです。製造業が設計から生産まで外注するようなものです。
なぜ内製化を進めるべきなのか
上記のガートナー社の調査結果では、内製化の理由について上位2項目は「開発コストの削減(システム・インテグレーション [SI] に支払うコストが高額なため など)」(55.2%)、「開発、実装、保守対応の迅速化(SI企業とのやりとりの時間が長いなど)」(49.7%)でした。それらに続いて、自社ビジネス・ノウハウの活用やスキル、ナレッジの改善・蓄積といった開発のあり方の積極的な改善も4割以上の回答があったとのこと。この3位の回答がもっと高い位置にこないといけないと思います。
さらに、内製化を後押しする別の深刻な理由もあります。それは、日本の市場でエンタープライズアプリケーションの導入をリードするプロジェクト管理者のリソースが、ベンダー側で枯渇していることです。実装する技術者は確保できても、業務にも精通したプロジェクト管理者はそんなに簡単に育成できないのです。エンド企業側でのプロジェクトのリードが不可欠ということです。逆に、クラウドベンダーはエンド企業側のクラウドCoE(CCoE)などの支援が重要になります。
もう1つの理由は、機能が常に増えていくマルチテナント型のクラウドアプリケーションをフル活用しようと思ったら、アジャイルアプローチでアプリケーションを常に進化させていく必要があるからです。ベンダーコントロールのウォータフォール型導入では、SaaSアプリケーションのオンプレ的な導入になってしまいます。カットオーバーしたら時代遅れという事態に陥る可能性があります。
海外を見ますと、特に内製化のトレンドは無いです(笑)。もともと内製化しているからです。日米のエンジニアの比率を見てみるとよくわかります。古い資料ですが、「IT人材白書 2017」(情報処理推進機構)を見ると、日本は72%のエンジニアがITベンダーにいますが、米国では34.6%にとどまっています。
筆者がMicrosoftに勤めているとき、ある時期はソフトウェア開発者に対するエバンジェリズムを担当していました。当時、全世界でソフト開発者へのアンケートを実施したのですが、日本はソフトウェア開発者の仕事への満足度が最低でした。それもそのはず、開発者は発注先の先に存在するからです。
この内製化のトレンドについて、筆者は懸念があります。日本お得意の小手先の内製化が行われているケースが見受けられるからです。小手先の内製化とは、ローコードやノーコードの開発環境を使ってアプリケーションを開発することです。ガートナーの調査の結果における内製化の理由が、コスト削減や開発期間の短縮というのがそれを物語っています。対象の業務によってはこれは悪いことではないですが、それが中心になるのが怖いのです。
内製化によってビジネスを成功につなげる
過去に、コグノスのような第4世代言語の4GLや、Lotus Notesなど、簡単にアプリケーションを開発できるツールがありましたよね。その結果、メンテナンスできない俗人的なアプリケーションが多数開発され、レガシーになっていきました。これは避けたいですよね。
海外の内製化では、アプリケーション開発だけでなく、カスタマイズやパラメータ設定が必要なERP、CRMに代表されるエンタープライズアプリケーションも自社で内製化して導入します。これは、パッケージで導入する分野と自社で開発する分野を明確に分類して、アプリケーションのポートフォリオ管理をしているということです。もちろん、場合によっては外製化します。
企業戦略のもとで全体のITを理解しているので、外注と内製の使い分けができるのです。また、アプリケーション開発はアジャイルもセットになります。数年後を目標にしたウォータフォール型はもはや通用しません。企業を取り巻く環境は劇的に変化していますので、それに合わせてアプリケーションを進化させていくのです。利用部門と協力しながら短い開発サイクルを繰り返していくことが、ビジネス上とても重要です。繰り返しになりますが、そのためには内製化は不可欠です。
日本の企業ではIT部門の人員が不足していると思います。よって、外部の開発エンジニアの協力が不可欠です。その場合に、外部の開発エンジニアを使うにしても、内製の一部に組み込む必要があり、従来の人月という考え方は通用しません。内製化を促進するには、一層のIT部門の変革が必要になりそうですね。しかし、その変革にはビジネスにテクノロジーが融合するという大きな意味があります。IT部門のバックオフィスからフロントオフィスへの変革でもあります。