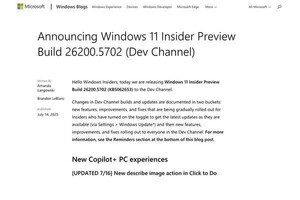知識不足のまま使うRAIDではデータが守れない
「絶対に障害が起きず安心してデータを保存できるストレージ」はこの世に存在するのだろうか? データ復旧のスペシャリストという立場から、ワイ・イー・データの技術者である情報セキュリティ事業部 技術員の佐藤倫史氏と情報セキュリティ事業部 技術グループ 担当課長の本庄豊氏に、一般的に安全と言われているRAIDについて話を聞いてみた。
データを安全に保管し、万が一の事態に備えようとした時、多くの企業が選択するのはRAIDによってシステムを冗長化する方法だ。例えば、RAID 5であれば、複数のHDDにデータを分散して保存することで、HDDの1台が破損してもデータが読み出せるとされているが、実際にはRAIDを利用していてもデータを失ってしまうトラブルも少なくない。その原因の1つは、ユーザーの知識不足だ。
最近は安価な機器が増えたため、RAIDは正しい使い方や運用上のポイントを理解せずに「これさえ使っていれば大丈夫」という感覚で利用するユーザーが増えている。正しい知識がないまま利用すると、RAIDの恩恵が受けられなくなる可能性もある。
「RAID構成を組んだとしても、HDD自体が頑丈になるわけではありません。SASディスクの安全性はかなり高いですが、価格の高さから採用している機器は少ないです。安価なRAID機器はSATAディスクが採用されているので、壊れる確率は一般的なPCと同じです」と佐藤氏は語る。
エラー放置や操作ミスでRAID構成も無意味に
堅固なはずのRAID構成を組んだマシンで出るトラブルの多くは、人為的なミスを原因としているものが多い。最も問題となるのは、作業上のミスではなく、運用上での不注意・不見識によるミスだ。
「"RAIDを構築しているHDDのうち1台が壊れているのに放置されている"といったケースが驚くほどあります。システムが完全に止まった時、初めてそのことに気付くわけですが、これではRAIDの意味がまったくありません」と本庄氏は語る。
大規模システムではRAID 5またはRAID 6が、中小企業や個人レベルではRAID1が利用されていることが多い。この種の深刻なトラブルが起こりがちなのがRAID5やRAID6を利用している場合だ。
「システムの稼働状況を日々確認し、障害が発生しても早期に対応できるような運用管理ができている状態であれば、RAID 5やRAID 6は信頼性を保つことができます」と、佐藤氏はRAIDという選択自体は正しいと語る。しかし、完全に壊れるまで放置されたのでは対応しようがない。
次に多いのが、リビルドのミスだ。HDDを入れ替えする際、オートリビルド機能によってデータが書き換えられてしまうなどのミスが発生するケースが多いという。「ほとんどの機器が標準でオートリビルド機能がオンになっていますが、ちょっとした手順ミスが命取りになります。できればオートリビルド機能はオフにしておいたほうが安全でしょう」と佐藤氏はアドバイスする。
即座に電源を切って専門業者に全HDDを持ち込むのが正解
では、オートリビルドによるリビルドのミスやソフトウェアの設定ミスなどに気づいた時、どのようにして対処したら良いのだろうか?
「やってしまった!」と思った瞬間にとるべき行動は、何と「電源を引っこ抜く」だという。乱暴な話に聞こえるが、これが最も瞬間的にデータ書き換えを止められる方法なのだ。「正規の手順で電源を落とすと、その分時間がかかってデータの書き換えが進行してしまいます。とにかく、すぐに進行を止めることが大切です」と本庄氏。RAIDを構成するHDDの一部が破損した場合、リビルドに失敗した場合なども即座に電源を落とすべきだという。
作業を止めた後、専門業者へデータの復旧を依頼するわけだが、この時も迅速な復旧につながるコツがある。破損の有無にかかわらず、RAIDを構成するすべてのHDDを業者に持ち込むのだ。「正常なHDDだけが持ち込まれても、データをすべて拾い出せるとは限りません。壊れたHDDも復旧作業の手がかりとなります。すべてのHDDを一式持ち込んで、"どのような構成にしていたのか"、"どのような事故が起こったのか"を伝えるのが最善でしょう」と佐藤氏は語る。
RAID機器の対応は設備投資がかかるため、手がけないデータ復旧事業者も多いようだが、同社ではソフトウェアによる仮想化RAIDなども含めRAID機器の復旧作業はすべて対応できるという。これはオントラックの技術とワールドワイドで蓄積されているノウハウがあってこそのことだ。
パーソナルNASは一時データ置き場と割り切れ
また、最近は家庭やオフィスで安価なストレージとして便利に使われているパーソナルNASについては、佐藤氏から「あまり過信しないほうが良いですね。短命の機器と割り切って使ってください」と、心構えの問題が指摘された。
ハードウェアを分解してみればわかるが、小型な筐体を採用しているパーソナルNASにはごく普通のHDDと非常に小さなファンが使われている。それが常に回転し続けているのだから、それほど長い寿命ではないということは想像がつくだろう。
「使い続ければ物理的な寿命はどうしても短くなりますが、かといって使い終わるたびに電源を落とすというのもナンセンスです。そういう仕様には作られていないため、電源は常時オンにしておいてよいと思います。ただし、パーソナルNASは大事なデータを恒久的に保存する場所ではなく、複数人で共有したいデータの一時保存場所として使うべきでしょう」と佐藤氏。
トラブルとして多いのは、使い続けたことによる物理障害のほか、操作ミスでフォーマットしてしまったなどの論理障害だという。「別構成でフォーマットした場合なども、それ以上触らずに連絡いただければデータを復旧できる可能性は高いと思います」と本庄氏は語る。逐次バックアップを取りながら利用したうえで、万が一の場合は即座に専門業者へ依頼するといった具合に、パーソナルNASも普通のPCと同じ扱いをする必要があるようだ。
状況を正直に伝えることがデータ復旧のカギ
今回、2人の技術者から異口同音に出てきた言葉は「状況を正直に話してほしい」というものだった。人為的なミスの場合はもちろん、他のデータ復旧事業者へ依頼した後にHDDを持ち込んだことなども包み隠さず伝えなければならない。そのほうがデータ復旧の確率が高くなるというより、むしろ、そこで嘘をつかれたり隠し事をされたりすると手の施しようがなくなる場合も少なくないのだ。
「今は製品数が多すぎるので、メーカー名だけなどでは製品の特定も難しいですね。きちんと型番とトラブルの原因を教えていただくのが、データ復旧への近道だと思います」と2人は語った。