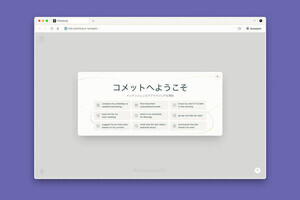2025年5月29日、検索特化型生成AIのパイオニアであるPerplexity AIが、新機能「Perplexity Labs」を発表しました。単に問いに答えるだけでなく、ユーザーのアイデアを具体的な成果物へと昇華させる、新しいコンセプトのプラットフォームです。まるでユーザー専属のAIチームを雇うかのように、リサーチから分析、さらにはアプリ開発までを自動で実行してくれるのが特徴です。今回は、Perplexity Labsについて紹介します。→過去の「柳谷智宣のAIトレンドインサイト」の回はこちらを参照。
やりたいことを伝えればあとはAIチームが総出で対応してくれる
これまでのPerplexityには、瞬時に答えを提示する「Search(検索)」と、数分かけて情報を網羅的に収集・要約する「Research(リサーチ)」という2つのモードがありました。
「Labs」は、そのさらに先を行く「工房」としての役割を担います。例えば、ユーザーが特定の市場に関する詳細な調査レポートを作成して、といったプロンプトを入力すると、Labsは自律的に動き出します。短ければ数分、時には1時間以上という時間をかけて、複雑なタスクを次々と実行していくのです。
まずはウェブを広範囲に調査しはじめ、必要な情報を徹底的に収集し、その膨大なデータの中から核心となる部分を抽出します。次に、収集したデータを構造化し、分析や可視化のためのコードを自動で生成・実行します。そして、詳細なレポートやダッシュボード、プレゼンテーション資料といったファイル群を成果物として提供してくれるのです。
従来であれば、リサーチャーやデータアナリスト、プログラマーといった複数の専門家がチームを組み、数日間を費やしていたであろう一連の工程を、Labsなら短時間で完結させてしまいます。アイデアの着想から成果物の完成までをシームレスに繋ぎ、生産性を飛躍的に向上させてくれるのはありがたいところです。
なお、Labsは有料プランのPerplexity Proユーザー向け機能で、無料プランユーザーは利用できません。
Labsには「Deep Web Browse(深層ウェブブラウジング)」や「Code Execution(コード実行)」、「Chart/Image Creation(チャート・画像生成)」といった機能が用意されています。
Deep Web Browse機能は、通常の検索エンジンではアクセスが難しい深いレイヤーのソースまで網羅的に探索し、質の高いデータを収集してくれます。続いて、Code Execution機能が集めたデータの整形や統計処理、数値計算を行います。
そして、分析結果はMatplotlibのような描画ライブラリを用いて、視覚的に理解しやすいグラフやチャートへと変換されます。生成されたPNG画像やPDFドキュメントなどの成果物は、すべてプロジェクト内の「Assets(アセット)」タブに自動で整理・保存され、ユーザーはいつでもダウンロードして利用できます。
加えて、Labsには「Apps(アプリ)」というタブが用意されており、生成されたコードをホストし、インタラクティブなWebアプリとしてブラウザ内で動作させることができます。パラメータを動かしてシミュレーションを行ったり、スライドショーを再生するなど、分析結果を動的な形で体験できるのです。情報収集から分析、可視化、そしてインタラクティブな共有まで、一連のワークフローを単一のプラットフォームで完結できるのがLabsの大きな特徴です。
他の人が作ったプロジェクトを見てみよう
まずは、何ができるのかを体感してみましょう。Labsの公式サイトにある「Projects Gallery(プロジェクトギャラリー)」には、ビジネスシーンでよくある多種多様なタスクに対応した、実用的なテンプレートが大量に登録されています。
例えば、新規事業のためのマーケティング企画立案、競合他社の製品比較レポート作成、企業の財務諸表分析、さらには機械学習モデルの性能評価といった、専門性が求められる作業もテンプレートを使えば手軽に着手できます。
まずは、気になるプロジェクトをクリックして、動作を確認してみましょう。今回は最初に表示されていた「1941年12月から1945年9月までの太平洋戦域における戦闘を示すインタラクティブマップ」を選択しました。「ラボ」タブではプロンプトやその応答が確認でき、成果物は「アセット」タブ、処理の過程は「タスク」タブ、情報源は「ソース」タブにまとめられています。
「アプリ」タブでは生成したコードを実行できます。今回は、第二次世界大戦の様子を時系列に再生するアプリで、「Play」を押すと領土や戦闘の状況が刻一刻と変化していきます。これが、たった数行のプロンプトで作れるとは驚きです。
ラノベ自動生成アプリを作ってもらう
では、実際にアプリを作ってみましょう。今回は、その時の気分に合わせたラノベをサクッと生成してくれる執筆アプリを作ってもらいました。
ジャンルやパターンを選択したら、その内容に合わせて創作してもらうのです。任意で登場人物やキーワードの設定ができるようにしました。また、世界観を統一させるために、設定ファイルを読み込む機能も欲しいところです。このような要望を五月雨にChatGPTに伝え、プロンプトに仕立ててもらいました。
-
プロンプト
ライトノベル生成アプリを作成してください。以下の要件を満たすようにしてください:
【UI仕様】
1画面完結型のUIとする(タブ分け不可)。
以下の入力項目を設け、すべてこの画面内で設定可能とする: - プルダウンメニュー
ジャンル(例:異世界、学園、SF、恋愛、ホラー など)
ストーリーパターン(例:成長、復讐、冒険、恋愛、日常)
文体(例:一人称、三人称、ライト調、硬派調 など)
- テキスト入力項目
キャラクター設定(任意):自由にキャラ設定を記入できるテキストエリア。
キーワード入力(任意):カンマ区切りで複数登録可能な入力欄。
設定資料アップロード:.txt形式のファイルをアップロードできるようにし、後の生成時に参照すること。
【機能要件】
上記の入力情報をもとに、物語のタイトルと第1章(約3000文字)を生成する。
ストーリー生成にはOpenAI GPT-4.1 APIを使用すること。
【出力仕様】
出力結果として以下を画面上に表示:
生成された物語タイトル
第1章の本文(3000文字程度)
以下の入力項目を設け、すべてこの画面内で設定可能とする:
- プルダウンメニュー
ジャンル(例:異世界、学園、SF、恋愛、ホラー など)
ストーリーパターン(例:成長、復讐、冒険、恋愛、日常)
文体(例:一人称、三人称、ライト調、硬派調 など)
- テキスト入力項目
キャラクター設定(任意):自由にキャラ設定を記入できるテキストエリア。
キーワード入力(任意):カンマ区切りで複数登録可能な入力欄。
設定資料アップロード:.txt形式のファイルをアップロードできるようにし、後の生成時に参照すること。
【機能要件】
上記の入力情報をもとに、物語のタイトルと第1章(約3000文字)を生成する。 ストーリー生成にはOpenAI GPT-4.1 APIを使用すること。
【出力仕様】
出力結果として以下を画面上に表示:
生成された物語タイトル
第1章の本文(3000文字程度)
このプロンプトをLabsに入力すると、すぐに処理がスタート。いろいろなサイトを検索して情報収集が始まりました。数分後、アプリが完成すると「アプリ」タブが現れるので、クリック。見事に、ラノベ執筆アプリが完成していました。
プルダウンメニューで内容を選択でき、ファイルのアップロード機能もあります。任意の追加設定も行えるようになっています。デザインもいい感じですし、ちょっと感動したものの、なぜかAPIの登録場所がありません。
案の定、「物語を生成」をクリックすると、内部の軽量AIを使って瞬時にテキストが生成されました。最初だけは小説の体をなしていますが、後半はあらすじにもならないような無茶苦茶な文章になっています。
そんな時は、Labsに改修してもらいたいところを自然文で指摘すればいいだけです。すぐに対応してくれます。
数分後、生成が完了したので「アプリ」タブを開くと、今度はAPIの登録フォームが用意されていました。指示していませんが、APIキーを入力すると、セキュリティのためにアスタリスクに変換されるようになっています。
設定ファイルもドラッグ&ドロップで登録できるようになり、すべて入力して生成させてみると、きちんと1000文字以上の小説が出力されました。
当初、指示した出力テキストをファイルでダウンロードするボタンはあるのですが動作しなかったりと、改良したい部分はまだありますが、それでもここまで簡単に作れてしまうのは驚きです。文字数や文章のクオリティはGPTに渡すプロンプトで改善するはずなので、簡単に修正できるでしょう。
生成したコードはダウンロードできます。実際に、このアプリをダウンロードし、圧縮ファイルを解凍したところ3つのファイルが入っていました。その中の「index.html」をダブルクリックすると、ローカルで同じアプリが動きました。
ビジネスクオリティまではあと一歩だが今すぐ触ってみるべき
Perplexityは検索のためのAIというイメージでしたが、Labsの登場によって、インタラクティブなコンテンツやウェブアプリも生成できるAIに昇格しました。
グラフや図表を使った市場調査や競合分析、業界動向レポートを作成したり、経理データをアップロードして分析結果をダッシュボードで可視化するなど、手間のかかる作業をAIに任せられるのは業務効率アップに大きく寄与してくれることでしょう。プレゼン資料も、資金繰り表も、トレンド分析も行えます。
シンプルな指示からでもウェブアプリを開発してくれるのも凄いところです。何となくそれっぽいコードを出すのではなく、実際に動くものを作ってくれるのです。これからは、何か欲しいツールや機能があれば、生成AIで作ってしまう、という時代になるのかもしれません。
ただし、課題もあります。今回、色々と試したのですが、成果物のクオリティが今一歩なのです。テーマにもよりますが、無理に図表を作ろうとして、意味のない内容になっていることも多くありました。また、Perplexityのサーチ機能にはほとんど見られなかったハルシネーションも出るようになっています。
今すぐにビジネスで使い倒せるとは言えませんが、これもあっという間にブラッシュアップされていくでしょう。PerplexityのProプランを使っているなら、ぜひ触ってみることをお勧めします。単なるチャットでのやりとりを超えた、AIの可能性を感じることができるでしょう。