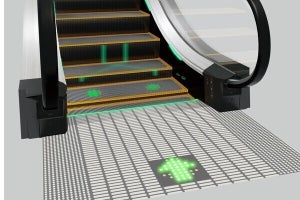生成AIや自動運転、量子コンピュータ、AR・VR技術――近年のテクノロジーの進化は目覚ましく、30年前には考えられなかったような体験をたくさんできるようになってきた。
一方で、「当たり前の存在」となって、私たちに生活に溶け込んでいるテクノロジーも数えきれないほどあるだろう。そこで、本連載では、その当たり前になっている存在にスポットライトを当て、読者が抱いているかもしれない「そういえば、この技術ってどういう仕組みなの?」という素朴な疑問に答えていく。
第2回目は、多くのビジネスパーソンが「乗らない日のほうが少ない」であろう「エレベーター」について詳しく紹介していく。
ボタンを押すだけで行きたい階に連れて行ってくれるエレベーターは、子どもからお年寄りまで、誰もが免許なしで操作・運転できる大きな乗り物の一つだ。「縦の交通機関」とも呼ばれるこの革新的技術は、一体どのような仕組みで動いているのだろうか。
前回と同様、自分の目で確かめたいと思ったので、エレベーターの設計開発・製造・販売などを手掛ける日立ビルシステムの開発研究施設「亀有総合センター」に足を運んでみた。同社が2019年に中国の超高層ビルに納入した分速1260m(秒速21m)で走行するエレベーターは、世界最高速エレベーターとしてギネス記録に認定されている。
取材中、100年以上の歴史を持つ同社の革新的なエレベーター技術に終始圧倒されていた筆者。普段は見ることができない“エレベーターの内部”をお届けしよう。
紀元前3世紀に誕生したエレベーター
本題に入る前に、エレベーターの歴史を振り返りたい。
「滑車とロープを使って荷物(人)の上げ下ろしをする道具」をエレベーターと定義するなら、その発祥は紀元前236年、古代ローマ時代にまでさかのぼる。
考案者は、浮力の発見や正確な円周率を求めたことで有名なアルキメデス。当時の動力はもちろん人力で、手動でロープを引っ張っていたという。また、主な用途は荷物用だった。上げ下ろし中に、滑車が壊れたり、ロープが切れたりしてしまえば荷台は急落下してしまうので、人間を乗せるには危険すぎたのだ。
蒸気機関の登場がエレベーターの効率を格段に向上させた。電力記号「W(ワット)」にその名を残すジェームス・ワットが1769年に発明した蒸気機関は、1835年、ついにエレベーターの動力としても使われるようになった。人力以外の動力が導入されるまでに、2000年以上もの時が流れたということになる。
しかし、エレベーターにおける蒸気機関の登場によって、人力による作業は激減したが、エレベーターの危険性がなくなったわけではなかった。新たな動力を手にしたエレベーターも構造上は危険と隣りあわせだった。
エレベーターを安全な装置へと進化させたのは、アメリカの発明家エリシャ・グレーブス・オーチスだ。オーチスは1852年にロープが切れても落下しない「非常止装置」を発明。2年後の1854年、ニューヨークのクリスタルパレス博覧会で、会場に設置されたエレベーターにオーチス自らが乗り込み、集まった多くの人の前でロープを切らせることで、その安全性を実証した。
こうして、ようやく人を乗せることのできるエレベーターが誕生したのだ。ちなみに、オーチスはエレベーターの製造・設置・サービスで世界有数の企業米Otis Worldwideの設立者。エレベーターは、オーチスが名づけた商品名で、これが一般化した名称とされている。
日本最古のエレベーターとは?
そして、近代エレベーターの原点となる技術が誕生したのは1903年のこと。エレベーターのカゴと「釣合おもり」の重量のバランスをとり、効率の良い昇降を実現する「カウンターウエイト方式」が登場した。
この技術により、高層ビルへの設置が可能になった。また、安全性能も飛躍的に向上し、最上階または最下階を通り過ぎてしまう事故が激減した。
日本における最古のエレベーターは、1842年に水戸偕楽園の休憩所「好文亭」に設置された、食事などを運ぶ小さな運搬機とされている。すでに欧州では蒸気機関の利用が始まっていたが、日本初のエレベーターは手動だった。
日本初の電動式のエレベーターは1890年11月10日に完成した12階建ての展望台「凌雲閣」に設置された。しかし、1923年の関東大震災で大きな被害を受け解体。11月10日が「エレベーターの日」に制定された由来は、この凌雲閣にある。
日本国内においてエレベーターが急速に広がったのは、1960年代の高度成長期。建築基準法やJISの制定により、製品の規格化に伴う均質化と安全性能の大幅な向上が実現した時代だ。
このころから、乗用エレベーター、物流倉庫などの荷物用エレベーター、病院向け寝台用エレベーターなど、設置台数は急速に拡大。またマンションの建設も加速するなど、すべての建物へのエレベーターの標準化が進んだとされている。
日本エレベーター協会によると、2023年3月末時点で、日本には約70万台のエレベーターが稼働しているという。
意外とシンプル? エレベーターの仕組み
エレベーターは、駆動方式や用途、速度、人や荷物が乗る「カゴ」の構造など、さまざまな分け方があり、かなり多くの種類が存在する。
駆動方式は大きく分けて「ロープ式」と「油圧式」の2つがある。
ロープ式のエレベーターの構造はいたってシンプルだ。カゴと釣合おもりの重量のバランスをとり、最上階のさらに上にある「機械室」と呼ばれる部屋に設置された「巻上機」によって効率よく駆動する。ロープと綱車間の摩擦力で駆動し、巻上機の綱車に掛けたロープの一端にカゴを、もう片方に釣合おもりを付け、綱車の回転力を主ロープに伝えて、カゴを昇降させる仕組みだ。
機械室ありタイプのエレベーターは、昇降行程500m以上などの高層建築物にも適用できるのが特徴。その反面、カゴの直上部に巻上機を設置する必要があるため、日照権の問題で機械室の配置に制約が発生することがあるという。
エレベーターは従来、ロープ式で機械室があるものが一般的だったが、1980年代に入り、高さ制限や日照権の規制がある中低層のマンションで、機械室の設置場所が比較的自由な油圧式のエレベーターが増加した。
油圧式エレベーターは、電動ポンプで油圧を制御しその圧力でカゴを昇降させる。しかし、油を使うため、独特な臭いやふわふわとした乗り心地、手間のかかるメンテナンスといった特有の問題があった。現在はほとんど生産されていない形式だという。
そこで注目を集めたのが、日照権の問題と油圧式エレベーター特有の問題を同時に解決する、機械室がないタイプのロープ式エレベーターだ。巻上機を昇降路の内部に設置したタイプのエレベーターで、機械室が不要になった。巻上機を上部に設けるタイプと下部に設けるタイプがある。
建物の屋上部に機械室を設置する必要がないため、建築費用の抑制や、制限高さ目いっぱいに居室を設けられるといった大きなメリットがある。一方で、機械室ありと比較して、一般的に昇降路内のローピングが複雑になり、巻上機の出力に制限がある。そのため、昇降行程が長いエレベーターには適用できない。
日立ビルシステム 経営企画部 広報グループの小泉佳一郎さんは「目安として、20階建てくらいまでの一般的なビルやマンションには、機械室なしのタイプが採用されます。それ以上の高層ビルやタワーマンション、人の利用が多いオフィスや商業ビルなどには機械室ありのタイプが導入されることが多いですね」と、解説してくれた。