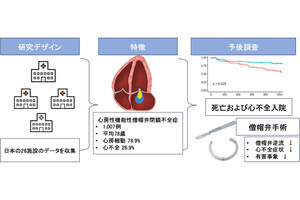AMIと熊本大学の両者は、心音と心電図を同時に測定できるAMI製のポータブルデバイス「心音図検査装置AMI-SSS01」シリーズと深層学習(AI)を組み合わせ、わずか8秒間で心臓の状態を推定できる新技術を開発したと、7月24日に共同発表した。
同成果は、AMIと熊本大大学院 生命科学研究部 循環器内科学の石井正将講師、同・辻田賢一教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、日本循環器学会の機関学術誌「Circulation Journal」に掲載された。
世界でトップクラスの高齢化が進む日本では、心不全が増加傾向にある。厚生労働省が発表した2014年の「人口動態統計月報年計(概数)の概況」によると、死亡総数127万3,020人のうち、高血圧を除く心疾患による死亡は19万6,760人(全体の15.5%)で、このうち心不全は7万1,612人(心疾患中最多の約36.4%)だった。しかし、同省の2024年の同資料によれば、死亡総数160万5,298人中、高血圧を除く心疾患は22万6,277人(全体の14.1%)を占め、心不全はその中で9万8,790人(心疾患中最多の約43.7%)であり、人数が増加している。
心不全とは、心臓が体に必要な血液を送れなくなる状態を指す。特に高齢者に多く、再入院や死亡率の高さが問題となっている。早期発見と適切な治療が重要となるが、これまでの診断方法には課題があった。中でも、心不全診断に用いられる主要なバイオマーカー「BNP」や「NT-proBNP」などを測定する血液検査は時間がかかることに加え、患者にとって負担が大きいものだった。
そこで研究チームは今回、BNPの血中濃度を予測する新モデル「eBNPモデル」の性能評価のため、複数の病院で前向き観察研究を実施し、同モデルの性能を新たなデータを使って検証することにした。
今回の研究では、心臓の超音波検査を受けた患者が対象とされた。心音データやECGのデータが不完全である場合や、透析を受けている患者は除外され、最終的に1,035人の患者から得られたデータを訓練セットと検証セットに分け、深層学習モデルの訓練に供された。
その後、eBNPモデルがBNPレベルを正確に予測できるか、実際の患者データで検証が行われた。高BNPレベルの患者を正しく識別可能かどうかを評価するため、「感度」(高BNPレベルの患者を正しく見つけられる割合)と、「特異度」(高BNPレベルでない患者を正しく除外できる割合)が測定された。外部検証には、別の病院の患者818人から選ばれた140人のデータが使用された。
eBNPモデルは、外部検証データセットでも優れた性能が発揮された。特に、BNPレベルが100pg/mL以上の患者の識別において、高い精度が確認された。具体的には、「受信者動作特性曲線」スコアは0.895、感度は84.3%、特異度は82.9%が達成された。これらは、eBNPモデルが、BNPの高低で患者をグループ分けできる能力が非常に高いことを示すとした。
なお、患者の体格指数(BMI)によって、eBNPモデルの性能にわずかな差が見られたという。たとえば、高BMIの肥満患者では感度がやや低く、BNPレベル予測能力の若干の低下が確認されたとする。しかし、正常BMIの患者でeBNPモデルは極めて良好な結果を示したとした。
今回の研究では、周囲の会話や呼吸音といった背景雑音がモデルの予測に与える影響も調べられた。その結果、通常の臨床環境における会話程度の雑音であれば、eBNPモデルの性能はほぼ影響を受けないことが確かめられた。しかし、音が非常に大きくなると、精度がわずかに低下する点も確認されている。
これらの結果から、eBNPモデルがBNPレベルを正確に予測し、心不全診断に有用であることが示されたとのこと。実際の臨床環境でも高精度を維持できることが確認されたことから、eBNPモデルを導入すれば、心不全のリスク評価が迅速かつ正確に行えるようになり、患者の診療に貢献する可能性があるという。
eBNPモデルは、心不全の早期発見と患者の状態のモニタリングを可能にするという。特に、心不全の症状が軽いうちに発見できれば、早期に適切な治療につなげられる可能性があるとのこと。なお、BNPの値は体格や腎臓の働き、心房細動などにも影響されるため、研究チームはそれらの要素を考慮したさらなる精度向上をめざし、研究を継続する方針だ。