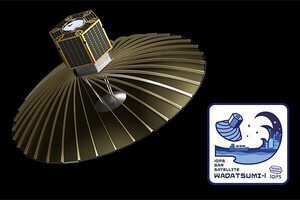QPS研究所は、業務提携している日本工営と共に、九州・霧島新燃岳の噴火状況を小型SAR衛星「QPS-SAR」の観測画像を活用して調査。火山噴出物範囲の判読に取り組み、火山活動に関する有効な情報が得られたと7月23日に発表した。
霧島新燃岳では2018年6月以来、7年ぶりとなる噴火が2025年6月22日に発生し、その後も断続的に噴火活動が続いている。
QPS研究所では、噴煙高度が初めて5,000mに達した7月3日13時49分頃の噴火を対象とし、同日23時30分にQPS-SARによる緊急観測を実施。その後、日本工営の協力のもとでSAR画像の判読を進め、国土地理院が発表した同時期のSAR衛星「ALOS」シリーズによる干渉解析結果や、7月5日に産業技術総合研究所(産総研)が行ったドローン観測の結果と照合した。その結果、それぞれで確認された、火口から北東部に広がるL字状の火山噴出物エリア(前出画像の青で囲んだ部分)を、QPS-SARによる観測画像にて視認できたという。
-

(左)QPS-SAR10号機による6月27日19時00分の試験観測画像(※初期運用中に通常モード・分解能1.8m×46cmにて試験観測を行ったもの) (右)QPS-SAR9号機による7月3日噴火後の緊急観測画像(同日23時30分)
-

(左)国土地理院によるSAR干渉解析(2025年6月28日~7月4日)。青く描写されている場所は干渉性が低いことを示しており、国土地理院のウェブサイトでは「火山噴出物によるものと見られる非干渉領域」と推定されている (右)産総研によるドローン観測画像(2025年7月5日 11時08分頃)。灰白色の堆積物について「7月3日の13時38分と14時05分の観察の間のどこかで広がったものであり、3日13時49分頃から始まった噴煙高度5,000mの噴火の開始に伴うものと考えられる」と推定されている
QPS研究所は「一度の観測で得た単一画像のみ、かつ、目視でその情報を得られるほど高精細・高画質な観測画像は、状況把握のスピード向上に直結し、有事のときにひとつの有効なデータとして貢献できる」とコメント。
SAR衛星は昼夜を問わず、悪天候や噴煙の中でも電波を使って地表の状況を広域に観測可能で、地上からの観測が難しい山頂や噴火中、噴火直後の火口周辺の様子も把握できる。同社では、「衛星データを活用することで、人的リスクを回避しながら、火山活動調査における目に見えないリスクを可視化し、早期対応と正確な意思決定を支える重要なツールとなる」とも指摘している。
QPS研究所は現在も新燃岳の噴火状況を観測し続けており、火山活動の推移を長期的に追跡する計画だ。今後も日本工営とともに調査を行い、火山活動観測の課題に対し、具体的な実証を進めていく。
さらに、⽇本⼯営が⼿がける社会基盤構築のさまざまな分野での事業ノウハウやアイデアを掛け合わせ、人々の安⼼・安全な暮らしを支える新たな衛星データサービスの開発と、国内外での市場展開をめざすとのこと。