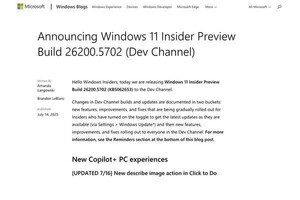京都・仁和寺での食事会
「日本の特色のある食材を使い、世界でも最先端とも言えるシェフたちの豊かな創造力と伝統を継承しながら、新しいものを取り入れて進化する日本料理の技が織りなす新しい美味しさを味わってもらいたい」─。このように語るのはキッコーマン社長CEOの中野祥三郎氏だ。
6月16日、同社は全日本・食学会、農林水産省などと国内外のトップシェフが「食の未来」を具現化した料理を振る舞う食事会を開催した。舞台は随筆集『徒然草』にも登場する仁和寺(京都市右京区)。披露したのは万博のテーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」を念頭に置いたサステナブルな食材などを取り入れた計19メニュー。
米国とフランス、タイの海外シェフ3人と京都の8つの料亭が日本の食材を使った料理を考案。「(海外の)ビッグシェフ3人が京都に一堂に会した」(京都の老舗料亭・菊乃井の村田吉弘氏=全日本・食学会名誉理事長)。京野菜や代替たんぱく質としての海藻、震災復興を目的とする能登牛を使った料理が並んだ。
2025年3月期の売上収益のうちの8割弱、事業利益のうちの約9割が海外─。今のキッコーマンの姿だ。同じく調味料を扱い、広く海外展開していることで知られる味の素よりも比率は高い(売上高の約65%、事業利益の約62%が海外)。
なぜキッコーマンが海外で、しょうゆを広げられたのか。会長の堀切功章氏は「食文化の国際交流はキッコーマンの経営そのもの」と表現する。通常の「海外展開」では、自社の製品を海外の販路に乗せて現地の消費者の手に取ってもらえるようにするケースが多い。外食では店舗出店で目に触れるようにする。
だがキッコーマンの海外戦略は一線を画す。同社は2つのステップを踏んでいる。第1段階は、しょうゆを使いたくなるレシピを現地の食材や嗜好に合わせて開発し、提案して周知を図る。第2段階では、しょうゆ工場を現地につくり、生産体制を整備し、さらに根付かせていく。第1段階での「いかに現地の人々に喜ばれるしょうゆを使ったレシピを開発できるか」(中野氏)が勝負だ。
象徴的な例が米国。今では同国の約5割の家庭で、しょうゆが常備されている。遡ると、キッコーマンのしょうゆは1868年にハワイに輸出されていた。ただ当時は日系人や米国駐在の日本人向け。戦後になって日本が復興していくものの、将来は日本の人口も減り、調味料の消費が大幅に増加するわけではないと同社は危機感を抱いた。そこで米国の現地の人々に焦点を当てた。
ヒントは戦後に来日した海外の官僚やジャーナリストなどの反応。彼らの評価が高かったからだ。それを踏まえて同社は1957年に米国・サンフランシスコに販売会社を設立。しかし、単にしょうゆを日本から持っていくだけではなかった。約70年前の米国は肉文化。味付けも塩こしょうが主流だった。
そこでキッコーマンは市場開拓に向けてスーパーでのデモンストレーションを開催。販売員が肉にしょうゆを漬け込んで来店客の前で焼いて見せた。香ばしい香りにつられた来店客が味見をすると、こぞってしょうゆを購入。58年に米国に留学し、デモ販売を手伝った当時の茂木友三郎氏(現名誉会長)も「肉にしょうゆが合うことを認識してくれた」と振り返る。それが徐々に「肉のテリヤキ」となって米国の食卓に定着する。
しかも、肉のテリヤキは「魚の照り焼き」が当たり前だった日本に逆輸入されているほど。他にもキッコーマンのフランスの駐在員が開発した甘いしょうゆ・スクレソースも海を渡り、米国でも普及している。
インドやアフリカを視野に
「現地の米国人が普段食べている料理のバラエティの1つとして、しょうゆを使った料理を提案していった。野菜の炒め物にも塩こしょうしかなかったところに、しょうゆを提案した」と中野氏は振り返る。73年には米国工場をつくり、現地生産したしょうゆの同国内出荷も始めた。
それから半世紀以上にわたり、海外のしょうゆ事業は順調に伸び続けている。今も「しょうゆをジワジワと定着させる」(同)という戦略に変わりはない。定着するまで何十年とかかる中でも、定着した国で稼いだ利益を次の国に投資している。
「当社は今後も米国の需要は伸びると見ており、3カ所目の米国工場を建設中だ。南米やインド、アフリカなどでもジワジワ広げていく」と中野氏は今後の意気込みを語る。
キッコーマンには70年の万国博覧会への出店を皮切りに、2010年の上海国際博覧会での出店、15年のミラノ国際博覧会での日本館ヘの協賛、18年には東京五輪開催に合わせて和洋中、異なるジャンルのシェフ・料理人が開発した〝融合〟をテーマにしたコース料理を実演やトークと一緒に楽しめるレストラン「キッコーマン ライブキッチン東京」の展開など、食文化の国際交流を続けてきた歴史がある。
「社名の〝亀甲萬〟の字の如く、歩く速さは遅くてもゴールはしっかり目指す」─。上席参与(当時、現顧問)の臼井一起氏は話す。
世界が分断・分裂の様相を強める中、食で世界をつなぎ、事業もつなぐことができるか。キッコーマンの〝食文化の国際交流〟はこれからも続く。