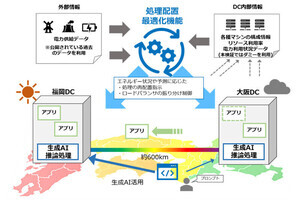NTTコミュニケーションズ(以下、NTT Com)は6月16日、中堅・中小企業の生成AI活用を支援する「Stella AI for Biz」の提供を開始することを発表した。同サービスはドコモグループの新規事業創出プログラム「docomo STARTUP」からスピンアウトしたSUPERNOVAが開発を進めた。
なお、同サービスはドコモビジネスパッケージのラインナップの一つとして提供し、企業の業務効率化と価値創出を支援するという。月額料金は1ID当たり1980円(「使いこなしサポート」を含む)。
サービス提供開始の背景
人手不足への対応や売上の向上、新たな価値創造など、生成AIの法人利用は拡大している。しかし、業務で生成AIを活用しようとする現場では、「どの生成AIを契約すべきかわからない」「利用の定着や導入後に十分に活用できるか不安」「環境構築が大変」といった課題が残される。
NTT Comの調査によると、中小企業の4社に1社が生成AIを「利用中」または「トライアル中」であり、前向きなアクションを進めている。また、「現在は生成AIを利用していない」とする55%の企業のうち20%は今後の活用を検討しているという。
中小企業において生成AIの導入効果を感じている企業は約70%に上り、特に時間削減効果とコスト削減効果を実感している企業が多いとのことだ。このように、中堅・中小企業では生成AIの活用効果が高いと期待される。
そこでNTT Comは、中堅・中小企業における生成AI導入と活用における課題を解決し、DX(デジタルトランスフォーメーション)を支援するため、「Stella AI for Biz」の提供を開始する。
複数のAIモデルとエージェント機能
同サービスは複数のAIモデルを搭載し、利用しやすいインタフェースを実装したことで簡単に使える生成AIサービスを目指したという。クラウドサービスとして利用可能で、同サービスに入力した業務情報や出力結果はAIモデルの学習には利用されないため、環境構築などは不要で申し込み後すぐに利用を開始でいる。
同サービスは「Gemini」「GPT」「Claude」「Grok」「tsuzumi」など、AIモデルを複数搭載。文章生成や画像生成などそれぞれのモデルの強みを生かして、最適なモデルを業務に応じて使い分けられる。
本稿執筆時点では「Gemini 2.5 Flash」「GPT-4.1 mini」「Claude Sonnet 4」が使い放題。なお、「Claude Sonnet 4」の使い放題は終了時期未定。汎用モデルには「GPT-4.1」「GPT-4o」「tsuzumi」、高性能モデルに「Gemini 2.5 Pro」「o3」「Grok 3」、画像生成モデルに「GPT -Image-1」「Imagen 4」「DALL・E 3」「Grok 2」をそれぞれ搭載。
使い放題以外のモデルは、ユーザー当たり毎月150クレジットが付与され、AIモデルの利用によってクレジットを消費する。WebやRAG(Retrieval-Augmented Generation:検索拡張生成)による情報検索、DeepResearchといったエージェント機能にも対応し、幅広い業務で利用可能。
直感的で日常業務に使いやすいインタフェース
Webブラウザ版に加えてモバイルアプリも提供しているため、オフィスワークだけでなく外出先でも「Stella AI for Biz」を利用可能。ブラウザ、Word、Excel、PowerPointなど業務で使用するアプリケーションに応じてカスタマイズされた拡張機能群「Stella Extension for Biz」も提供する。
ワンクリックでの要約や翻訳、選択範囲の解析など、業務で利用するアプリケーションごとに適したAI活用を開始できる。
AI利用の知見が蓄積されるワークスペース
社内の各部署や各チームなどでワークスペースを作成し、組織の業務に使えるAI活用のテンプレートやRAGを共有できる。テンプレートは利用回数や作成者が表示され、組織内での活用を促す。
組織や業務に特化したテンプレートを作成することで、AIの利用経験や知識の有無にかかわらず誰もがAIを活用できるとのことだ。
使いこなしサポートで有効活用を支援
組織全体でAIを有効に活用するため、導入時のガイドライン策定支援や設定サポート、導入後の勉強会開催や相談窓口の設置など、「使いこなしサポート」も提供する。さらには、AIの活用状況に基づいたアドバイスや事例の共有により、AIの利用率向上を伴走型でサポートするとのことだ。