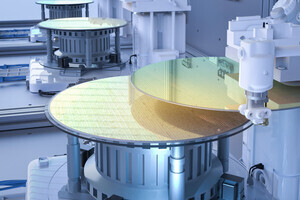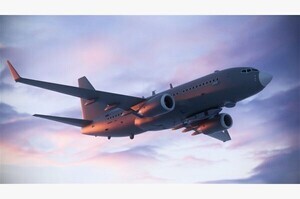イスラエルがイランの核開発施設などを攻撃
6月13日、イスラエル軍はイラン各地の核関連施設を含む数十カ所の軍事拠点を空爆したと発表した。イスラエル国防相のヨアブ・カッツ氏はこの攻撃を「イランに対する先制攻撃」と明言。イラン国営メディアは同日未明、首都テヘランや中部ナタンズなど5カ所が攻撃を受け、核開発の要であるナタンズのウラン濃縮施設から黒煙が上がる映像を報じた。さらに、革命防衛隊の最高司令官ホセイン・サラミ氏や複数の核科学者が死亡したと伝え、イランは報復を宣言した。中東情勢の緊迫化が一段と進んでいる。
こうした中東の不安定な情勢は、日本企業にとって「イスラエルリスク」として無視できない課題となっている。特に、2023年10月のイスラエルとパレスチナ自治区ガザ地区を実行支配するイスラム組織ハマスとの軍事衝突以降、イスラム諸国を中心に、ガザ地区への容赦のない攻撃を続けるイスラエルへの批判が高まり、イスラエル企業との取引が企業イメージや事業継続に及ぼすリスクが顕在化している。近年、イスラエル企業とのビジネスは、評判リスク(レピュテーションリスク)や地政学リスクとして、日本企業が慎重に検討すべきテーマとなっている。
日本企業がイスラエル企業との取引で直面するリスク
例えば、川崎重工業はイスラエル製ドローンの輸入を巡り、国内で強い反発に直面した。2024年7月、パレスチナを支持する市民団体が、川崎重工業の神戸本社前で抗議活動を展開。同社は防衛省の防衛力整備計画に基づき、イスラエル製ドローン1機の輸入代理店契約を結んでいるとされるが、団体はこれが「パレスチナでの人道危機に加担する行為」と批判。イスラエル製ドローンの購入は、イスラエルに経済的利益をもたらすだけでなく、パレスチナでの軍事行動を間接的に支援するとの主張を展開し、契約解除を求める2万人以上の署名を提出した。この抗議は、企業が人権や国際法への配慮を怠った場合、社会的批判にさらされるリスクを示している。
同様に、伊藤忠アビエーションも、イスラエル企業との関係見直しを迫られた事例として注目される。2024年2月、同社はイスラエルの軍事企業エルビット・システムズとの協力覚書(MOU)を終了すると発表した。この覚書は2023年3月に締結され、防衛省の要請に基づき自衛隊向け防衛装備品の輸入を目的としたものだった。しかし、2023年12月には伊藤忠アビエーションの本社前で、エルビット・システムズとの提携中止を求める抗議デモが発生。国際司法裁判所(ICJ)が2024年1月にイスラエルに対し、ガザ地区でのジェノサイド防止のための全ての手段を講じるよう命じたことも影響した。同社は提携が中東紛争に直接関与するものではないと説明したが、ICJの命令などが提携終了に起因したと思われる。具体的な理由は明らかにされていないが、イスラエル企業との関係が企業ブランドに与える悪影響への懸念が背景にあったとみられる。
日本企業に求められる地政学リスクの動向への注視
これらの事例から、日本企業がイスラエル企業との取引で直面するリスクは、単なる経済的損失に留まらない。イスラエルによるガザ地区への攻撃がジェノサイドと批判される中、イスラエル企業との取引は、国際社会や消費者から人権侵害への加担と見なされる可能性がある。特に、ソーシャルメディアの普及により、抗議活動や不買運動が急速に広がるリスクが高まっている。実際、2024年10月の日本国際航空宇宙展では、エルビット・システムズのブースに対しデモ隊が抗議し、ブースが早期閉鎖される事態も発生した。
近年、イスラエル・ネタニヤフ政権に対する国際的非難が広がり、イスラエル企業との関係が企業にとってレピュテーションリスクとなってきたが、今回イスラエルが再び先制的な攻撃をイランへ仕掛けたことで、イスラエル企業との連携は今後さらに難しいものになる。イスラエルは中東のシリコンバレーとも呼ばれ、同国のハイテク企業の発展は目覚ましく、イスラエル企業との関係強化を目指す日本企業も多い。しかし、ハイテク分野でイスラエル企業との関係強化を目指す日本企業は、上述のような地政学リスクの動向を注視していく必要があろう。