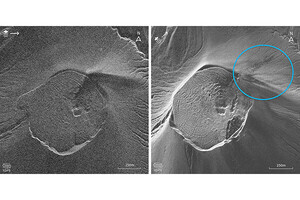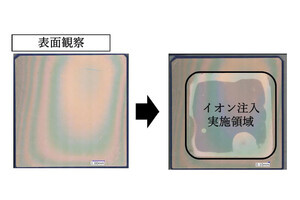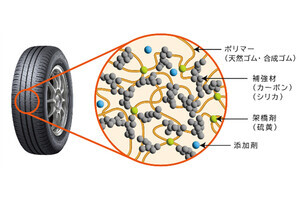優れた女性科学者をたたえる「猿橋賞」が、昆虫の聴覚情報処理の仕組みを解明し、ヒトと似た機構があることを見いだした、名古屋大学大学院理学研究科教授の上川内(かみこうち)あづささんに贈られることが決まった。主宰する「女性科学者に明るい未来をの会」(中西友子会長)が発表した。
授賞理由は「昆虫脳における聴覚情報処理原理の解明」。多くの動物は耳や触覚を使って、空気の振動である音を感じ取り、脳で処理し、他者とのコミュニケーションに役立てている。この仕組みの不思議に迫るのが、上川内さんの研究テーマだ。動物のモデルとして実験などに使われるショウジョウバエを使い、生理学や行動学、分子生物学、形態学などの多彩な技術を生かし成果を上げてきた。
ショウジョウバエは触角にある「ジョンストン器官」で音と重力の情報を得ているが、それぞれを担う神経回路が別々であることを、2009年に発見した。ヒトなどの哺乳類でも、音と重力の情報は異なる脳の部位で処理される。これとよく似た仕組みが、進化的にかけ離れているはずのハエで判明したことで、種を超えた聴覚情報処理の理解につながる成果として注目された。
ハエの聴覚による行動を大規模に効率よく調べるため、独自の自動画像解析プログラムを2013年に開発した。現在は潮流となっている、動物行動のビッグデータ解析に先鞭(せんべん)をつけた。この手法を活用し成果を重ねた。
多くの日本人は英語のRとLの聞き分けが苦手だが、赤ちゃんの頃は米国人と変わらないという。ヒトなどは子供の頃の音の経験が、成長後の音感に大きく影響する。一方、ハエの聴覚は先天的と考えられていた。しかし上川内さんは、ハエが若いうちに求愛の音の刺激を受けると、成熟後に仲間の求愛の音に応じて行動することを、2018年に発見した。このような、聞いたことのある音で行動を変える「歌識別学習」を担う神経回路の機構も昨年、解明した。求愛の“歌”を聞いた経験が、求愛を受け入れるか否かを決める脳の機能を調節している。
同会は「ショウジョウバエというモデル動物を用いて、動物種を超えた聴覚情報処理の原理に迫る先端的研究で優れた業績を上げ、国際的な研究者として世界的に高く評価されており、今後の研究の進展も大いに期待される」とした。
先月21日の会見で上川内さんは「歴史ある賞をいただき大変名誉なこと。日々の積み重ねでここまで来られた。女性に限らずいろいろな背景の人が研究しやすくなってきていると感じる。そういう状況を今後の人たちもうまく活用し、私以上に羽ばたいていくと期待している」と話した。
1975年、東京都生まれ。東京大学薬学部卒業、同大大学院薬学系研究科博士課程修了。科学技術振興機構(JST)バイオインフォマティクス推進センター研究員、独ケルン大学留学、東京薬科大学生命科学部助教を経て2011年9月~現職。19年12月~23年3月、東北大学大学院生命科学研究科教授(クロスアポイントメント)。22年10月~名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所教授兼任。
同会は地球化学者の猿橋勝子博士の基金により創設され、同賞は今年で45回目。贈呈式は今月24日に東京都内で開かれる。
|
関連記事 |