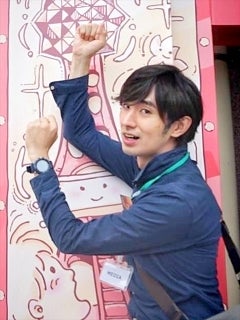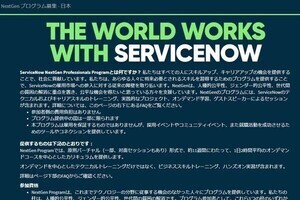世界標準とは言えないながらも、日本企業においても女性の社会進出が進んでいる。結婚・出産を経てもキャリアを継続したいと考える方が増えている。
とは言うものの、妊娠・出産・育児は女性の人生における大きな転換期。実際のところ、仕事と両立できるのか、不安に思う女性も依然として多いのが現状だ。特に仕事に重きをおいてキャリアを築いている方はなおさらだ。
そこで本企画では、異なるライフステージ、異なるキャリアを持つ3人の女性に、それぞれの経験や考えを語ってもらった。
出産を迎える人に向けて
川嶋沙央理さんは、人材紹介会社やWeb制作会社を経て、いまはAWS専業のクラウドインテグレーターであるサーバーワークスの広報を担当している。そして昨年、31歳で初めての子どもを妊娠。「妊娠が分かったとき、嬉しい気持ちと同時に、今後のキャリアについて考えるとやはり不安もありました。同年代でバリキャリ(バリバリ働くキャリアウーマン)として活躍している女性は、まだ子どもがいない人も多く、子どもがいるとやはり描くキャリアとの両立は難しいのかな、とも思ったんです」と川嶋さん。
田中優子さんは、新卒でトヨタ自動車にマーケティング職として入社。その後、大手外資系コンサルティング会社で経営コンサルタント、クラウドワークスの取締役などを経た。現在は複数社の社外取締役として活躍している。プライベートでは小学生のお子さんを持つ母親。
「私は41歳のときに出産しているので、もし川嶋さんと同じく31歳のときに妊娠していたら、また状況は違っていたと思います。時代の違いもあるし、その年齢における自分のキャリアも違ったでしょうから。もっとも31歳のときに妊娠していても、仕事を続けることに迷いはなかったと思います」と話す。
小澤美佳さんは、リクルートでHRの営業を10年間経験したあと、32歳で中米のベリーズという国に移住し、現地で観光会社を経営。その後、日本に戻ると、人事、経理、営業事務などの事務周りの業務をアウトソーシングで請けるニットに転職。1人目のお子さんが生まれた。
その後に起業し、現在は会社員として広報をしつつ、令和PRという自身の会社も経営している。実は3か月前に2人目のお子さんが生まれたばかりだという。「私は32歳のタイミングで、結婚か夢か、の究極の選択をしました。その結果、夢を追いかけたんですが(笑)。1人目を出産したのが37歳です。私もちょっと遅めの出産でしたが、仕事はいつでもできる、けれど出産は物理的にタイムリミットがある、という思いがあった。わずか10年ほど前の話ですが、私の友人にも『バリキャリを続けるために出産を控える』という人は多かったです」。
いまの仕事を続けたい、でもいつか子育てもしたい--。世の中の多くの女性が、そんな悩みを抱えながら働いている。では、いつ産むのがベストなのか?小澤さんは、こう断言する。「これは個人的な思いですが、いつの時代もバリキャリでいく人は、バリキャリをやめるつもりはない。であれば人生ずっと忙しいんだから、産みたいと思ったときに生んだら良いと。自分の経験を振り返って、いまならそう思えます。生んだら当然、仕事に費やせる時間は短くなりますが、そうなったら生産性の上げ方を考え直す、働き方を見つめ直す。その良いきっかけになる、と思うんですよね」。
川嶋さんには、妊娠が分かったときの心境、出産に向けた現在の思いについて聞いた。「業務の都合上、代表の大石にも妊娠の報告したんですが、第一声が祝福の言葉だったことだったことに正直驚きましたし、社会は変わってきているんだなと実感しました。『女性が出産を経ながらもキャリアを伸ばしていく社会は、今後も増えていく。育児しながら、自分のキャリアも大事にしていってください』という言葉をかけてもらえました。
以前は、育休を経て会社に戻ると仕事内容が変わっている、お給料が下がっている、業種が変わっている、転職しか道がない、なんてことが事実としてありましたから、サーバーワークスの様な会社も増えてきているんだなと」。
これから育休に入る人に、送るべきアドバイスは?田中さんは次のように話す。
「これまで会社で頑張って働いてきた人なら、育休中に長く職場を離れることに不安を感じることもあるでしょう。だから、ほどほどに会社と繋がっておくのも良いと思います。会社から数カ月間離れるだけで、戻るとき結構緊張しちゃいますからね。具体的には、リモートでちょっとした仕事をこなす、資料の作成などを手伝う。復帰が近づいたら、社内のミーティングに顔を出す。もちろん会社との交渉が必要ですが、育休手当が減額されない範囲(育休開始時の賃金月額の13%以下の報酬での稼働)で働く、そんな時間の過ごし方もありかなと思います」。
育休中に気をつけるべきことは?
育休に入ったら、気をつけるべきことはあるだろうか?
小澤さんは「同僚はバリバリと働いていて、会社からも評価を得ているのに、自分は家にいて子どもとばかり喋っている、だから『もう自分には社会的価値なんてないんじゃないか』、そんな思いに囚われたりするかもしれません。私の先輩も、それで病んでしまいました。子育てのノイローゼではなくて、社会から置いていかれる、という恐怖感が原因です。
きっと会社の同僚は、気を遣って『あの人には仕事を入れるな』『チャットから外そう』なんてしてくれるでしょう。すると余計に疎外感が強くなる。先ほど田中さんも仰っていましたが、ちょっとでも良いので、緩く会社と関わり続けることが大事だと、私も思います。社員のお悩み相談を引き受ける、ちょっとしたアドバイスを送る、そんなことでも良いでしょう。どんな形であれ仕事や社会とつながっておく。そして、ちょっとずつ緩く社会復帰していくのが良いと思います」。
この意見に、川嶋さんも「育休中の不安として、社会から外されちゃうっていう感覚は、確かにありますよね」と大きくうなずく。
出産はキャリアに響くのか?
出産・育児のため一定期間、会社には不在となる。これはキャリアを積むうえでマイナスになるのだろうか?同僚と比べて“遅れる”ことにもなる?そんな問いかけに、小澤さんは「実際はそんなことはないです」と回答する。また田中さんは、次のように続けた。
「1年程度の育休を取ることで遅れを取る感じがしてしまう、この感覚こそ罠だと思うんです。新卒で入社した会社で、みんなでヨーイドンで走り始めることが当たり前だった、昭和的企業の価値観です。いまや企業も働き方もさまざまですし、たとえばスタートアップや外資企業なら中途採用の人の方が多い。もはや誰が何年目で何歳か、なんて誰も意識していません。
昔だったら、入社したらその会社で部長まで登りつめる、それができなかった人は脱落した人、なんて思われていたかも知れない。でもいま、そんな時代でしょうか?実際、若い人たちを見ると、転職や独立も当然のことと見据え、自分のスキル、キャリアをどうやって構築していくか、上の世代が持てなかった視点で判断しているのを感じます」。
小澤さんは「私も若いうちは『仕事がすべて』という走り方をしていました。だから妊娠・出産となったとき、これからどうなるの、これまでのように仕事は続けられるの、という不安がありました。存在意義を仕事に置いていたから怖かった。でもいま振り返ったら、社会人だった自分が妻になり母になり、人生に彩りが増えた。これまで先輩たちが仰っていた意味がよく分かりました」。
働く女性の子育て論
ここで2人は、仕事と子育ての両立の仕方についても触れた。
実際に子どもを出産してみると、住んでいる地域の行政のサービス内容の違いにも関心が向く、と話したのは小澤さん。「たとえば、どこの区は保育園の申込書がとても細かくて大変、どこの区ならベビーシッターの利用支援がどこまで受けられる、といったような違いがあります」。
これに田中さんも「子どもが産まれるまで、そんなこと考えたこともなかったですよね」と応じる。「私の住んでいる区は想像していたよりも子育て支援が手厚くて助かっています。でも私の友人が住むある区は、認可保育園において0歳児の延長保育が認められていないらしい。だから0歳児は5時にお迎えする必要がある。そうなると、もうフルタイムで働くことは無理です。私の友人は弁護士ですが、週5でベビーシッターにお迎えに行ってもらう選択をしたそうです」。
田中さんは、子育てについて持論を展開する。
「子育てに関して、自分に高いハードルを設けちゃうことがあります。ご飯は手作りしなくちゃいけない、保育園に長時間も預けるのは良くない、といったことです。昔、自分の母親がしてくれたことを思い出して、自分にプレッシャーをかけてしまう。私自身、子どもを保育園に預け始めるとき、自分の母性がとても強くなっているのを感じました。子どもがとても小さいうちから長時間人に預けて面倒を見てもらうことに、罪悪感が襲ってくる。できれば子どもに付きっきりでいてあげたい、だから仕事は辞めてしまう、という人がいるのもよく理解できます」。
しかし、実際には週5で保育園に預けることにした。そればかりか保育園では、夕食も食べてさせてもらうことにしたらしい。なぜだろう?
「母性が過剰に強くなるのはホルモンバランスのせいで、一時的なものだと自覚していたというのが大きいです。なので、そこはあえて合理的に考えて、保育園のサービスを使い切ろうと割り切りました。そのおかげで、買い物をして、自宅で料理して、食べさせて、という平日のタスクを減らすことができた。私は6時過ぎまで会社で働いてから、7時前後に子どもをピックアップして帰宅するのが日課でしたが、子どもの食事は保育園で終えているので自宅では寝るだけです。その結果、子どもは機嫌よく遊ぶ時間ができて、早く寝かせることもできた。本来なら親がやるべきことなのに、と罪悪感に苛まれるかもしれませんが、心理的な負担を感じる必要もないと思うんです。
親にしかできないことってあるじゃないですか。たとえば掃除とか料理って、親じゃなくてもできる。また、子どもが未就学児のうちは、安全や健康管理などケアの要素が大きいと思うんですよね。それに対して、保育園は子ども一人ひとりに手厚く目を配ってくれる。一方、子どもが小学生になると、立派に意思も芽生えてくる。学校では勉強もあり、友だち付き合いなど人間関係の難しさなど、子育てに教育的な要素が増えてきます。でも、学校は一人ひとりの子どもにそこまで目を配ってくれません。だから、より親のサポートが必要になるし、私も以前よりもっと子どもに関わってあげたいという気持ちがあります」(田中さん)。
育休中に起業もアリ?
小澤さんは、育休をきっかけに会社を起業している。どのような経緯だったのだろう?
「やるなら今かな、という気持ちでした。やはり社会人だと、育休によりどうしても会社と同僚に、仕事のシワ寄せがいってしまいます。もちろん、マイナビニュースの読者の皆さんに『妊娠したら育休中に起業しろ』と呼びかけるつもりはありませんが、副業を1本持っていると妊娠・出産を経ても自分のやりたい仕事を緩やかに続けられる、そんなことを思うんです。カカシみたいに支柱が1本だと、それがなくなったらグラっと傾きますが、2本か3本あれば『そっちでも生きていける』と余裕ができる。精神的にも安定します」。
ここれに対し、田中さんは自身の経験からこう補足する。「スタートアップ企業だと、そもそも育休を取っている前例が少なかったり、子どものいる社員をサポートする制度がなかったりもします。自分が『社員で初めて出産する人』になるケースだってある。そうしたら“初めて育休を取得する私”がやりやすいように制度を作ってしまえばいい。たとえば、育休中でもちょっと働きたいんですと申し出る。上司も考えてくれるでしょう。すべて、これまで私がやってきたことなんですが(笑)」。
2人の話に、熱心に耳を傾けていた川嶋さんは「勉強になることがたくさんありました。地域行政の話、会社の制度の話など、知らないことがとても多いことに気付かされました。やはり妊娠・出産を経験した先輩たちに、さまざまなことを相談できると良いですね。なかなか起業まではできそうにありませんが(笑)、そんなロールモデルとしてのお話を聞いていると、女性の働き方にも限界値なんてないんだな、と思います」。
子育てに図々しくなって良い
今回の企画では、女性のキャリアにおける多様性と可能性についてさまざまな話題が出た。最後に、マイナビニュース読者に向けたメッセージをもらった。
田中さんは「子育ては楽しいです。仕事とは違う種類の楽しさです。パートナーとはよく話し合って、お互いに何も分からない出産直後から一緒に子育ての経験値を積んでいけるようにするといいと思います。その方が楽になります。また、職場には『子どもがいるので何時以降の打ち合わせは無理です』といった宣言をしてしまっていいと思います。自分の望むスタイルに“図々しくなれる人”が当たり前になれば、日本の社会も変わっていくと思うんです」。
小澤さんは「子どもとの時間は、何ものにも代えられない大事な時間です。この10年間で、社会は多様性を受け入れるようになりました。ベンチャー、スタートアップにお勤めの人であれば、出産した人がパイオニアになってくれたら。また会社に制度がないなら、率先して作って欲しい。そんなマインドで働ける人が増えたら良いなと思います」。
川嶋さんは「今回先輩たちの話を聞いて、そこまで心配しなくてもいいんだと安心しました。現在勤めているサーバーワークスはキャリアと育児の両立に理解があり、働く時間や場所などにも寛容なので、恵まれた環境にいると思っています。。今後も、自分の思うようなキャリアを歩み続けられるよう、努力を積み重ねていけたらと思います」と話した。