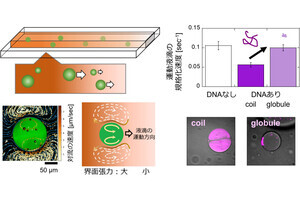近畿大学(近大)は12月20日、イチイ科カヤ属の常緑針葉樹である「カヤ」の変種の1つで、和歌山県の天然記念物に指定されている「ヒダリマキガヤ」群のうち、世界遺産である高野山の山麓に位置する和歌山県海草郡紀美野町の推定樹齢400年の樹が、接ぎ木によって積極的に増殖されていた痕跡を発見し、接ぎ木技術が利用された現存する樹としては和歌山県内最古と考えられることを発表した。
同成果は、近大 生物理工学部 生物工学科の堀端章准教授、近大 民俗学研究所の藤井弘章教授、りら創造芸術学園の共同研究チームによるもの。詳細は、近畿地区を中心とした作物学・育種学の学会誌「近畿作物・育種研究会第197回例会講演要旨集」に掲載された。
世界遺産である高野山の山麓で栽培されているカヤの樹は、1本の木材から作り出される仏像製作に利用されるだけでなく、実から採れる油が良質な食用油となり、厳寒期でも固まることがないため、冬期の灯明にも用いられてきた。そのため、和歌山県の紀美野町などの「旧高野寺領」(江戸時代に幕藩体制が整備される中、平安時代から続く荘園の維持を認められた、紀州藩などに属さない地域のこと)では古くからカヤの樹の栽培が奨励されており、カヤの実は年貢として高野山に貢納されていた。古くは、仏像製作のために直立して育つカヤが栽培されてきたが、ある時期から油の収量の多いヒダリマキガヤの栽培が奨励されるようになったことが推定されているという。
また、カヤの実は縄文遺跡からも発見されており、狩猟・採集生活をしていたころからカヤと人とのつながりは深く、カヤの遺伝子を調べることで、山村と農村での人の生活や交流を明らかにできる可能性があるという。直立して育つカヤは用材として極めて優れていたため、バブル経済期に多くが伐採されてしまったが、ヒダリマキガヤ(大きく長い実や種子にねじれた線があることが名前の由来)は、幹が直立せず分枝も多いことから用材として劣るため、現在でも樹齢800年を超える古木が残る。そのため、ヒダリマキガヤの遺伝解析を行うことで、より古い時期から人の生活の一端を明らかにできるとする。
ヒダリマキガヤは、上述したように材木用には適していないが、果実の収量が多く、油の生産性に優れている点が特徴だ。近畿圏を中心にいくつかの地域に分かれて集中的に生育しており、自然に生息域を広げたのではなく、人為的に栽植されたと推測されている(旧高野寺領もそうした地域の1つ)。
紀美野町の「ヒダリマキガヤ群」は、2019年に和歌山県指定天然記念物となった。天然記念物に指定する際の調査では、種別判定が形態的特徴に基づいて行われたが、実際には判別困難な樹も少なくなかったという。そこで研究チームは今回、分子遺伝学的手法を用いて、紀美野町内のカヤの「遺伝的構造」を調査したとする。なお遺伝的構造とは、生物は同種であっても地域によって遺伝的な多様性を保有している場合があり、そのことを指す。
今回の研究は、高野山麓のカヤの樹の成立を、分子生物学的手法を用いて解析した初めての調査となるとのこと。特に、根元は共通でありながら、部分的に異なる幹の特徴を示す樹が複数見出されたことから、複数の部位からDNAサンプルが採取され、単一樹内の遺伝的差異の有無が検証された。それにより、これらの樹に接ぎ木技術が使われたことが明らかにされたのである。さらに、この事実から、400年以上前よりカヤの樹において接ぎ木技術を用いた繁殖が積極的に行われていた可能性が示唆されたとした。
-

ウォード法による19サンプルのカヤに関する「デンドログラム」(クラスター分析で得られた情報を図示したもの)。丸数字はヒダリマキガヤを、四角数字はその他のカヤが示されている(出所:NEWSCAST Webサイト)
また、この解析で紀美野町内のヒダリマキガヤを含むカヤの樹の遺伝的構成に、これまでに知られていなかった地域的差異が存在することが初めて示されたとする。高野山地域のカヤの樹は人の手によって管理されていたと考えられるため、地域による遺伝的な差異は当時の人の交流圏の範囲や交流の密度を考える上で重要な情報となるという。また、県の天然記念物に指定された「ヒダリマキガヤ群」は保護や活用が推進されており、今回の研究成果はそうした取り組みにも貢献できると考えられるとしている。