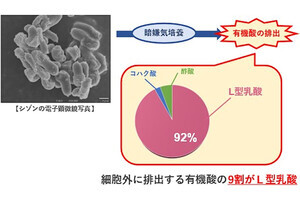バスクリンは12月17日、40歳以上の男女を対象として入浴習慣と健康状態について検討した結果、湯船につかる浴槽浴を毎日行うことに加え、日々の入浴で体温を上げ、1週間あたりの累積においても体温を高める習慣が健康維持のカギであることを実証したと発表した。
同成果は、バスクリン 製品開発部の石澤太市氏、同・小番美鈴氏、同・奥川洋司氏、同・中西信之氏、同・松本圭史氏、東京都市大学 人間科学部 早坂信哉教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、日本健康開発財団が刊行する「日本健康開発雑誌」に掲載された。
入浴を提案する具体的な方法は、お湯の温度や入浴時間などで示されることが多いが、ヒトの体温の上がり方はお湯の温度や入浴している時間、お湯につかる深さなどによって変わってくるほか、年代や性別によっても異なってくる。そのため、個人ごとに適した入浴法を提案することが必要だと考えられるという。しかし入浴習慣と健康状態については、入浴頻度と心身の健康状態に関連性があることをこれまで報告されているが、入浴方法についての報告は少ないのが実情だった。
そこで研究チームは今回、入浴時の体温変化と健康状態との関連性を見出し、“入浴でほどよく体温を高める習慣が健康につながること”を仮説とし、それを実証することを目的とした実験を行ったとする。
今回の研究では、40歳以上の健康な男女54名(女性22名・男性32名)を対象に、自記式アンケートによる入浴実態調査(入浴頻度、湯温度、入浴時間、深さ)、質問紙による健康状態調査(生活の質、気分プロフィール、健康感など)、健康状態の実測値(歩行試験、脳活動試験、健康診断結果など)が調べられた(調査期間は2021年10月~2022年5月)。
そして、入浴実態調査による被験者属性(年代、性別)と入浴実態(湯温度、入浴時間、深さ)より入浴時体温上昇値が推定され、入浴頻度を乗じて「週あたり累積体温上昇値」が算出された。その上で、「入浴頻度」を週7回以上とそれ以外の2群に分け、健康状態との関係についての解析が行われた。なお「週あたり累積体温上昇値」は、男女間で差を認められたため、性別に平均値で2群に分け、健康状態との関係について解析が実施され、高値群と低値群で心身の健康状態の比較が行われた。
分析の結果、「週当たりの累積体温変化」の高い群は、質問紙による生活の質や気分状態、歩行試験による歩幅や歩行速度などの歩行状態、老化に関する意識調査、脳活動状態、健康診断時の脂質に関する指標などが良好であることが認められたとのこと。また主観的健康感が高い群は、入浴時に体温を約1.1℃高めていることが認められたとした。
-

入浴で体温を高めた群の方とそうでない群とで有意な差が認められた結果。(左上)女性のQOLの質問紙の評価結果。入浴で体温を高めている群の方が良好だった。(右上)女性の健康診断の結果。入浴で体温を高めている群の方が、中性脂肪の値が低かった。(左下)男性に対する、モニター画面の数字をタッチ操作した際の速度の結果(脳活動の素早さが表されている)。入浴で体温を高めている群の方が素早かった。(右下)男性に対する、注意力散漫になったと感じるかの問いの結果。入浴で体温を高めている群の方が感じていなかった(出所:バスクリンWebサイト)
これらのことから、入浴習慣である「入浴頻度」および「週あたりの累積体温」を高めることと、QOL(生活の質)の高さとの関連が認められた。また、歩行状態や歩行速度、脳作業時の素早さ、健康診断での脂質に関する指標などが良好であることとの関連から、体温を高める入浴習慣は、健康寿命の延伸にも貢献することが期待できるとする。
この結果を受けて研究チームは、1回の入浴において体温を約1℃高めること(額にうっすら汗ばむ程度)を目安に、習慣として毎日湯船へつかる入浴を行うことを推奨するとのこと。ただし、入浴は体調に合わせて行い、入浴前後には水分補給を忘れずに行うこととしている。