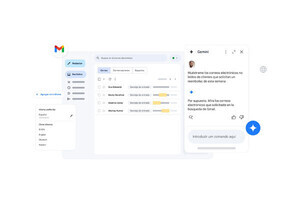Google Cloudは11月27日、Gemini for Google Workspace の最新アップデートに加え、各業界における導入事例を紹介するセミナー「Gemini at Work - Google Workspace -」を開催した。本稿では、船井総研ホールディング グループIT推進部 兼 コーポレートストラテジー部シニアマネージャーの石田朝希氏によるプレゼンテーションを紹介する。
全社員1500人にGemini for Google Workspaceを配布
石田氏は登壇するなり「11月に全社員1500人にGemini for Google Workspaceを配布した。全社展開は日本初となる」と述べた。船井総研グループでは、さまざまな業界における中堅・中小企業向けのコンサルティングを手がけ、ビジネスモデルやマーケティング支援などのビジネスコンサルティングから、IPO(新規公開株)、M&A(合併・買収)といった戦略コンサルティング、人材不足の企業におけるBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)など行っている。
同社グループの業務としては、顧客の手書きアンケートの声をホームページに掲載する際の打ち換えやWebコンテンツ素案、営業先リストの作成などを行っている。同氏は「これらの業務は一見ノンコア業務と考えられがちだが、顧客が業績を伸ばすうえでは間違いなくコア業務。この領域にGeminiは活用できる」と話す。
グループでは、Gemini for Google Workspaceが便利だから導入に踏み切ったわけでなく、「ショールーム経営」という重要な考えのもとで導入したという。
ショールーム経営について、石田氏は「単に紹介するだけでなく、工夫した使い方やノウハウを顧客仕様へのカスタマイズや、新たなユースケースの創出などを考え、コンサルタントが蓄積して提供する。当社が徹底的に使い込むことで、Gemini for Google Workspace活用のアイデアが生まれることを期待している」との認識を示す。
ライトユーザーのレベルをいかに引き上げるか
当初、船井総研グループでは2009年に全社で旧G Suiteを共通のグループウェアとして利用開始した。同氏は「Gmailやドライブ、Meet、カレンダー、スプレッドシートなどを利用していたが、各コンサルタントのフォルダの中に有象無象のデータが溜まり、まったく整理されていなかった。」と振り返る。
2022年の生成AIブームもあり、同社グループでは「Azure OpenAI Service」を用いて、自社の人事・総務関連の問い合わせに対応する「FUN-AIセンパイ」を利用開始。しかし、Google Workspaceのデータを読み込むことができず、通常はアクセスできない自社の業務データにアクセスするためのRAG(検索拡張生成)に開発工数を割けなかったことに加え、業務に特化したプロダクトを継続的に開発するリソースがないとの理由から、活用が進まなかったという。
そのため、Gemini for Google Workspaceが日本語対応したタイミングで全社導入を決定。導入を決めた理由として石田氏は「Google Workspaceとの高い親和性があり、低コストかつセキュアな環境だからだ。また、当社のショールーム経営で取り組んだ内容をお客さまに容易に提案できる点を評価した」と経緯を説明した。
こうして、Gemini for Google Workspaceを導入した船井総研グループでは、全社社員が生成AIを活用して企業のカルチャー変革を目指している。しかし、同氏は「当たり前に仕事に使うという文化は、まだ醸成されていない」と現状を紐解く。
グループでは導入前に社員150人を対象にテストユースケースの創出を依頼したが、うち66%は1日あたり1回使うか否かという状態のライトユーザーであり、活用されていない実態が浮き彫りになった一方で1日あたり500回使うヘビーユーザーもおり、リテラシーの格差が広がる現状を目の当たりにしたという。
石田氏は「テスト期間における1カ月あたりの平均利用回数は41回だったが、社員に対する活用促進の企画を実施した結果、現在では80回となっている。ただ、利用されているアプリケーションは『Geminiと話す』のため、次のステップとしてGmailやスプレッドシートとの連携を促進し、66%のライトユーザーのレベルをいかに引き上げるかにフォーカスした」と強調。
1500人全員が活用するためのリテラシー向上に振り切っている
そこで、これまでAIを利用したことがない、または苦手意識を持つベテランの社員を対象に4つの課題として「画像生成トライ」「殴り書きOCR」「社内のGmail検索」「メールでのサイドパネル活用」に取り組み、生成AIの利用による「驚き」や「できる」ということを実感してもらうことにした。
同氏は「これら4つの課題をクリアできなかったチームは、意外にも取締役・役員・秘書のチームだった。もちろん補講を実施して乗り越えてもらった。その後、Gemini for Google Workspaceを全社員で使い込むため朝礼の時間帯はGeminiの研修に充て、各チームから一週間におけるベストユースケースを提出し、その中からベスト5を発表している。これにより、自分事と考えられなかった社員が自分事として捉えるようになった」と、成果を口にしていた。
プレゼンテーションの終盤ではユースケースとして、コンサルティング業務における「Gems」を用いた事例を紹介。GemsはGeminiのカスタマイズ機能であり、利用者独自のチャットボットが作成できるというものだ。
同社グループでは各顧客に対して、スプレッドシートでPVやCVなどWebアクセス解析の数値を記入し、提出していた。これらの内容をGemに読み込ませて、サマリーを作成してもらうことで、無駄な資料作成や考える時間が省け、次のアクションをすぐに実行に移しているという。
石田氏は「さまざまなユースケースがあるが、要約や翻訳など過去に聞いたものが多いと感じている。そのため一般化すれば当たり前のユースケースだが、これを1500人で行うことは難易度が高いと自負している」と自信をにじませる。
そして、最後に「通常、AIのユースケースはRAGで業務内容に特化したものを開発が労力をかけて提供し、ユーザー側のリテラシーは問わなくても気づかないうちにAIを利用しているという環境を作り出している。これが当社は真逆で、エンジニアに負担をかけずユーザー側のリテラシー向上に振り切っている。そのため、1500人全員が使えるようになれば社内のカルチャー変革が進み、コンサルティングの生産性とともに品質が向上し、価値を創造する仕事につなげていける。私たちの姿を見て、中堅・中小企業の方には自分たちもできると自信を持ってほしい」と述べ、話を結んだ。