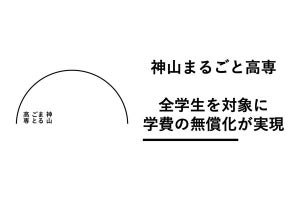徳島市中心部から自動車で30~40分ほど走らせた山深い場所に位置する徳島県神山町。同町には鮎喰川が流れ、何を隠そう同県の特産品「すだち」の生産が日本一としても知られている。
そんな大自然に囲まれた地に「神山まるごと高等専門学校」(以下、神山まるごと高専)がある。同校はさまざまな国内企業が支援しており、そのうちの1社がフォトシンスだ。今回、前後編にわたり、同校の成り立ちや社会的な存在意義などについて紹介する。
すべて“まるごと”学ぶ「神山まるごと高等専門学校」
ご存知の方も多いかと思うが、前段として高専の説明をしたい。高専は実践的・創造的技術者を養成することを目的とした高等教育機関であり、中学卒業後に5年間集中して専門的に学ぶことに主眼を置いている。現在、全国に国公私立で計58校あり、全体で約6万人の学生が学んでいる。
私立校の神山まるごと高専は人口5000人の神山町に立地している。2023年4月2日に19年ぶりとなる高専として開校し、学科はデザイン・エンジニアリング学科で全寮制となっている。学生数は1学年40人の計200人だが、現在は開校から2年目のため約80人以上の学生が在籍。校歌「KAMIYAMA」の作詞は歌手のUA氏、作曲は昨年亡くなられた筆者が尊敬してやまない故・坂本龍一氏(坂本氏の没後に生前の意思にもとづき綱守将平氏が編曲)が担当している。
校舎「OFFICE」と寮「HOME」の2棟で構成し、OFFICEは地元・神山杉を用いた木造平屋建ての新築、寮は旧神山中学校をリノベーションした。2棟間は鮎喰川を隔てて徒歩4~5分の距離となっている。
神山学園 常務理事 神山まるごと高専 事務局長の松坂孝紀氏は「意思を持って“これを学ぶんだ!”と考えた学生たちが、一般的には高校、大学と7年間で学ぶことを5年間に凝縮して学ぶことに可能性を感じています。さまざまな特徴がありますが、その中でも特に違いを生み出していることは起業家たちが心から欲しいと思い、理想の学校として作り上げている点です」と話す。
実際、同校の理事長にはSansan 代表取締役社長 CEOの寺田親弘氏が就任しており、設立に伴う出資者はテックやデザインなどのビジネスを手がけてきた人たちが携わっている。
そのため、同校が育てる人物像は「モノをつくる力で、コトを起こす人」としており、テクノジー×デザイン×起業家精神の3つを軸に据えている。これは、ソフトウェアやAIなどに関するテクノロジー、UI・UXやアートに関するデザイン、リーダーシップといった起業家精神をすべて“まるごと”学ぶというものだ。
ここで気になる点は校名に冠している“まるごと”に関してだ。その点について、松坂氏は「建学の精神に“まるごと学ぶ学校”と掲げています。授業こそが学校ではなく、課外活動や寮生活に至るまで、そして学校というと失敗を取り除く方向に向かいがちですが、成功と失敗もすべてまるごと経験するため“まるごと”を付けています」と述べている。 まず、学生たちが入学して最初に行うことが4~5日間の合宿形式で行う「ITブートキャンプ」。お題として「神山町にある地域課題の解決」をテーマにアイデアソン、ハッカソン、ピッチを行う集中講義だ。
同氏は「中学校を卒業したばかりの学生たちに、まずは地域課題の解決に向けてアイデアを出してもらい、それをプロトタイプとしてハッカソンします。技術力は小さいですが、自分なりにハッカソンで開発し、プロダクトで届けるまでのピッチを行います。狙いとしては5年間で学ぶことへの意識づけ、身につけてもらうためです。授業において共通することは、社会に出たときに役立つものにしたいという点です」と狙いを説明する。
神山町に高専を設置した理由
高専卒業後のキャリアパスとして就職、編入に加え、同校では「起業」を当たり前の選択肢として、大きく捉えている。というのも多くの中学生、高校生世代にとって起業は自分以外の特別な人がやるものと考えている節も少なくないため、起業に対する捉え方も変化していく必要があるとのことだ。
こうしたことから、従来の高専とは一線を画しており、隔世の感がある。そのため、第一線で活躍する起業家が特別講義を行う「Wednesday Night(起業家Night)」を実施。実際、サイボウズ 代表取締役社長の青野慶久氏や星野リゾート 代表の星野佳路氏、ディー・エヌ・エー 代表取締役会長の南場智子氏、マネーフォワード 代表取締役社長CEOの辻庸介氏、さくらインターネット 代表取締役社長の田中邦裕氏をはじめ、錚々たる起業家たちが協力し、学生たちの学びに一役買っている。
松坂氏は「起業家の方と話すと、良い意味で当たり前の感覚がアップデートされ、自分自身が目指していく生き方やキャリアなどが少しずつ変化し、起業というもの自体が身近な存在になると考えています」と話す。
では、なぜ神山町に高専を開校するに至ったのだろうか?これはSansanが2013年にサテライトオフィスとして「Sansan神山ラボ」を開設したことで端緒が開かれた。また、当時の神山町では早期から光ファイバー網の整備を実施していたことから、ネットワークインフラの面で不安材料がなかったこともサテライトオフィスの設置を後押ししたという。
加えて、同町の風土も関係する。松坂氏は「もちろん、われわれもそうなのですが、神山町は人と異なる選択を応援するという風土が根付いています。全国に先駆けて光ファイバー網を整備するなど、チャレンジングな町です」と強調した。
現在、同校の学生は倍率10倍の入試を突破した北は北海道、南は沖縄まで全国31都道府県+海外から集まっている。その入試も一般的なものとは異なる。2024年度に関しては(1)過去3年間における自身のモノづくりの歴史を90秒の自己PR動画として作成、(2)自身が住む地域の魅力を発見し、その魅力をテクノロジーを活用してさらに向上するアイデアの提案、(3)受験の決意日から現在までの取り組みを振り返り、学習力を適切に自己評価の3つを課題とした。
松坂氏は「課題自体を楽しい、面白いと感じてくれる学生に来てもらいたいということが狙いです。そのような方々と私たちも学び合えると考えており、マッチングを非常に大切にしています」と、その意図を語る。
学生自らが資金調達を行い国際ロボット大会に出場
こうして入試を突破した学生たちが取り組むプロジェクトも意欲的なものが多い。例を挙げれば地域の夏祭りイベントの企画や農業の立ち上げ、映画祭への出品(県知事賞)、高専プログラミングコンテストへの挑戦(特別賞)、企業と共同自動運転技術の施策を自治体に提案、Podcast部の立ち上げ、国際ロボットコンテストへの挑戦など、枚挙にいとまがない。
そのうちの1つである国際ロボットコンテストの話は興味深い。これは、NHKの国内大会「NHK学生ロボコン」ではなく、グローバルで約10万人が参加する国際大会だ。
地区予選が米国ハワイで開催されるため、ロボットの作成や参加費なども含めると300万円ほどの資金が必要な状態だったが、この資金調達を学生自身が行ったという。結果的に、想定金額の300万円を超える750万円を企業などからの資金調達を実現し、決勝進出は逃したもののルーキー賞を受賞している。
松坂氏は「学生たちは来年も出場に意欲を示しており、1000万円を集めると言っています。ここに教育の本質が詰まっていると感じます。実際、300万円を集めるときに疑心暗鬼な気持ちも正直あった一方で、われわれと神山町の風土でもある人と異なる選択を応援するということを再現したと思います。来年は、1000万円を集められると考えており、教育上このような思考になることは重要です。学生の伸びやかな成長が日々あふれている状況です」と説く。
また、寮のHOME内にある食堂では“地産地食”を目的に地元食材を使用した給食を神山町役場、神山 つなぐ公社、モノサスが共同で立ち上げた神山の農業を次世代につなぐための会社であるフードハブ・プロジェクトが提供。地産地食率を平均80%超を実現しており、松坂氏は「特徴としては仕入れる食材からメニューを考えることです。通常の学校給食はメニューが決まっていて仕入れを考えますが、順番を逆転させることで地産地食を実現しています」と説く。
このような取り組みも含め、同校に対する企業からの協力体制も力強い。その1つが奨学金制度だ。企業11社の協力で基金を組成し、各企業は1社あたり10億円の出資もしくは寄付を行い、利回り5%で運用益を寄付することで全学生の学費を無償化し、協力企業はスカラーシップパートナーと呼ばれている。
各スカラーシップパートナーは4人の奨学生を支援しており、企業の取り組みなどを紹介するなどしている。一例として、富士通と奨学生は神山町のオンデマンド交通の最適化に取り組んでいる。
また、スカラーシップパートナーのほか、多くの企業がリソースサポーターなどとして教育的・経済的に協力しており、そのうちの1社にフォトシンスは名を連ねている。
「β Mentality」 - 変化を創出する学校へ
校舎のOFFICE、寮であるHOMEの2棟ともにフォトシンスの入退室管理システム「Akerun」を採用しており、HOMEへの導入が中心だ。
松坂氏は「15歳~20歳の時期に親元を離れて過ごすことから、安心・安全を担保した寮は不可欠です。こうした部分でテクノロジーを活用していくことが有効です。そのため、われわれから実現できないかとフォトシンスさんに相談したところ実現し、全校的に導入しています」と、設置までの経緯を説明した。
一方、フォトシンスは起業家の育成に加え、ハードウェアスタートアップのためモノづくりへの賛同があることから快く受け入れたという。当初は高専から有償契約での話を持ち掛けれたものの、同社では神山まるごと高専の設立の趣旨やコンセプトに賛同したほか、リソースサポーターの制度も活用しつつ、一部を支援として無償で提供している。
さらに、今後はリソースサポーターとして学校運営の面から積極的に支援しながら、将来的にはスカラーシップパートナーも含めた、さまざまな支援を検討していく考えだ。
現在、両棟には自動ドア/電気錠対応の電気制御のドア用スマートロック「Akerunコントローラー」が5台、サムターン付きの開き戸用スマートロック「Akerun Pro」が17台の計22台が導入されている。
最後に同校のビジョンを紹介したい。それは「β Mentality」(ベータメンタリティ)というものだ。下図がその考え方だ。
松坂氏は「学校経営に携わってみると、一般的に学校は安定が求められます。変化の激しい社会に対して、安定が求められる学校の乖離は大きくなります。私たちは社会の変化・流れに負けないように変わり続ける学校をつくりたいと考えており、ひいては変化を創り出せる学校でありたいなと考えており、神山町で新しい学校の挑戦に取り組んでいます」と述べていた。
前編では開校から1年半が経過した同校の取り組みを主に紹介した。神山町と一体となり、地元に根差した形で学校づくりを進めるとともに企業の力強い協力、官民を超えた巻き込みにより魅力的な高専だと感じた。特に奨学金制度による学費無償化は将来的に日本の教育機関が見習うべきポイントが多々あるように思う。後編となる次回は学生のインタビューを紹介する。