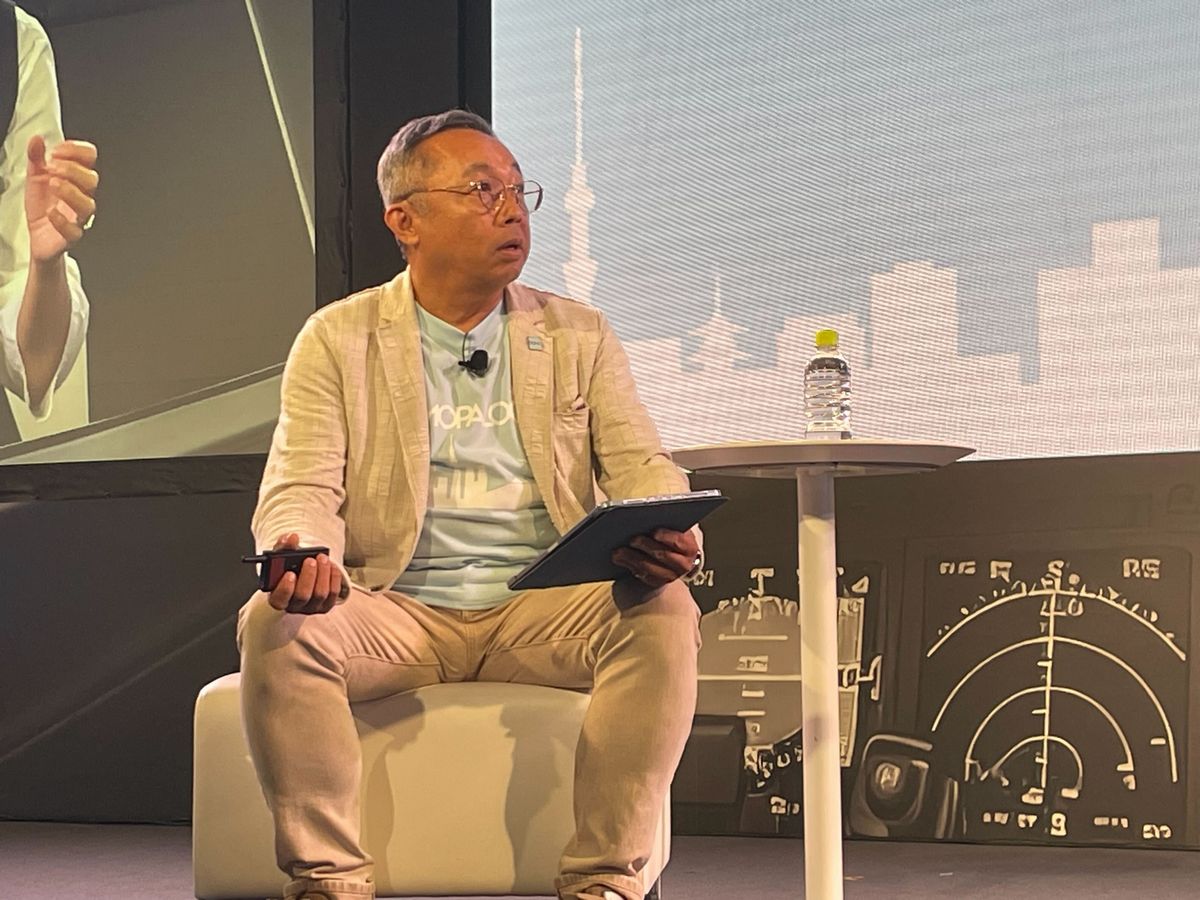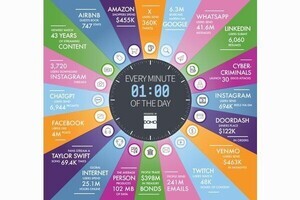Domoは10月9日、年次カンファレンス「Domopalooza Japan2024」を開催した。「データ+AI、進化した組織の旅へ」をテーマに行われた今年は、日本の玄関である羽田空港の第3ターミナルに直結しているベルサール羽田空港にて行われ、日本を牽引する各業界リーダーが組織全体でのAI、データ活用の取り組み事例、人材育成戦略を語った。
本稿では、元サッカー女子日本代表の澤穂希氏を招いて行われた、基調講演「個を繋ぎ組織を変える立役者~澤穂希はなでしこジャパンのDomoだった!?~」についてレポートする。講演には、澤氏とドーモ 取締役会長の高橋慎介氏が登壇した。
今回の基調講演では、FIFA女子ワールドカップ2011にて、キャプテンとしてなでしこジャパンの優勝に貢献した澤氏が、日本代表選手の個々の力をつなぎ、チーム一丸となって「勝ちにいく組織」へと導いたリーダーシップ、また、スピードが求められる試合場面での決断力、努力を成果に変える組織作りの秘策などを説明した。
高橋氏は「澤さんはピッチ上では司令塔として、チームメイトの力を120パーセント引き出すための『核』となる存在だった。そしてわれわれドーモも、ビジネスというエリアでは、多様な情報を駆使して、現場や経営層が的確な判断をスピーディーにできるような司令塔としてのプラットフォームの役割を担っていきたい」と、澤氏を講演のゲストに選出した理由を説明した。
「全員で勝つ」チームはどう作るのか?
最初のディスカッションは、キャプテンとしてチームを率いた澤氏が考える「全員で勝つチームはどう作るのか?」というテーマで実施された。
「日本代表は、普段所属してるチームと違って、ある一定期間に集められる即席チーム。その短い時間の中でチーム力を調整するのは非常に難しいのではないか?」という高橋氏の問いに対して、澤氏は「(代表チームでは)『チームコンセプト』に基づいて、そこにチームがどう向かっていけるかが重要」と語った。
「他国のチームと比べて身体の小さい日本人の選手が体格差に負けないためには『チームとしての連動』がとても重要でした。この部分を極めるカギが密に話し合いをすること。練習で納得できないことがあったら、全員が納得するまで話し合いをしていました」(澤氏)
この澤氏の説明に対して、高橋氏も「企業もビジョンやパーパスといった支柱があることで、そこを軸として社員が結集していく」と深く納得した様子だった。
決勝のPK戦を辞退した理由とは?
続いてのテーマとなった「試合中の意思決定」について、澤氏は、「データを用いて準備もするが、最終的な決定は現場で行うことが多い」と話した。
データに基づいた作戦や監督からの指示は当然用意されているものの、最終的な判断は一瞬の間で自分で下すことがほとんどだといい、瞬時に自分やチームメイトの状況を把握できる能力が大切だった、と説明した。
また澤氏は、アメリカとの決勝戦のPK戦を振り返り「本当は監督から4番目のキッカーに選ばれていたが『私は蹴りません』と辞退していた」という事実を明かした。
これには高橋氏も驚いた様子で、理由を尋ねられた澤氏は「サッカーに限らず、人には得手不得手がある。私は『PKが苦手』で、(4番目のキッカーとして勝負を決めた)熊谷は『PKが得意』だっただけ。チームプレイは自分の不得意な部分をチームメイトがカバーしてくれるし、チームメイトの苦手な部分は自分がカバーできる。適材適所という言葉があるように、チームが勝つためには得意な人がやった方が良いという自分の判断だった」と、自分ができないことを受け止めて人に任せるという強さを説明した。
澤氏の代わりにキッカーに選ばれた熊谷選手は、ゴール左上にボールを突き刺す豪快なシュートを決め、日本の勝利を決定付けた。どうしてもプレッシャーからゴールの下を狙ってしまいがちなPK、しかも優勝がかかったタイミングで上の方を狙える熊谷選手に「代わってもらって良かった」と、澤氏は振り返っていた。
最後には会場から質問を募集し、聞かれた「新しいメンバーとの関わり方」に対して、澤氏は以下のように語っていた。
「新しい若い選手が入ってきた時は常にコミュニケーションを取っていました。若い選手からベテランや年上の選手に話しかけるのはなかなか難しいので、こちら側から一生懸命話を聞いたり、アドバイスをしたりしていました。監督もコミュニケーションの問題を気にして、あえて年上の選手や中堅の選手と若い選手を同じ部屋にして日頃から密にコミュニケーションを取れるような環境を作れるようにしてくれていました。練習以外にもコミュニケーションの場を提供することが大切だと思います」