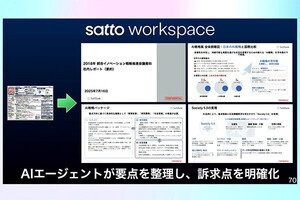企業が直面するビジネス環境の変化や人材不足といった課題を解決する手法として「ローコード/ノーコード開発」が注目されている。そこでTECH+では、ローコード/ノーコード開発を糸口に、開発レベルに合った環境から、その後も伴走してプロジェクトを推進できるような開発基盤の構築を目的に、市民開発でイノベーションを創出するための活用法を紹介する「TECH+セミナー ローコード/ノーコード開発 2024 Sep. 自組織に適した開発基盤の実装」を、9月13日にオンラインで開催した。
基調講演には、ふえん 代表取締役 安藤昭太氏が登壇。「内製化できるDXを組織でマネジメントする理論『ふえん式』とは」と題して、ノーコード開発を社内に定着させるポイントについて解説した。
ローコード/ノーコード開発の本当のメリット
安藤氏は冒頭、ローコードやノーコード開発のメリットについて触れた。一般的には、学習コストが低い、すぐに導入できる、柔軟性が高い、開発スピードが速い、開発コストが安いなどが挙げられているが、同氏は、誰かがつくったITシステムを我慢して使うのを止められる点がメリットだと強調した。
「他の人がつくった見た目が良くないデザインでも、仕事で使うからと我慢して使わざるを得ないと感じたことがあると思います。これを僕らは『デジタル学習性無力感』と表現していて、取引先の中には、『DXハラスメント』という方もいます。要はDXをやらないといけないが、自分たちでやれないところでストレスを感じたり、学習性の無力感を感じたりするということです。自分がどれだけ行動を起こしても、一切変化が起きないと分かると、人間は無力感を覚え、受身になって希望が持てなくなるということがデジタルでも起きているのです」(安藤氏)
同氏によれば、デジタルの学習性無力感をなくすとは、裏を返すと、社員の力を信じることだという。これまでは、自社の基幹システムや海外の会社がつくったクラウドサービスに自分たちの業務を合わせていたが、ローコード/ノーコード開発は、自分たちの業務に合わせてツールをつくっていくことになり、そのためには、社員を信じることが大切になってくると話す。
「トップがこう変えると宣言して、そのやり方は現場の人に任せるというところが大事です。柔軟に変化するところが、企業の競争優位性になるとに感じています。それはノーコードを活用することによって、実現ができると私達は信じています」(安藤氏)
「ふえん式」とは
ふえんは、コードを書かない業務DXを支援しており、そのために「ふえん式」という、組織としてノーコードを導入するフレームワークを推奨している。
「ふえん式」は、理論と実践を体系化したもので、情報処理推進機構(IPA)が出しているスキル標準+DXのスキル標準、ノーコード開発版のプロジェクトマネジメント標準を軸に、国内外の事例を調査して実践としてまとめているという。
「ふえん式」では、ノーコードを活用する組織の成熟度を、とりあえずノーコードを使ってみる「体験化」、実験してみた結果をまとめていく「知識化」、ビジネスとしての良い影響がどれくらいあったのか、人材も含めてどういうふうに成長していくかを決める「組織化」、基幹システムに適用したり、運用を安定させたりするかたちでより高度なものに変化していく「標準化」、そして基幹システムも含めて、ノーコードを会社のIT基盤としていく「自立化」の5つに分類している。
「体験化」では、2.5%の人が利用することが重要
セミナーでは、最初の「体験化」について説明が行われた。
安藤氏によれば、体験化のフェーズでは、会社全部署の2.5%が利用することが重要だという。
「私達が実際に研修をやったり、導入サポートをやったりするときに、2.5%で始めるのが一番良く、1%だと研修から戻った後に日々の業務で忙しくなり、焼け石に水になるという経験をしています」(安藤氏)
この2.5%は、マーケティングのキャズム理論に基づいたものだ。
「キャズム理論は、昔からあるマーケティングの理論です。例えば新しいサービスが出たときに、イノベーターと呼ばれる2.5%の熱狂的なファンに使われると、その後、アーリーアダプターと呼ばれる『これは使えるかも』という人たちが増え、そこからアーリーマジョリティーと呼ばれる次の34%の人たちの手に届くと、市場に展開されるというものです。アーリーアダプターとアーリーマジョリティーの間にはキャズム(裂け目)があり、ここが壁になると言われています。ノーコードを組織に導入するところもでも、これに近いことが起きます。だからこそ、まず、先行部署で成功事例を積み上げるのが大事です」(安藤氏)
先行部署の成功事例を積み上げることで、それが口コミで他の部署に広がっていく。
「今まで紙でやっていたものがデジタルになったときに、それがいろいろな部署で広がると、『うちもやろう』みたいな現象が起きます。これを次の34%の人に広げていくことで、会社の中でノーコードができるようになります。最終的にはそれを業務プロセスに組み込むことによって、全社で展開します。ノーコードを導入する、ノーコード開発をする場合には、2.5%がまずやってみるという規模感で、予算や時間を確保することをおすすめします」(安藤氏)
ノーコードを導入する際の注意点
ノーコードを組織に導入する際の注意点としては、ITガバンスやコンプライアンスの低い領域から導入することだという。それがあまり高すぎると、ノーコードの導入に適さないと判断されるためだそうだ。
「ノーコード開発のスピードや利便性は、ITガバナンスとトレードオフになるところがあります。ノーコードは利便性が高く、すぐ着手でき、すぐ使える状態で、かつガバナンスがそれほど高くなくてもいいところから置き換えていくのが良いでしょう」(安藤氏)
具体例として同氏は、普段、Excelで管理していて、それをクラウド管理に置き換えるような場合を挙げた。
ノーコードを普及させるためのポイント
最後に安藤氏は、ノーコードを社内に普及させるポイントを説明した。
1つ目は、経営者が宣言して使ってみることだ。クレディセゾンでは、役員16人が半日間のノーコード研修を受け、LIXILでは、全社展開の前に経営層が1カ月研修を実施することで浸透を図っているという。
2つ目は費用対効果を求めないことだ。研修の時間を設け、業務として取り入れる、予算をしっかりと確保することが重要だと述べた。
3つ目は、研修として業務アプリの作成を行うことだ。
「研修内でつくったもので運用も始めると、PDCAを1回回して改善をするところまで行うことができます」(安藤氏)
4つ目は、研修は座学だけではく、実際手を動かして開発することである。
「いろいろなものを適当に選んで、それを模写する。コピーしてつくってみるというのが大事です。例えば、スケジュール管理や在庫管理などを、他のシステムを見様見真似でつくってみることが重要だと言われています」(安藤氏)
5つ目は、たくさんアプリをつくることだ。LIXILでは、合計1万7,007個のアプリケーションをつくり、そのうちの680個を実際に運用しているそうだ。
「10%以下ぐらいしか本番に乗りません。したがって、たくさんつくることが大事です。たくさん失敗することで、本当に使えるものが業務に載せられるようになります」(安藤氏)
最後に同氏は、誰かがつくったITシステムを我慢して使うのをやめられることがノーコードのメリットであり、組織でどう導入していくか大切になってくると改めて訴え、講演を終えた。