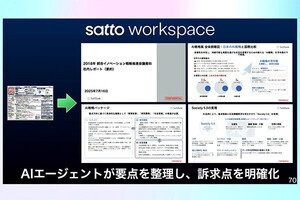ガートナージャパンは8月27日~28日、年次カンファレンス「ガートナー デジタル・ワークプレース サミット」を開催した。本稿ではLayerX 代表取締役CTO 松本勇気氏が登壇したセッション「人が、人らしい仕事に専念できる未来: 生成AIとLLMがもたらす生産性向上と業務デジタル化」の内容を抜粋してお届けする。
生成AI活用を阻む3つの原因
LayerXは「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに、バクラク事業、Fintech事業 、AI・LLM事業を行っている。松本氏はまず、生成AIの現状として「導入企業は増えているものの、定着率で見ると、定着率3割以下の企業が7割を占めている」というデータを示した。
「生成AIは“便利っぽい”ところまではいきますが、本当に便利なところにまではいっていません」(松本氏)
では何が生成AIの定着を妨げているのか。同氏はその原因を3つ挙げる。
1つ目はチャット(プロンプト)の難しさだ。生成AIを利用する際は、プロンプトと呼ばれるテキストを入力し、生成AIとチャットをするかのようなやり取りをする必要がある。生成AIの特性を理解した上でプロンプト設計をできる人の場合は問題ないが、多くの人がそれに精通しているわけではなく、「誰もが使えるシステムではない」と松本氏は指摘する。また、現行の業務の多くはエクセルや自社の基幹システムと紐付いており、「(チャットでの指示は)業務プロセスに沿っていない」と続けた。その結果、ユースケースがコールセンターや社内規定FAQなどに限られてしまいがちになる。
2つ目は業界や企業に特化したユースケースに合わせた最適化が必要なことだ。一般的な生成AIは多くの人が共通で持つ知識を学習しているため、業界特有の専門用語や判断ルールなどを認識していない。松本氏は「ジャム」を例に、一般的にはトーストに塗る甘いジャムだが、複合機業界では紙詰まりを示すと説明。専門用語が使えないと業務が進まないため、生成AI活用は遠のく。また、技術的な観点においても、業界特有の資料などを生成AIに読み込ませる場合、ファイルの前処理・後処理や、検索アルゴリズムの選定などが必要なことも、生成AI活用のハードルになっているとした。
3つ目は、生成AIの正答率が100%にならない点である。「100%にならないと使いづらい」「どこまで精度を上げれば良いのか分からない」といった悩みから取り組みが進まないことも多いそうだ。
生成AIで、知的繰り返し作業を効率化
このような問題点を挙げた上で、松本氏は「もう少し別の観点で、生成AIの使い方を考えていくべきではないか」と提案する。それが「知的繰り返し作業」への活用だ。
同氏が知的繰り返し作業の例として紹介したのが金融業界における銀行の稟議書作成・レビューやアセットマネジメント会社の書類整理である。これらは「エッセンスはあるけれども、7~8割は単純な作業」であることから、「正解が決まっていてクリエイティビティがなく、早く終わらせる以外に差別化が乏しい」と言う。
「このような知的繰り返し作業をAIに移していくことで、新しい働き方につながるのではないでしょうか」(松本氏)
では、知的繰り返し作業に対し、どのように生成AIを活用すべきか。松本氏は生成AI活用のメリットとして、業務時間の削減やヒューマンエラーの削減、業務の標準化があるとする。知的繰り返し作業の場合、プロセスの各所に、人が必要な文章を読み、解釈をして、次のプロセスへ橋渡しをしている部分がある。この部分に活用できるものとして同氏が挙げたのがLLMだ。チャットに答えてくれるだけでなく、文章の意味を汲み取り、デジタルに使いやすいかたちにする「LLMによる非構造的なデータの構造化」をすることで、橋渡しの部分も生成AIに任せることができるのだそうだ。
金融業界で言えば、従来から、帳票や契約書といった一定の型を持つドキュメントに関わる業務ではAI分析ツールが存在していた。しかしこれは「単体で事業が成立した既存のAIの領域」だと松本氏は説明する。
「LLMは市場が小さく、いろいろなバリエーションの知的繰り返し作業にも活用できます。人類史で初めて知的繰り返し作業を生成AIに任せられるようになったのです」(松本氏)
フルスクラッチを目指す際の落とし穴とは
だが、企業の生成AI活用においては、さらにハードルがあると松本氏は語る。それがフルスクラッチの受発注によるAI化の限界だ。生成AIの活用領域をチャットボットなどからもう1歩先に進めようとすると、カスタムの必要性が出てくる。そのため、フルスクラッチでの生成AI開発を……という流れになるものの、ここにも複数の課題が存在するのだ。
例えば、多様な領域で活用可能性のある生成AIを複数のシステムで構築・提供してしまうとUXにばらつきが生じることに加え、プロンプトやAIの精度を毎度それぞれで担保しなければならない。さらにセキュリティなどの非機能要件の整理・対応を毎回個別発注で対応すれば、抜け漏れが出る可能性が高まる上に、非効率的である。また、生成AIやLLMは日々、現在進行形で進化しており、これらに追従し、毎回対応することは難しいだろう。
そのような課題を解決するため、LayerXではノーコード・ノープロンプトのプラットフォーム「Ai Workforce」 を提供しているそうだ。多様なファイルやデータを分析・構造化することで、さまざまな業務やRAG(Retrieval-augmented generation)などで活用可能になるほか、モジュールを組み合わせた開発をすることで、「低コストでクイックな実装が可能」だと松本氏は話した。
セッションの最後を同氏は、以下の言葉で締めくくった。
「生成AIの活用領域は多岐にわたりますが、チャットやRAGでできることは限られています。生成AIを業務で活用していくためには、業務にあった生成AIとは何か、そのために必要なものは何かを考え、どう実現するかが重要です。チャット以外の新しいかたちで知的繰り返し作業の自動化が目指せる、新しい自動化にもぜひ目を向けてもらえればと思っています」(松本氏)