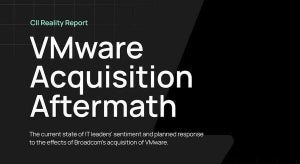米Broadcom傘下のVMwareが開催した年次カンファレンス「VMware Explore 2024」(8月26日から8月29日:ネバダ州ラスベガス)には、日本から約150名のパートナーや顧客が参加した。
これまでVMwareが有していた8,964種類のSKU(Stock Keeping Unit)と168種類の製品・バンドル・エディションを大幅に見直し、「VMware Cloud Foundation(VCF)」と「vSphere Foundation」に集約。さらにライセンスモデルを永久ライセンスからサブスクリプションモデルにした。
Broadcom CEOのHock Tan(ホック・タン)氏はプライベートクラウドに注力する姿勢を鮮明に打ち出した(関連記事 https://news.mynavi.jp/techplus/article/20240829-3014188/ )。買収から約8カ月間で実施されたこれらの変更を、日本の既存顧客に対してどのようにアプローチしていくのか。
VMware Explore 2024の会場で、Broadcom アジア太平洋地域および日本担当上級副社長兼ゼネラルマネージャーのSylvain Cazard(シルヴァン・カザール)氏とヴイエムウェア(※)代表取締役社長の山内光氏は日本メディアのインタビューに応じ、顧客の現状と今後のアプローチについて語った。
どうなる、パートナーエコシステムの変化と継続
買収に伴うさまざまな変更について、顧客からはどのような声が寄せられているのか。
山内氏は「VMware Explore 2024に参加いただいているお客様は、買収に伴うライセンスモデルや製品体系の変更を非常にポジティブに捉えていただいています。8,964種類以上あった製品をVCFとvSphere Foundationに集約し、同時に買収後はプライベートクラウドにフォーカスすることを明確にしたことで『わかりやすくなった』との評価をいただいています」と強調する。
カザール氏も「私たちは日本において、多くのクライアントと共に、長年にわたってVCFによるITインフラのモダナイズに取り組んできました。ですから、今回発表したVCF 9は多くのクライアントの(IT戦略に)一致していると確信しています」と語る。
パートナーエコシステムプログラムの変更については、数カ月前からパートナーに対して個別に説明を重ねてきたという。山内氏は「日本では日立、富士通、NECが『Value Added OEM Services(付加価値OEM)』に参画いただいています。また、NTT、IIJ、ソフトバンク、KDDIにもクラウドサービスのパートナーとして協力をいただきます。日本においては長年、パートナーを通じたビジネスモデルでした。このモデルはブロードコム傘下での体制でも継続して推進します」と説明した。
カザール氏は「日本におけるVMwareの基盤は非常に強固です。日本では大規模なITインフラのモダナイゼーションが進んでおり、レガシーシステムを最新インフラに更新する動きがあります。また、大規模企業ではデータプライバシーやセキュリティの懸念から、データをすべて(パブリック)クラウド上で扱うことはないでしょう。日本企業が高品質で非常に耐障害性の高いプラットフォームを重視することを考えれば、VCFは理想的なポジションにあり、プライベートクラウドがITインフラの主軸になると考えます」と力説する。
顧客離れの懸念と継続利用への自信
とはいえ、大幅な変更で、VMwareからの乗り換えを検討している企業もある。特に個別製品を利用していた中堅小規模企業では、VCFやvSphere Foundationの導入は予算的に厳しいという声も少なくない。そうした企業に対するフォローアップは行う計画があるのか。
カザール氏は「VCFやvSphere Foundationに製品を集約したからといって、大幅な顧客離れは予想していません」と断言する。
その理由は、集約した2製品はこれまでの中核技術を集約したものであり、以前から顧客が使用してきたものであること。そして、今後は顧客と密にコミュニケーションすることで、単一プラットフォームというプライベートクラウドがもたらすメリットを十分に理解してもらえると確信しているからだという。
「日本のお客様やパートナーは、長年にわたってVMwareの技術に投資してきました。新しい製品体系でも、コアとなる技術の根幹は不変です。VMwareから別の選択肢に移行するのは、技術者の教育を含めて簡単なことではありません。われわれは、これまで培ってきた技術を基盤に、VCFに包含されている新技術を取り入れることで、大規模企業のビジネス成果を向上させられると考えています」(カザール氏)
VMwareはグローバルなパートナーエコシステムを「OEM」「クラウドサービスプロバイダー」「リセラー」、そしてAWSやMicrosoft Azure、Google Cloudといった「ハイパースケーラー」の4カテゴリーに整理した。
カザール氏は新しいアプローチについて、「この再編により、顧客は必要なSKUだけを効率的に選択・購入できるようになりました。以前のような異なるコンポーネントを組み合わせる複雑な方法を避け、プライベートクラウドの利点をより迅速に実現できます。単一プラットフォームでフルクラウドの運用モデルを採用することで、顧客により大きな価値を提供できると考えています。市場のリーダーとしての我々の役割は、単に顧客が望むものを売るだけでなく、将来を見据えて最善の選択肢を提案していくことです」と説明した。
サブスク移行は業界標準
また、今回の買収で最も注目されたのが、永久ライセンスからサブスクリプションモデルへの変更だ。これについてカザール氏は「VMwareは最近まで永続ライセンスを提供していた数少ない企業の一つでしたが、過去3年間でサブスクリプションと永続ライセンスの併用を進めてきました。今回のBroadcomによる買収を機に、完全なサブスクリプションモデルへの移行を決定しました。サブスクは一般的なビジネスモデルであり、逆にVMwareが(移行に)遅れていました」との見解を示す。
日本では2013年にVMwareのパブリッククラウドサービスである「vCloud Air」を、従量課金型サービス「vCloud Air VPC OnDemand」として提供を開始していたが、サブスクリプションモデルへの移行戦略を明言したのは2021年だ。ただし、その際にも「永久ライセンスからサブスク併用」だった。
その点について、山内氏は「VCFやvSphere Foundationはサブスクと親和性が高いです。特に技術の更新という観点から、サブスクリプション制のほうがより効果的な提供方法だと考えています」と説明した。