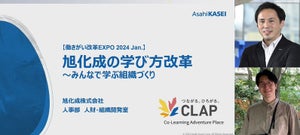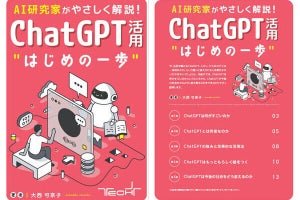市場の変化にいち早く対応するため、多くの企業が導入しているアジャイル開発。柔軟性の高い開発手法として知られ、開発期間の短縮も期待できる反面、スケジュールの調整が難しかったり、ニーズに振り回されてプロジェクトが迷走したりといった問題に頭を悩ませている企業も多い。
アジャイル ビジネス インスティテュートは7月25日、アジャイル開発を成功させている企業の事例を紹介するイベント「アジャパーシアター」を開催した。「シアター」をイベント名に冠した同イベントは、複合映画館「ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場」のスクリーン7を会場とする非常にユニークな形式で行われた。
オープニングキーノートには、旭化成 デジタル共創本部 DX経営推進センター長 石川栄一氏が登壇。同社の取り組むトランスフォーメーションについて、DXを中心に語った。本稿では、その模様をダイジェストでお届けする。
旭化成グループが注力する“トランスフォーメーション”
大手総合化学メーカーとして知られる旭化成グループ。売上の半分を占めるマテリアルや、ヘルスケア、住宅などさまざまな領域で事業を展開しており、その売上高は2兆7000億円以上(2023年度)。住宅領域で展開する「ヘーベルハウス」や分譲マンションの「アトラス」などは一般にも広く知られているブランドだろう。また、売上の半分は海外というグローバル企業でもある。
同社が早期から注力しているのが、DXだ。経済産業省が認定するDX銘柄に4年連続で選ばれており、24年度は化学メーカーで唯一の受賞企業となった。そのほか、「オープンバッジ大賞2023」大賞や「IT Japan Award2024」準グランプリなど多数の賞を獲得している。
そんな同社のDXを支える組織がデジタル共創本部である。同組織を構成する5つのセクターのうちの1つ、DX経営推進センターのセンター長を務めるのが石川栄一氏だ。
同氏は94年旭化成工業に入社後、医薬品営業をはじめ、さまざまな業務を経てデジタル共創本部CXトランスフォーメーション推進センター長に就任。2024年から現職に就いたという。
「もともとは営業なので、正直エンジニアリングはまだ全然分からないところも多々あり、部下の皆さんに助けてもらっている状況」と石川氏は笑う。
もっとも、旭化成グループにおける“トランスフォーメーション”の立役者の1人は石川氏である。なぜ石川氏は変革を急ぐのか。そこには近年の日本を取り巻く環境の変化に対する懸念がある。
「厚生労働省の資料によると、OJTの実施率や勉強会の実施率など、従業員の皆さんの学ぶ機会が多いグループほど労働生産性が高まる傾向にあることが分かっています。ところが、サービス業や小売業、飲食業などはそういった能力開発の機会がなかなか持てていません。また大企業と中小企業の格差も非常に大きいようです。さらに男性に比べると女性はOJTなどの機会が少なく、勉強会を受講する頻度も低いことも報告されています」(石川氏)
そもそも日本自体、他国に比べて従業員の能力開発の機会が多いとは言いがたい。石川氏が示した資料によると、GDPにおける企業の能力開発の割合で日本は他国に大きく遅れを取っており、しかもその数値は年を追うごとに減少していることがわかっている。
「今後、日本企業がやるべきなのは人材育成や業務効率化、省力化、省人化により今の仕事を少人数でこなせるようにすることです。そのためにはデジタルの導入と、一人一人のスキルアップがポイントになるでしょう」(石川氏)
政府も手をこまねいているわけではない。厚生労働省は2023年度予算で人材の育成や活性化に1000億円以上を計上しており、さまざまな助成金を用意している。また、東京都もDX推進支援事業を行っており、特に中小企業におけるDXを支援しているのだ。もっとも、これらの制度はまだあまり周知されていないという。
こうした状況の中、旭化成グループではいち早くDXの推進に着手。先述の通り、成果を上げているわけだ。同社は、経営の基盤強化に向けて取り組むべきテーマの1つにDXを位置付けており、並行してグリーントランスフォーメーション、そして人材のトランスフォーメーションにも着手している。
従業員約5万人のうち5%を「デジタルプロ人材」に
旭化成グループのDX推進が順調に進んでいる要因はどこにあるのだろうか。
その解として、石川氏は「人」「データ」「組織風土」の3点を挙げる。
「企業を構成しているのは“人”です。また、データを活用して経営基盤の状況を分析し、より良い製品を作り出していかなければなりません。そして、人を変革するのは組織風土です。いかにトップから組織風土を変えられるか。そういったところに現在チャレンジしています」(石川氏)
デジタル共創本部が目指すのは、デジタルプロ人材の育成だ。DX専門組織であるデジタル共創本部メンバーだけでなく、全員参加かつ現場主導により、グループ全体のデジタル変革を推進する。そのためには、現場でDXを担うデジタルプロ人材が必要なのだ。
具体的には、グループ全体の従業員約5万人のうち5%にあたる2500名のデジタルプロ人材をつくることが目標だという。
そのための施策として導入したのが、オープンバッジ制度である。「オープンバッジ」とは、ナレッジやスキルの習得を証明するデジタル認証制度だ。レベル1から5までのコースが用意されており、旭化成グループではレベル1と2をデジタル入門人材、レベル3をデジタル活用人材、レベル4以上をデジタルプロ人材としている。
オープンバッジ制度では、社内eラーニングシステムにオリジナルの学習コンテンツを公開。合格者にオープンバッジを付与する形で進められる。例えばレベル1なら「IT入門」や「AI入門」といった基礎的な知識を学び、レベル2なら「生成AI」や「データサイエンス」などを学ぶといった具合だ。
レベル3で「データ分析入門」や「Python」、「デザイン思考」、「アジャイル開発」などで専門性を高めていき、レベル4では「ローコード・ノーコード開発」や「スクラム実践」などを学ぶ。レベル5ではデータサイエンティスト育成レベルの「デーア分析」や「デジタルマーケティング」「スクラム実践」といったコンテンツが用意されている。
現在、旭化成グループの国内従業員は約2万5000人。そのうち1万6000人がレベル3まで習得済みだという。現在の目標は、全従業員がレベル3まで習得することだ。
人材育成施策の“仕掛け”
では、デジタルプロ人材が充実すると、どのような効果が表れるのか。
「例えばR&D分野でデジタル人材を育成することにより、実験検証の期間を短縮できると考えています。仮に素材を開発するのにこれまでは500回の実験を繰り返す必要があり、3カ月かかっていたとします。これをデータ分析により100回の実験で500回分の予測ができるようになると、期間を1カ月短縮できたりするのです」(石川氏)
このほかにも製造現場のスマートファクトリー化を進め、生産の安定・高度化を図ったり、マーケティング機能の高度化を実現したりといった成果が期待できるという。
こうした人材育成に向けて、同社では多岐にわたる“仕掛け”を実施している。
デジタルプロ人材向けに社長からの激励のメッセージ動画を配信したり、タレントマネジメントシステムに掲載してデジタルプロ人材を全社に向け可視化したりといったのはその一例だ。また、事業固有のデジタル領域におけるプロフェッショナルを把握・認定し、可視化する仕組みを整えるといった取り組みも行っているという。
加えて、デジタル活用人材については工場の休転を利用し、集合型研修を実施して受講者層を拡大するなど、身近なデジタル事例集を公開して学習意欲と活用意識の維持・定着に努めているとのことだ。
さらに、「未来のデジタル人材の会」を始動。損保ジャパンやリコー、キリン、トヨタ自動車といったさまざまな業種の企業とデジタル人材育成に向けた取り組みなどもスタートさせている。
社内だけでなく、社外とも積極的にデジタル人材育成に関する共創を進めている旭化成グループ。同社の取り組みがやがて大きなうねりとなり、将来の日本における課題解決につながることを期待したい。
なお、映画館という場所でこういったセミナーを聴講するのは筆者としても初めての体験だった。映画館ならではの大スクリーンと薄暗い空間は没入感たっぷり。参加者の多くがポップコーンや飲み物を手に講演を楽しむなど、普段のセミナーよりもどこか柔らかい雰囲気だったのが印象的だった。