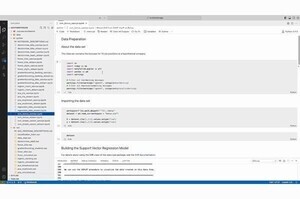ChatGPTの登場により、再び注目を集めることになったAI業界。現在はさまざまなAIサービスが提供されており、AI業界は百花繚乱の状態となりつつある。加えて、AI活用やデータ分析によってDX(デジタルトランスフォーメーション)を進めようという機運が高まっており、企業はAIを使うことが当たり前になりつつある。
しかし、こうした状況に対し、SAS Institute Japan 代表取締役社長 手島主税氏は「AIを正しく理解できていない人が多い。AIを活用するにはリテラシーが必要」と指摘する。そこで同氏に、SASがAIとの付き合い方をまとめたコンセプト「人中心型イノベーション」について聞いた。
生成AIのせいでSASがなくなってしまう!?
2023年5月に現職に就いて以来、手島氏はさまざまな企業の経営層と会話を重ねてきたが、その中で、「日本においてアナリティクスに対するニーズは増えているが、普及はこれから。日本企業がAIとデータを意思決定に活用するには、いくつかステップを踏むことがあると実感した」という。
日本企業がAIとデータを意思決定に活用できるようにするため、SASは人が中心とした意思決定が行う「人中心型イノベーション」というコンセプトを作り出した。
このコンセプトは、実験計画や予測の科学に基づく旧来のAIと生成AIに代表される機械学習を中心とした新しいAIを使いこなして、意思決定を行うことを主旨としている。
手島氏は、AIの現在の状況について、「アルゴリズムのパラダイムシフトが2種類ある。1つは、2010年以降の機械学習に代表される、人に代わって仕事をする世界。金融工学など、SASが得意としてきた分野で、人が予測を立ててデータを使って検証するという統計の一部となる。もう1つはコンピュータが予測を行って人間以上の成果を出せる、生成AIに代表される世界。今、この2つの重なりが増えてきた」と説明する。
例えば、サプライチェーンや気候変動のリスクを管理する際、定量化が必要となるが、2つのAIを組み合わせないと答えが出ない。だから、「2つのAIをうまく使うリテラシーが求められている」と手島氏。
SASは統計解析ソフトに始まり、今ではアナリティクス関連のソリューションを幅広く提供しているが、「生成AIの登場により、SASはなくなってしまうのかと聞かれることがあるが、予測をベースとする旧来のAIのスキルがわからなければ、生成AIに代表される新しいAIの使い方もわからないと見ている。AIを正しく整理できていない人が多い」と、手島氏はいう。
2つのAIを融合して人の意志に基づき決定する
では、2つのAIを融合できるリテラシーとはどのようなものなのだろうか。
手島氏は、「AIをどのような目的でどのように使うのかを決めるのは人。例えば、経営のリスク管理において、何を軸にしてどのパラメータを見るかを選択するのも人。現在、AIを使うことばかり注目を集めており、AIを使うことの本質が忘れられがち。われわれは、意思決定に人が介在することを訴求していきたい」と語る。
一方、「デジタル化が進むことで、意識を働かせなくても選択が可能であり、勝手に物事が進むようになってきた。昔に比べると、決定に意思が反映する比率が低くなっているような印象がある」と、手島氏は指摘する。だからこそ、SASは人が選択するというリテラシーを高めようとしている。
「コンピュータが出した答えについて、もう一度学ばせるのか、どう判定するかなど、人の意識を入れて選択しなければ コンピュータにとって代わられる」と、手島氏は危機感を露にする。AIのネガティブな側面として語られる、「AIが仕事を奪う」世界が現実のものになってしまうかもしれないというわけだ。
そして、手島氏は「SASは、テクノロジーによって、アナリティクスのロジックに感性を入れられる唯一の会社。人の感性も注入できる、それがわれわれの強み」という。
半導体工場でも発生しているデータ活用の問題
手島氏は最近の活動の例として、半導体業界の支援を紹介した。工場の設立が相次いでいる九州にまで足を運んでいるという。半導体企業は新工場に投資しているが、旧工場と並行稼働する際に発生する問題を3つ、手島氏は紹介した。
1つ目の問題は、旧工場は人の感性で作られて運用されてきた一方、新工場はテクノロジーを活用して自動化されていることだ。「自動化されたデータを活用して、どうやって生産性を上げるのかがわからない状態でスタートしている」と手島氏は指摘する。
2つ目の課題は、半導体業界に限ったことではないが、人手不足だ。とにかく、人が集まらないという。
3つ目の課題は、データを基に製造計画を出さなければならないことだ。半導体企業によると、「いろんなAIベンダーが来て、『あれができます』『これができます』といってPoCを実施しているが、予測が当たらない。もはや、「AIより自分たちの感性のほうが予測の角度が高いのでは」という意見になっているそうだ。
そんな思いを抱えている半導体企業の人々に対し、手島氏が、旧来のAIと新しいAIとのかかわり方やデータとの向き合い方について説明すると、「そこまで話してくれるのはSASしかいない」と言われたとのこと。