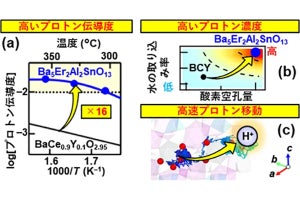名古屋大学(名大)は7月9日、「ウィック」と呼ばれる多孔質体で生じる毛細管現象をポンプの駆動力に利用することで、電力を使用せずに半永久的に熱を輸送できる技術の「ループヒートパイプ技術」を用いて、電力を用いずに10kW以上もの熱を2.5m先まで輸送することに成功したと発表した。
同成果は、名大大学院 工学研究科の長野方星教授、同・渡邉紀志特任准教授、同・上野藍講師、同・Shawn Somers-Neal大学院生らの研究チームによるもの。詳細は、熱および質量移動に関する全般を扱う学術誌「International Journal of Heat and Mass Transfer」に掲載された。
焼却炉の廃熱でプールの水を温水にするなどの施設が全国各地にあるなど、廃熱利用は行われているものの、地球の温暖化を考慮すれば、さらに廃熱利用を増やす必要があり、実際にまだまだ未利用な廃熱が多く存在している。しかし、廃熱源から利用先までの距離が離れている場合が多いため、熱を損失なく運ぶ技術がなければ、有効活用は難しいとのこと。従来の機械式ポンプは電力が必要な上に、顕熱輸送で効率が悪く、機械的な機構の寿命も短いといった問題があり、無電力で高効率に半永久的に熱を輸送する技術が求められていた。
そうした中で注目されているのが、多孔質体のウィックが液を吸収する毛管現象をポンプの動力とする、電力不要の熱輸送デバイス「ループヒートパイプ」。これまで電子機器の冷却などに使われてきたヒートパイプなどと比べ、高いポンプ力を有しているのが優れた点だという。ただし、これまでのところは、人工衛星の電子機器の冷却を対象とした、熱輸送量100W、熱輸送距離1m程度の物が多く研究されてきており、さらに大きなスケールでの利用が求められていた。
そのような背景のもと、適用範囲のさらなる拡大のため、kWクラスの大型のループヒートパイプ、熱輸送距離10mクラスの長距離ループヒートパイプ、モバイルデバイス冷却用の厚さ1mm以下の薄型ループヒートパイプなど、さまざまな研究開発を進めているのが研究チームだ。今回の研究では、ループヒートパイプの性能を上げるため、ウィックで運ばれた液体を効率よく蒸気に変えるために重要な蒸発器内の構造の開発のために赤外域と可視域での顕微計測手法を開発し、実験と数値シミュレーションを通じて、ウィック近傍での液体、蒸気の振る舞いを解明し、熱伝達性能を上げるための蒸発器構造を提案することにしたという。
今回開発されたループヒートパイプは、蒸発器の構造が最適に設計され、また最適な放熱条件が設定されることで、名大で過去に開発された最大のループヒートパイプよりも蒸発器のサイズを18%小型化しつつ、熱伝達特性を4倍以上、熱輸送量を1.6倍以上に向上させることに成功したとする。その結果、最大10kWの排熱を2.5m先まで無電力で輸送することが実現された。
今回の蒸発器は、従来一方向で構成されているグルーブ(蒸発器で生成した蒸気を蒸発器外に排出するための溝)を、3D微細グルーブ構造(グルーブ幅×高さ×ピッチ:1×2×2mm)を蒸発器ケース内側四面に採用することにより、ウィックとグルーブでの冷却性能(蒸発効率)を格段に上げることに成功し、4.5kW熱輸送時には、蒸発熱伝達率9万2000W/(m2K)が達成された。なお、蒸発熱伝達率とは蒸発による冷却性能を表す指標で、単位面積、単位時間、単位温度あたりの伝熱量のことだ。
ウィックはステンレス製のブロック型(W143×L145×H22)が用いられており、ウィックの高さ・コア数・コア径は、ウィック部の有効厚さをパラメータに、ループヒートパイプの性能に関係が深い熱リークと流動圧損が最小になるように決定された。その結果、最大10kWまでの熱輸送が確認されるともに、熱源面積換算した熱流束(伝熱面の冷却性能を表す指標で、単位面積、単位時間あたりの伝熱量のこと)は最大で30W/cm2が達成された。
今回開発された技術は、電気自動車、データセンター、月面探査車などの熱マネージメントの省エネ化に貢献するという。また、工場排熱や住宅における太陽熱利用など、これまで無駄に捨てられていたエネルギーを有効活用することで、カーボンニュートラルの実現にも寄与するとしている。