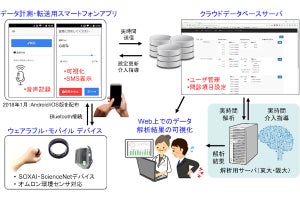富山大学は6月25日、マウスを用いた研究から、睡眠中でも脳は活動を続けて情報を処理し推移的推論の演算を行っていることを見出すと共に、その神経細胞レベルの仕組みを明らかにしたと発表した。
同成果は、富山大 学術研究部医学系 生化学講座の井ノ口馨教授/卓越教授(富山大 アイドリング脳科学研究センター センター長)らの研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。
睡眠中の脳活動は、記憶の定着に重要だ。しかし、より高次の脳機能に関しても睡眠中の脳活動が重要な働きをしているのか、仮にそうだとして睡眠中のどのような神経活動によってそうした高次の情報処理が為されているのかといったことは解明されていなかった。そこで研究チームは今回、マウスを用いる「推移的推論の学習課題」を開発して調べることにしたという。
今回の実験装置では、A>B>C>D>Eという階層性のあるA~Eの5つの部屋が用意された。各学習セッションでは、推移的推論の前提として2つの部屋だけが提示され、たとえばAとBの前提ペアの場合、マウスがたまたま部屋Aを選択して10秒以上留まると、報酬として砂糖水を受け取れるという仕組みだ。そして14日間にわたる学習の後に推論テストが実施され、その際にマウスが経験したことのない新しいペアの部屋BとDが用いられ(Bが正答)、どちらが選択されるのかが調べられた。
テスト1は最後の学習から30分後に、テスト2~4はその後の1日おきに行われた。マウスはテスト1では50%の正答率(チャンスレベル)しか示さなかったが、それ以降のテストでは80%以上の高い正答率(部屋Bを選択)を示し、正しく推論できていることが確認された。その一方で、テスト1の直後に睡眠をはく奪されたマウスでは、テスト2~4でもチャンスレベルの正答しか示せなかったという。
-

推移的推論には睡眠が必要なことがわかった。(A)用いられた5つの部屋。(B)実験の流れ。4つの前提ペア(A>B、B>C、C>D、D>E)の学習後に推論テストが行われた。(C)推論テストでは、新規のペアBとDが初めて提示された。正答率50%がチャンスレベルである。睡眠はく奪グループのマウスは、テスト1~3それぞれの直後の睡眠が阻害された(出所:富山大プレスリリースPDF)
次に、正しい推論に睡眠中の大脳皮質の神経活動が必要かどうか、学習後の睡眠または覚醒期間中に大脳前帯状皮質の神経活動を抑制することで、その影響が調べられた。ノンレム/レム睡眠中の神経活動を抑制されたマウスでは、正しい推論ができなかったとする。その一方で、覚醒時の前帯状皮質の神経活動を抑制しても正しく推論できたという。また、A>Bなどの前提ペアに対する記憶は、抑制の影響を受けなかったとした。つまり、ノンレム/レム睡眠それぞれの脳活動は、過去の経験に基づいて実際には未経験なことを推論する能力に必要だが、覚醒時の脳活動は必要ないことがわかったのである。
-

推論には、学習後の睡眠中の大脳皮質活動が必要と判明した。(A)実験の流れ。テスト1~3それぞれの直後の覚醒時、ノンレム/レム睡眠中における前帯状皮質の神経細胞活動を光照射で阻害。(B)推論に覚醒時の神経活動は不必要、ノンレム/レム睡眠中の神経活動は必須と判明した。(C)前提ペアに対する記憶テスト。いずれの記憶も光照射による神経活動抑制の影響を受けなかった。なお、縦軸のスケールは(B)とは異なる(出所:富山大プレスリリースPDF)
続いて、睡眠中の前帯状皮質の神経活動を促進することで、推論成績を向上させられるのかが調べられた。10日間の不完全な前提ペアの学習を遂行したマウスを用いて、学習後のノンレム/レム睡眠中の前帯状皮質の神経回路が、人為的に活性化された。活性化なしのマウスは正しく推論できなかったが、レム睡眠中に活性化されたマウスはテスト2~4のいずれでも80%以上の高い推論成績を示したという。一方、ノンレム睡眠中の活性化では促進されなかったとした。これらの結果は、ノンレム/レム睡眠中のどちらの神経活動も推論に必須だが、それぞれが異なる機能を果たしていることが示されているとした。
-

レム睡眠中の神経活動を人為的に活性化することで、推論成績を向上可能なことがわかった。(A)実験の流れ。テスト1~3それぞれの直後のノンレム/レム睡眠中の前帯状皮質回路の活動が光照射で活性化された。(B)不完全な前提ペア学習ではマウスは推論できなかったが(光照射なし)、レム睡眠中の光照射による活性化で推論できるようになった(出所:富山大プレスリリースPDF)
そして、それぞれの睡眠の機能の相違を解明するため、前帯状皮質の神経細胞の活動が測定された。B・Dペアの推論テスト2・3において、マウスがBを選択する決断をした時に出現する神経細胞の共活動(推論)パターンの検出が行われ、正答Bの選択直前に現れる場合もあれば、スタート地点からBに向かう途中に現れる場合もあったという。また推論パターンはB・Dペアのテスト時に初めて出現するのではなく、前提ペアの学習終了時から徐々に出現し、特筆すべきはレム睡眠中に強く検出された点とした。つまり、推論の正答はレム睡眠中に脳内で形成されていたのである。なお、推論パターンを構成する神経細胞は、前提ペアに対応する神経細胞とは異なっていたとする。
-

推論の正答は、レム睡眠中に形成されることが解明された。(A・B)テスト2、3で正答する時に、マウスがスタート地点からB、D選択地点(赤星印、A)に移動するまでの間に出現してくる神経活動パターン(推論パターン、B)。(C)推論パターンはレム睡眠中に形成されてくる(出所:富山大プレスリリースPDF)
さらに、推論パターンが脳内でどのように形成されていくのかを知るため、4つの前提ペアそれぞれの学習時に活動した神経細胞グループの間における共活動が調べられた。ノンレム睡眠中に高い共活動が示されたのに対し、覚醒時やレム睡眠中では共活動は低いままだった。異なる記憶に対応する神経細胞間の共活動は、記憶同士を照合し関連づけることが知られている。つまり、ノンレム睡眠は各前提ペア間の関係を照合して全体の階層性を形成していることが考えられるとした。推論パターンを構成する神経細胞は、レム睡眠中に各前提ペアの細胞と高い共活動が示されており、レム睡眠中に脳が全体の階層性からBとDの関係を抽出することで推論していることが示されているとした。
-

ノンレム/レム睡眠中の神経細胞の共活動が重要であることがわかった。(A)学習済みの4つの前提ペアに対応する神経細胞の間での共活動の強さ。ノンレム睡眠中に強く出現してくる。(B)推論パターンを構成する神経細胞は、前提ペアの神経細胞とレム睡眠中に強い共活動を示す(出所:富山大プレスリリースPDF)
以上から、まず前提ペアに関する情報は、お互いが独立して散在する情報として蓄えられ、その後のノンレム睡眠中に、各前提ペアに対応する神経細胞が共活動し、前提ペアの情報を整理して全体の階層性を構築。続いてレム睡眠中には、ノンレム睡眠中に構築された全体の階層性からB>Dの推論知識を導き出すと結論付けられた。レム睡眠中に観察された推論パターンと各前提ペア細胞の間の高い共活動は、前提ペア細胞が新しい神経細胞群をリクルートして推論パターンを創出している過程を表していることが想定されるとした。
今回の研究成果により、今後、潜在意識下で脳がどのような神経活動を行って、覚醒時には実現が困難な情報処理を行っているのかという疑問に実験的にアプローチすることが可能となったとしている。