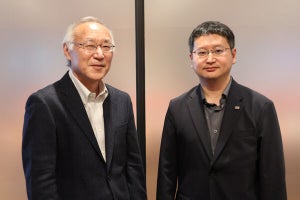フューチャーショップは6月5日、SaaS型ECサイト構築プラットフォーム「futureshop(フューチャーショップ)」において「配送・送料機能」のアップデートを発表した。今年1月に続き、今年2回目のアップデートとなる。アパレルから食品、インテリアなど、幅広いジャンルの導入企業の配送関連のニーズにいち早く対応することで、業務効率化やサービス向上に貢献している。今回の配送・送料機能アップデートの内容や、「futureshop」で引き合いが増えている機能などについて、取締役 セールス・マーケティング部 統括マネージャー 安原貴之氏に聞いた。
<重量で送料計算可能に>
――6月5日にリリースした「配送・送料機能」のアップデートの内容は?
梱包重量による送料を計算できるようにしたのと、温度帯などに応じて同梱配送できるグループを設定できるようにした。
これらの機能によって、購入時に送料を自動計算できない組み合わせの購入などで、これまで店舗が「後から連絡します」と対応していたケースでも、自動で送料の計算や同梱の設定ができるようになった。
「後から連絡します」のパターンだと、手動で計算して、購入者に連絡して了解してもらってから、事業者側で金額を変更し、それから発送するという時間も手間もかかってしまっていた。これが自動化できるのは大きい。
――梱包重量による送料計算機能とは、具体的にどのような機能か?
以前はパターン別送料という機能があり、商品のサイズなどに応じてパターンを決めて送料を設定していただいていた。今回の新機能により、宅配便の送料設定に「重量別」を追加した。商品ごとに設定した梱包重量の合計により送料を計算できるようになった。同じ温度帯の個口ごとに商品重量を合算し、最終的な送料・手数料金額を自動で算出する。
――同梱配送のグループ設定機能の内容は?
同梱可能なグループを設定することで、同梱できない商品を分けて管理できるようになる。同じ温度帯の商品でも、A商品とB商品は同梱できないというパターンがある。例えばA商品は専用ボックスで送る必要があるけど、B商品は通常の梱包で送ることができるといったケースだ。
ほかにもC商品は自社から出荷するが、D商品は産直品で別の場所から出荷されるといったケースもある。このような場合も同梱できないようにグループ分けできる。
近年、導入が加速している食品販売事業者は、特に配送のバリエーションが複雑なケースがある。今年1月にも三温度帯への対応を行い、今回さらに新たな機能を追加したが、まだ足りない部分があると感じている。
例えば常温商品でも冷凍商品と一緒に送ってもよい商品があったり、冷凍商品だけど冷蔵で送っても構わなかったりと、さまざまケースがある。これらのケースには、まだ対応できていないが、いずれ対応しないといけないと考えている。
<配達日表示機能が好評>
――今年1月には、三温度帯以外にも、宅配便やメール便など複数の配送サービスに対応できるようにしたり、「商品詳細」ページで最短お届け日を表示できるようするなど、配送関連の新機能をリリースしている。これらの機能の反響は?
いずれの機能も好評だが、特に「最短お届け日」を表示できることを知って、問い合わせしてくる事業者が多い。
今回のアップデートでより細かい配送・送料の設定に対応できるようになった。カスタマイズなどでこうした細かい設定に対応できるサービスはあるが、SaaS型のカートでここまで細かく対応できるサービスはないと思う。
実際、他社のカートも利用している事業者も参加したセミナーで実施したアンケートでは、他社のカートよりも配送機能が充実しているという声をいただいている。
<オムニチャネルの引き合い拡大>
――配送関連以外の機能で好評な機能は?
以前から提供しているオムニチャネル対応プラットフォーム「futureshop omni‐channel(フューチャーショップオムニチャネル)」の問い合わせが増えている。以前は、もともと「futureshop」を導入していて、実店舗も持っている事業者が「futureshop omni‐channel」に切り替えるケースが多かった。今年に入ってからは「futureshop」以外のECプラットフォームを活用している事業者が、「futureshop omni‐channel」に乗り換えて、実店舗とECの連携を進めるケースが増えている。
オムニチャネルプランで価格をオープンにしているソリューションは少なく、手軽に導入できる点が評価されていると思う。カスタマイズでオムニチャネル対応するソリューションよりは安価に導入でき、当社よりも安価にオムニチャネル化できるというソリューションは機能的にだいぶ制限されることが多いようだ。
より安価なソリューションの場合、会員データの統合とポイントの共通化はできても、会員ランクの自動設定や通常購入以外のポイント付与などロイヤリティプログラムを柔軟に構築することができないケースがある。オムニチャネルの目的は、システム的な統合だけではなく、その基盤の上でお客さまの体験を高めることにある。具体的な施策を打とうと考えたときに、機能的な制限でできなければ意味がない。
オムニチャネルに関連して、今年2月にリリースしたスマホアプリを構築できるオプション機能「future M‐App」の問い合わせが増えている。スマホアプリを核にオムニチャネルのサービスを提供したい事業者は多いようだ。
<制作支援機能も強化>
――ほかにもアップデートしている機能はあるのか?
制作支援機能をアップデートしている。ECサイトの要素一つ一つを「パーツ」単位に分割し、システム提供分と独自に作成できるパーツを組み合わせてECサイトを構築できるCMS(コンテンツマネジメントシステム)機能「コマースクリエイター」は、2018年9月に提供してから6年弱が経過している。
これまでは「コマースクリエイター」を使っていない店舗が新たに導入するケースがほとんどだった。ただ、提供開始から時間が経ったことで、「コマースクリエイター」を利用している店舗が、その中でリニューアルするケースが出てきた。
そのリニューアルの際に制作会社がやりづらい部分があった。制作会社の手間がかかる仕組みだと、その工数がコストとなり、導入店舗への負担にもなる。その課題に対応するため、今回はパーツの情報を一括でダウンロードできる機能を提供した。今後も制作支援機能はさらにアップデートしていく予定だ。
■「futureshop」
https://www.future-shop.jp/