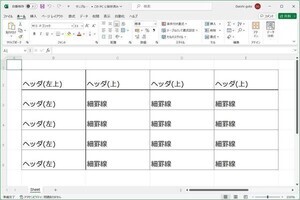統合コマースプラットフォーム「ecforce(イーシーフォース)」を提供するSUPER STUDIOは、D2Cの成長を支援する企業から、OMOやデータ活用を支援できる企業に進化している。自らブランドを展開したり、実店舗を開設したりすることで、机上の理論ではなく、実践で得た知見を基に具体的な仕組み作りから施策まで提案できる体制を構築した。支援先の商品カテゴリーはコスメ、健康食品に加えて食品、アパレルなどへ広がり、大手メーカーや全国チェーンなど企業規模も拡大している。OMOやデータ活用の支援体制の進化について、取締役COO 花岡宏明氏と執行役員 大谷元輝氏に聞いた。
<商材・支援領域が拡大>
――「ecforce」の導入企業の状況は?
花岡:2024年4月末時点で導入実績は1333ショップとなり、非常に伸びている。カルビーや再春館製薬所、キューサイ、ワタミ(宅食)などエンタープライズ企業や業界の大手企業に採用されるケースが増え、導入企業の規模も拡大している。
大谷:この1年間でアパレルや食品を取り扱う企業からの問い合わせや導入が増えた。これまではコスメや健康食品が中心だったが、月によっては食品事業者などの方が導入企業数は多かったり、以前はあまり導入実績のなかったアパレル事業者の導入が目立つようになったりしている。
花岡:アパレルに関しては自社で「MEQRI(メクリ)」というストリートアパレルブランドを展開しており、その実績を持っていることが好影響を与えている。アパレルブランドとしてどう売り上げを伸ばすのかを研究し、マーケティングやEC運営のノウハウを持っていることが大きい。
――アパレルをはじめ、多くの事業者がオムニチャネルやOMOの取り組みに注力している。そのノウハウもあるのか?
花岡:「THE [ ] STORE(ザ・ストア)」という実店舗を持っており、自社ブランドでもオフラインを活用したOMOに取り組んでいる。実際に商談している大手企業にも具体的な施策を提案できている。
大手企業でも実店舗とECのデータが分断されていたり、売り上げのKPI設計がチャネルで分かれていたりするケースが多い。当社のOMOソリューションであれば、それぞれのチャネルのデータを統合・分析し、その上で店頭の最適なKPIを設計し、店舗オペレーションなども含め、具体的な施策にどう落とし込むかを提案できる。
外資の大手コンサルティング会社が支援してきたようなチャネルを超えた事業提案を、当社ならより具体的な形で支援できる点が、大手企業にも注目いただけている。
――コスメや健康食品の導入企業も多いと思うが、市場環境は悪化しているのか?
花岡:足元でそこまで環境が悪化しているわけではないが、デジタル広告の単価高騰の影響は出ている。実際にデジタルのみで勝ち抜く難易度は上がってきていると思う。
そのような変化を受けて、オフラインに販売チャネルを広げるなど、総合的に戦う企業が増えている。そこでもOMOやオフライン活用のノウハウが生きている。
<実行力あるOMO支援>
――オフラインの課題を抱えている企業が多いのか?
花岡:ECシステムの老朽化により、やりたいことが実現できないという相談も多い。話を聞くとパッケージやフルスクラッチで構築されており、ECサイトのデザインを少し変えるだけでも3カ月などと時間がかかったり、決済手段を1つ足すだけでも大きなコストと時間がかかったりしている。その環境だと変化の速いECのトレンドに追いつけない。
当社はECのチャネルを最適化するサービスとして成長してきた。SaaSの強みを生かし、最新の機能を活用する支援ができる。
ECの課題解決に加えて、チャネルが多角化する中で、オンラインもオフラインも合わせて総合的に戦える環境を作りたいという相談も増えている。
大手企業はトレンドに敏感なので、DXの流れを受けて、データを活用するためのソリューションを導入したり、コンサルティング会社を活用したりしている。しかし、実際にデータを活用できているかを聞くと、上手に活用できている企業は少ない。戦略を考える会社と仕組みを提供する会社が別々だと、一見、理想的なビジョンは描けても、具体的な施策に落とし込めないケースが多いようだ。
当社は自社のソリューションを駆使してデータをただ集めるだけではなく、そのデータを使って、打つべき施策を知っている。その施策を実行するためにデータをどのように集めて、どう活用するのかというところを、仕組みだけではなく、ノウハウまで提供できる。
――具体的な施策とはどういったものなのか?
大谷:ブランドの課題によってもとるべき施策は変わる。例えば顧客データを取った後にCRMで引き上げるということを前提に、店頭で売ることに終始しない戦略もある。
LINEの友だち登録を促すためにお試し価格の商品を販売し、成果を上げた事例もある。SNSのUGCを獲得するオペレーションを組むようなケースもある。
――すでに店舗網を持ち、さまざまなシステムを導入している企業の支援も可能なのか?
花岡:そのようなケースで実際に支援している事例がある。OMOの課題を持っている全国に店舗展開をしている企業にコンサルティングを行っている。そういったケースでは、施策の提案は行うが、ECのカートシステムを「ecforceに変えましょう」という提案はしない。
例えば店頭のオペレーションを最適化するために、特定の店舗だけをロイヤル顧客がよりリッチな体験ができる場にする提案を行う。その際にカートシステムは既存のものを活用し、必要に応じて予約システム「ecforce check」を提供して、そのデータを基幹システムとつなぐこともできる。予約した顧客に再来店を促すために、MA(マーケティングオートメーション)の「ecforce ma」やBI(ビジネスインテリジェンス)の「ecforce bi」を提供して、データソリューションを支援したりすることも可能だ。
最終的にカートも「ecforce」に変えてもらうと、大きなメリットを享受していただける自信はあるが、必ずしもそこは変えずに支援させていただくこともできる。
<データ支援をより強化>
――2022年から推進している「次世代EC構想」の進捗は?
花岡:「次世代EC構想」の先に、現在進めている「統合コマースプラットフォーム」があるというイメージだ。
昨年10月、「ecforce」は「ECプラットフォーム」から「統合コマースプラットフォーム」に変わると発表した。「EC」から「コマース」に変わったのは、ECだけに閉じることなく、コマース全体に対応するというメッセージだ。具体的にはオフラインとデータ活用領域を攻める。
OMOといってもただPOS連携したり、会員データを統合したりするだけではなく、オフラインで会員データを取るための施策や、会員化した後のリピート購入をどう作るかまで支援していく。
「統合」を足したのは、高度な専門知識や専門人材がいなくてもデータを活用できる仕組みを提供するという意思表示だ。分断されたシステムでは、データを活用するために、データの連携や整形をする必要があり、どうしてもエンジニアリングやデータサイエンティストなどの専門知識が必要になる。この課題を解決するために、専門性をできる限り排除した統合したソリューションを提供し、マーケターがすぐに使える仕組みにする。
販売チャネルを多角化してもデータを一元化してビジネスに使えるようにするというのが、「次世代EC構想」が目指したものであり、その流れを汲んだ統合コマースプラットフォームとしてもプロダクトのラインアップがそろってきた。
――今後、新たに提供するプロダクトの計画や、強化するサービスは?
花岡:POSソリューションも一般リリースに向けて準備している。実際、「THE [ ] STORE」ではPOSを活用しており、ブラッシュアップを重ねている。
当社の強みになっているデータソリューション周りのサービスはさらに拡充していく。MAやBIが好評だが、他のプロダクトもローンチする計画だ。より幅広いデータを統合できたり、データの加工を自由にできたりするプロダクトも提供する予定だ。
データソリューションは「ecforce」を利用していなくても使えるものにしていく想定。データ活用やOMOの仕組み作りから施策まで支援できるコンサルティングサービスの提供も強化していく
■「ecforce」
https://ec-force.com/