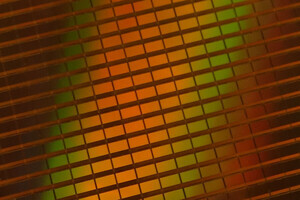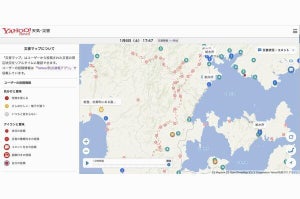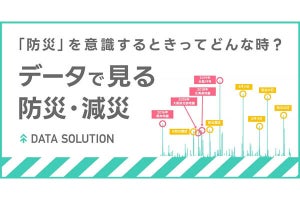能登半島地震の発生から3カ月以上が経った。石川県内の被災地では復旧への取り組みが進められているが、7千戸以上で断水が続いている状況だ。犠牲者は4月2日時点で245人となった。
一方で、通信インフラにも甚大な被害を及ぼしている。ピーク時の1月3~4日には、850以上もの基地局が電波を送受信できなくなった。電源喪失による基地局の停止や、基地局から通信を届けるための伝送路が地震によって途切れてしまったことが原因だ。
「船上基地局」や「スターリンク」各社の応急復旧
通信事業者各社は迅速な対応を進めている。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルの4社は、地震発生17日後にあたる1月18日に応急復旧の工事がおおむね完了。そして、ソフトバンクは2月27日に、NTTドコモは3月22日に被災地のほぼ全域で携帯電話のサービスが利用できるようになったと発表した。
応急復旧には車両から電波を飛ばす「車載型基地局」などが活用された。NTTドコモとKDDIは共同で、船舶上に携帯電話基地局の設備を設置した「船上基地局」の運用を日本で初めて実施。また、ソフトバンクはドローンを使って通信エリアを確保する取り組みも行った。ドローンを上空に停留飛行させ、半径数キロメートルのサービスエリアを確保した。
また、KDDIとソフトバンクは両社が提携する米スペースXが手掛ける衛星通信サービス「Starlink(スターリンク)」を活用。スターリンクの受信アンテナ約700台を各地の避難所などに無償で提供し、被災者のインターネット通信を実現させた。スターリンクは高度550キロ程度の低軌道上を回る5000機以上の小型の人工衛星を使い、宇宙からのインターネット接続を実現する。道路も壊れて基地局にたどり着けない状況の中、一役買った技術だという。
KDDIの執行役員常務 技術統括本部 副統括本部長兼エンジニアリング推進本部長の山本弘和氏は、1月に開いた共同記者会見で「静止衛星を用いた基地局よりスループット(単位時間あたりに処理できるデータ量)が高く、かつ衛星の捕捉も短い時間でできる」とスターリンクの特徴を強調した。
仙台市「ドローン」で大津波警報を発令
2011年3月11日に発生した東日本大震災も通信インフラに甚大な被害を及ぼした。地震や津波の影響により、通信ビル内の設備、地下ケーブル、管路、架空ケーブル、基地局、商用電源などが被害を受けた。
固定通信は約190万回線、移動通信は約2万9千局、地上テレビ放送の中継局については120か所で停波する状況に。被災地では音声通信のトラフィックが増大し、通信規制が実施された。
東日本大震災の津波により沿岸部が甚大な被害を受けた仙台市は、ドローンを活用した防災・減災に取り組んでいる。2019年11月には、フィンランドの通信機器大手のノキア日本法人と連携し、プライベートLTE(Long Term Evolution)網上でのドローンの津波避難広報の飛行実証実験を世界で初めて実施した。
同実証実験では、仙台市沿岸部での大津波警報発令を想定し、仙台市宮城野区の沿岸にプライベートLTEネットワークを構築。そしてノキアのドローンに搭載したスピーカーから録音済み音声やリアルタイム音声データを配信した。またHDカメラ、サーマルカメラにて、ドローンからのHD映像やサーマルカメラ映像を利用した上空からのモニタリングも実施した。
具体的には、沿岸部にいる要避難者にドローンスピーカーを通して大津波警報の発令を告知。また、津波到達状況や沿岸部の様子をドローンカメラ映像で監視したり、逃げ遅れた人々を避難場所へドローンスピーカーからアナウンスして誘導し、避難する様子を上空からドローンカメラで監視したり、災害時の過酷な避難誘導活動を想定した実験を行った。
「あの日を教訓に」救援者の2次災害防ぐ
東日本大震災の津波では、避難する側と呼びかける側双方に「過小評価」が存在していたという。仙台市においても、地震が起こった直後に津波が来るかどうかを沿岸部まで見に行った人が結構いたといい、また、避難を呼びかけに行った市役所の職員も津波から逃げ遅れてしまった。
「津波避難広報を迅速に、そして、救援者が2次災害のリスクを負うことなく、防災・減災に取り組めるようにする。過去の教訓をもとに、より強靭な地域づくりにつなげている」と、ノキア日本法人のノキアソリューションズ&ネットワークスの柳橋達也CTO(最高技術責任者)は話す。
通信事業者やネットワーク機器提供事業者だけでなく、個人レベルで行える通信インフラの防災もある。
柳橋氏は「特定の通信キャリアに依存せず、複数の通信サービスに何らかの形でアクセスできる環境を作っておくことは重要だ。防災だけでなく、バックアップとしての可用性を高めることにもつながる」と提言している。