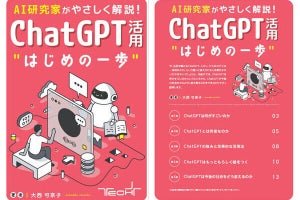日本経済新聞社と金融庁は3月5日~8日、FinTechをテーマにした年次カンファレンス「FIN/SUM2024」を開催した。
初日に行われた金融庁パネルでは、日本マイクロソフト 代表取締役社長 津坂美樹氏、東京大学大学院 工学系研究科 教授 松尾豊氏、セブン銀行 代表取締役社長 松橋正明氏、金融庁 総合政策局 審議官 柳瀬護氏らが登壇。金融データ活用推進協会 代表理事/デジタル庁 プロジェクトマネージャー 岡田拓郎氏がモデレーターを務め、「AIが描く金融の未来:リスクを超えて」をテーマにディスカッションが繰り広げられた。
金融業界における生成AIの「可能性」と「課題」
パネルディスカッションでは、3つのテーマが用意された。最初のテーマは「生成AIの金融セクターにおける活用可能性と課題」だ。政府の「AI戦略会議」で座長を務め、取り組みをリードする松尾氏は「生成AIは社会全体に影響を与えるものであり、見えているのはまだごく一部」だと語る。今後、技術の進化に伴い、さまざまなかたちでソフトウエアに組み込まれ、日々の業務や生活の中に入ってくるという。
「特に金融は影響が大きい産業の1つだと思っています。かなり業務の効率化もできるし、付加価値も作り出せるので潜在的なインパクトは相当大きいはずです」(松尾氏)
では、当の金融機関は生成AIについてどのように考えているのだろうか。バトンを渡された松橋氏は、「攻めと守りの両面で取り組みを進めている」と説明する。
「(生成AI活用の目的として)一番やりたいのは収入への貢献です。まだ今日はお話できるフェーズにはありませんが、松尾先生のご期待にも沿えるようなかたちで作っていきたいと考えています」(松橋氏)
生成AI活用に関しては、自社独自の環境を構築して業務に組み込むパターンと、日常作業の効率化に既存のサービスを使うパターンで使い分けているという。業務効率化に関しては、コールセンター応対やコード生成での本番実装に向けた動きが進む。
もう一つ紹介されたのは、ATMにおける問い合わせ対応の取り組みである。「ATMの問い合わせはATMで返す」ことを目指し、接客画面を経由した音声での問い合わせをフックに、応対マニュアルを参照した上で回答を音声で返す。音声変換や回答生成の機能はAzureOpen AIによって構築されており、回答の精度と性能の向上に向け改善を継続中だ。
松橋氏曰く、生成AIを使っていかに新しい発想ができるかが最も重要であり、利用する人間側も生成AIを使う前提の思考回路に変革していく必要があるという。だが、「自分自身、まだ変われていない」ため、とにかく使ってみようと毎日、生成AIを使った画像生成やビデオ編集に挑戦していると話した。
他方、金融庁でイノベーション推進とリスク面の両サイドを所管する柳瀬氏は、「『新しいことをやらないリスク』をきちんと評価できるようにする方法を考えていかなければならない」と語る。
「リスクを考えると、最初はスモールスタートで取り組むことになると思いますが、そこで得た知見をどうやって共有しながら進めていくのかが非常に重要だと思います。そうした“場”を民間でつくっていただくことも重要ですし、それに対して金融庁としても何かできないかということを日々考えています」(柳瀬氏)
柳瀬氏の話を受け、津坂氏も「日本では石橋を叩いて叩いて渡らない。そして渡らないリスクは相当ある」と指摘する。生成AIに対する企業の姿勢はさまざまであり、積極的に活用を進めているところもあれば、現時点でまだ、取り組むかどうかを迷っている企業もあるはずだ。
「生成AIの利用に関しては、まずは社内で使う、その次は業務プロセス、そしてお客さまへという3段階のステップがあると思います。少なくとも今現在、まず自分が使うということをしていないと、本当に乗り遅れるリスクはあるでしょう」(津坂氏)
潜在的なリスクとリスク軽減に向けた取り組み
慎重になりすぎるあまり生成AIを「使わないリスク」への警鐘が鳴らされたが、もちろん、活用していくにあたっても考慮するべきリスクはある。
「金融規制監督当局として、リスクのことを忘れるわけにはいかない」と強調するのは柳瀬氏だ。同氏は、これまでにFSB(金融安定理事会)で行われてきたAI/MLに関する国際的議論を紹介。その上で、生成AIを含むAIに関する国際金融規制の議論は年内に進展する見込みだと説明した。
こうしたリスクへの配慮はもちろん不可欠だが、リスクにおびえすぎて思考を止めてしまうのも問題だ。松尾氏は、「日本はどんどん生成AIを使って自分たちの事業を進めていけばいい」と鼓舞する。
「例えば金融で言うと、法律面に重きを置いたLLMなどは自国の中でいろいろ考えないといけないのでやりようがあると思います。また歴史的に見ても、何かすごい技術が登場して逆転したことはあまりありません。むしろすごいアプリケーションが出てきて、そこから技術への投資が起こって、より強固な強みになっていくっていうのはあると思います。そういう意味でも、気にせず、いろんな面でどんどん進めていけばいいんじゃないかと思います」(松尾氏)
今後の展望 - 他のステークホルダーへの期待と注文
今回、金融業界と生成AIの“今”に最前線で向き合う産官学の有識者が集結したわけだが、それぞれの目線から、他のステークホルダーに今後、どのような動きを期待しているのだろうか。パネル最後のテーマとして、各人がお互いに寄せる期待が語られた。
一言に「生成AIを活用する」と言っても、具体的に何に活用すれば大きな効果が得られるのかは試してみないことにはわからない。手探りで進めなければならないため、特に規模の小さい金融機関などでは「まず使ってみる」というところが最初のハードルになるだろう。
だが、ディスカッションでも上がったように「チャレンジしないこと」にはリスクが伴う。産官学が業界を超えてつながり、ナレッジを共有することでそうした“壁”を乗り越え、さらなる発展が可能になるのではないか。
金融業界は、内部の制度が厳密に整えられているが故に、保守的な側面があることは否めない。だが、「変わらないといけないという意識はどんどん高まっていると思う」と松尾氏は言う。
「危機感を持って(変化の)スピードを上げていってほしいと思いますし、もう始めているところは具体的な業績に繋げていくと、世の中の見え方が変わってくると思います。もうやらなきゃ負けだというのがはっきりしてくるはずなので、ぜひそこまで進めていっていただきたいと思います」(松尾氏)