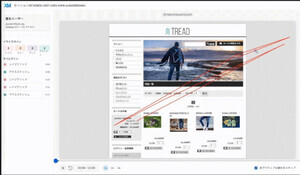クアルトリクスは3月5日、ビジネス戦略発表会を開催した。同日、 2024年の従業員エクスペリエンス(EX)と消費者エクスペリエンス(CX)に関する最新調査結果も発表、その分析結果の紹介も行われた。
2023年のハイライト
2024年度のビジネス戦略は、 カントリーマネージャーの熊代悟氏が説明を行った。同氏は、2023年の最大のハイライトとして、6月に完了したSilver Lake/CPP Investmentによる買収を挙げた。
この買収により、これまでSAPグループとして上場していたが、プライベートカンパニーになった。そのため、売上情報の公開は控えるが、「堅調に 顧客は増えており、グローバルで2万社を超え、日本は500社に達している」と、熊代氏は語った。
SAPとの資本関係は解消されたが、戦略的パートナーとしての関係は継続しているとのことだ。
2024年の活動計画
熊代氏は、2024年の活動計画の柱として、以下を紹介した。
- XMOS2の新機能を日本市場に向け展開
- 顧客のXM(エクスペリエント・マネジメント)成熟モデル向上の支援サービス強化
- 国内におけるパートナーシップの強化
XMOS2は生成AIを実装している次世代のXMオペレーティングシステムで、昨年8月に発表された。熊代氏は、XMOS2について、「独自のLLMと機械学習のノウハウに市場に出ているものを組み合わせて強化し、XMプラットフォームに組み込む。われわれはどこよりも感情データを多く保持しており、XMのために先進的なAIを提供する」と述べた。
また、熊代氏は、「人と人とのつながりをより高めること」「感動・共感できるエクスペリエンスを生み出すこと」「業務効率の改善・向上」のために、AIを提供していくと語った。
2024年には、アンケートデータ以外の間接的フィードバック収集・分析のリリース、日本語自然言語解析(NLP)機能の強化、VTT(Voice to Text)の日本語版のリリースが計画されている。
熊代氏は「これまで日本市場では、明示的なフィードバックに関する機能を提供してきたが、今年は間接的なフィードバックに関する機能を提供する。これにより、これまで対象としていなかったエクスペリエンスのデータを取得できるようになる」と説明した。
また、XMを実践するにあたっては、これまでのデータの見方を変える必要があるとして、昨年度はアドバイスする人を増やし、アドバイザリーサービスを強化したという。
今年も引き続き、アドバイザリーサービスを強化し、パートナーシップもアドバイザリー分野で協業を拡張していく構えだ。
日本の従業員エクスペリエンスの現状:AI活用に後ろ向き
「2024年従業員エクスペリエンストレンドレポート」の分析結果については、EX ソリューションストラテジー マネージャー 東田真樹氏が説明を行った。同調査は日本国内の回答者2,002名のインサイトを抽出したもの。
東田氏は、同調査のグローバルのトレンドとして、以下の5点を挙げた。これらの中から、日本企業が注目すべきトレンドは「AI活用」「現場従業員対応」「出勤制度」であるとして、それぞれのポイントを紹介した。
AI活用
グローバルでは、エンゲージメントが高い従業員ほど、AI活用に対し寛容的であるという結果が出ている。日本でもその傾向はみられるが、グローバルに比べて、AI活用に対し否定的であることもわかっている。
中でも、人事考課や採用面接など、評価に関わる業務にAIを活用することに対し、拒否感が強くなっている。その背景について、東田氏は「AIの活用が一歩間違えば従業員の不利益になると思われている」との見解を示した。そのため、従業員の納得感を高め。効果を出し、エンゲージマネジメントを刷新する必要があるという。
現場従業員対応
エンゲージメントの調査の後に前向きな変化を期待できると答えた現場の最前線に立つ従業員はその他の従業員よりも13%低いという結果が出ている。
東田氏は、「産業構造が変わり、企業のビジネスがモノづくりからコトづくりに代わる中、顧客エクスピリエンスの向上に現場従業員は不可欠」として、企業が現場従業員のエンゲージメントを高めることを重視すべきとの見方を示した。
出勤制度
コロナ禍を経て、リモートワークが定着してきたが、企業によって完全出社、ハイブリッドワーク、完全リモートワークと、出勤制度はまちまちの状況にある。
エンゲージメント、継続勤務意向、インクルージョン、ウェルビーイングを3つの出勤形態ごとに分析したところ、すべての項目でハイブリッドワークの社員の値が高いことが明らかになった。
こうした状況を踏まえ、東田氏は3つの項目に対し以下の提言を示した。
悪い顧客体験(CX)による損失、日本では年間7.6兆円
「2024年消費者トレンドレポート」については、CX ソリューション ストラテジー シニアディレクター 久崎智子氏が説明を行った。同調査は26の国・地域を対象に実施、2万8000の回答を得ている。うち、日本の回答者は1200人。
同調査より、悪い顧客体験(CX)により失うリスクがある金額は3.7兆ドル、約555兆円であることがわかった。久崎氏は、顧客サービスの体験の良しあしは期待と現実にギャップがあることが起因していると指摘した。
消費者の購入意思に与えるインパクトは商品やサービスの質が最も高いが、これに顧客サービス、低価格が続いている。これより、久崎氏は「商品やサービスの質、価格は会社が担うべきことだが、顧客サービスは現場の従業員が提供するものであり、会社と現場が改善することで相乗効果を狙うべき」と説明した。
また、日本だけの分析結果として、悪い顧客体験(CX)により失うリスクがある金額が520億ドル、約7.6兆円であることが示された。日本の顧客体験のランキングにおいては、財物保険会社、携帯電話、病院・診療所、生命保険会社が悪い体験に挙がっている。これらを改善する手立てとして、久崎氏は、体験情報を取得する方法を拡大することを挙げた。
こうした状況を踏まえ、久崎氏は、CX戦略立案とCXアクションプランのポイントとして、以下を示した。