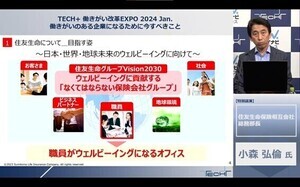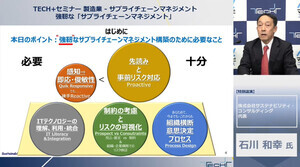丸井グループは、Well-beingを経営目的とし、働きがいを高めるために企業文化の変革に取り組んでいる。2005年からは「企業文化1.0」として主体性を高く持つための「手挙げの文化」への変革、そして2023年からは「企業文化2.0」となる「挑戦と創造の文化」への変革を推進中だ。
1月22日~25日に開催された「TECH+働きがい改革 EXPO 2024 Jan. 働きがいのある企業になるために今すべきこと」に、同社 取締役上席執行役員 Chief Well-being Officerで、専属産業医でもある小島玲子氏が登壇。企業文化をどのように変革し、その結果どのような効果が出ているのかを紹介したうえで、Well-being経営実現のために考えるべきことについて解説した。
主体性の高い企業文化と、社員以外も対象としたWell-being経営を目指す
講演冒頭で小島氏は、同社が「人の成長=企業の成長」という理念を持って企業文化1.0の取り組みを進めてきたことを紹介した。その中で重視したのは、自律的で主体的な企業文化に変革すること、そして全てのステークホルダーを対象にしたWell-being経営を実現することだという。
企業文化については強制ではなく自主性、上意下達ではなく支援を目指し、そのために手挙げの文化の浸透に努めてきた。また2015年には「すべての人が『しあわせ』を感じられるインクルーシブな社会を共に創る」という企業ミッション設定。この「すべての人」とは、顧客、取引先、社員、株主、投資家、地域・社会、そして将来世代の6つのステークホルダーを指す。若い世代だけでなくまだ生まれていない将来の世代も対象にしているところが、同社のWell-being経営の大きな特徴だ。
2021年からの5カ年中期経営計画では、サステナビリティとWell-beingを経営目的として定め、ここでは社会貢献につながる事業を通じて財務的価値を生み出すことを目標とした。
それが実現した事業の例として、「自分が買い物を楽しむこと」と「誰かを応援して社会に貢献すること」を両立させる「ヘラルボニーカード」がある。ヘラルボニー社との共創により、カード利用額の0.1パーセントが知的障害を持つアーティストの支援に使われる。また社会貢献と個人の資産形成を両立する「応援投資」もある。これは、ブロックチェーンを活用してカード会員にデジタル債を発行し、途上国や新興国の就労支援や新規事業のための融資に役立てるものだ。
「このように本業と社会貢献を融合したかたちで、お金の使い方の選択肢を提供する新たなサービスが数多く生まれています」(小島氏)
経営推進会議の出席者を公募したところから始まった“手挙げ”
企業文化1.0への変革のきっかけは、同社 代表取締役社長の青井浩氏が「管理職以上が参加する経営推進会議の雰囲気を改善したいと思った」ことだったと小島氏は振り返る。会議に活気がないのは、「義務的に出席しているだけで主体性がないからではないか」と考え、全社員を対象に出席希望者を公募することにした。これが手挙げの始まりとなった。
経営推進会議は毎月1回開催されるが、毎回約1000名が出席したい理由を書いた作文を提出して応募し、その中から300名の出席者が選ばれている。出席者はみな事前に勉強をして作文を書いた社員ばかりなので、当然ながら会議には活気が生まれていく。この結果を受け、全社横断のプロジェクトや外部スクールへの派遣など、あらゆる場面で手挙げ方式を採用しているそうだ。
「(会議参加者の)年代や性別の多様性も広くなりました。やらされるものではなく、自ら『出たい』と参加する会議はこんなにも活気が生まれることがわかりました。そのため、社内においてあらゆる文化で手挙げ方式を採用しています」(小島氏)
健康経営も手挙げ方式のプロジェクトで推進
小島氏が担当する健康経営の分野でも手挙げ方式を採用している。これは「全社横断Well-beingプロジェクト」と呼ばれるもので、やはり全社員を対象に作文を審査する方式でメンバーを募集した。
プロジェクトは毎月1~2回、就業時間中の10時から18時まで実施されており、第1期ではビジョンの策定、第2期で職場への波及、第3期では他社との共創、第4期にはコロナ禍の地域社会を幸せにすること、そして第5期では本業を通じた社会課題の解決に主眼を置いた取り組みを行ってきた。
例えば第5期には、働く女性のWell-beingを高める取り組みがいくつも行われた。女性の健康をサポートするテクノロジーであるフェムテックのテナントの誘致、他社と協働での女性の健康オンラインセミナーの開催、Z世代の企業家とのインスタグラムでのライブセッションといった取り組みはどれも、企画から実践まで、プロジェクトメンバーが自発的に行ったそうだ。
また、「丸井グループのミッションが自分の人生の目標と重なっていたから入社した」と話す入社2年目の社員を中心としたプロジェクトチームもある。ここで開発されたのが、企業ミッションと個人の価値観の重なり合いを言語化するワークショップだ。自分が大切にしている価値観を共有し、仕事と自分のストーリーの重なりを言語化することで、自分の思いの実現のために仕事をする意味を見つけるワークショップとなっている。実際、ワークショップによって、自分の仕事を重要なものと感じられるようになった社員の割合が着実に増加していることがわかったため、現在は全社に展開しているという。
このように手挙げを中心とした取り組みで自主性を高めてきた結果、「選び選ばれる関係」の基盤としての企業文化もでき、数値にもその変化が表れるようになってきた。例えば、離職率は大幅に低下、社員のWell-being指標も大幅に拡大していると小島氏は話した。「自分が職場で尊重されていると感じている」社員は2012年からの10年間で28%から66%に増え、「自分の強みを活かしてチャレンジしている」社員の割合も38%から52%と半数以上にまで増えた。ただし、新たなサービスをこれからも生み出すには、チャレンジしている社員の割合がまだ少ない。次の課題として、失敗を恐れず挑戦する、創造性の高い文化を目指すことにした。それが企業文化2.0への変革だ。
挑戦を奨励する仕組み、挑戦する場をつくる
企業文化2.0では、失敗を許容して挑戦を奨励することで創造性を高め、社会課題解決企業になると同時に収益も両立させることを目指している。そこで、行動KPIとして「打席数」を設定した。イニシアチブやプロジェクトへの参画などの「打席」に累計打席に5000回立つことを目標として挑戦を奨励していくという。
社会課題解決企業への進化には、仕事を通じて「フロー」を体験できる組織になることが必要だという考えから、フローを測るKPIも設定した。フローとは、心理学者のミハイ・チクセントミハイ氏が提唱する、「自分でやりたいことに没頭することで高い充足感を得られ、創造力が全開になり、高いパフォーマンスを実現できる」という概念だ。
「一人一人が主体性を持って行動し、社員自身が幸せで充実感がある組織をつくることをキーワードに掲げています」(小島氏)
そこでストレスチェックの調査から「挑戦」と「技能や知識の活用」の2項目をピックアップした。その結果、両方の数値が高くなっていればフロー状態に入りやすくなることがわかった。さらに、ワークエンゲージメントの要素も加味して分析すると、技能や技能を活用していても、挑戦の度合いが低ければワークエンゲージメントが低い傾向にあることが判明した。つまり、最も重要なのが挑戦であることがわかったのだ。そこで、社内にさまざまな挑戦の場をつくることにしたと小島氏は説明する。
例えば、社内起業家コミュニティやコロナ禍以降の働き方など、10以上のテーマのイニシアチブを設けたのもその1つだ。これらは従来の縦割り組織ではなく部門横断型で、社内副業的に活動することでより挑戦しやすい体制を整えている。
また、事業につながるようなアプリを新規開発し、社内でコンクールを行う「社内版アプリ甲子園」と呼ばれる取り組みも始めた。これは今後、生成AI等も活用したDXコンクールへと進化させていく予定だ。
最後に小島氏は「人的資本経営やWell-being経営、健康経営はいずれも、それが企業のミッション。つまり経営を通じて実現したい目的や価値創造につながる文脈だからこそ浸透していく」と述べた。
事業戦略に沿った人材戦略を行うのが一般的だが、同社グループはその逆だ。
「丸井グループでは、企業文化の変革、組織・人材戦略から新たなサービスや事業を生み出しています。Well-being経営や健康経営は、企業文化の変革につながる取組みなのです」(小島氏)