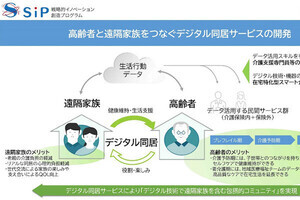離れて暮らす高齢の親--。特に中高年の方にとって、気にかかる存在ではないだろうか。中でも両親のどちらかが先に亡くなり、1人で暮らしている場合、何かがあってからでは手遅れになってしまう。
一方で、親の側は子どもに心配をかけたくないからと、1人でも大丈夫だと主張したり、子どもから見守りサービスの導入を打診されると「監視されているようで嫌だ」と断ったり、双方の思いはすれ違うことも少なくない。
そんな親子双方の要望に沿うような高齢者見守りサービス「ひとり暮らしのおまもり」が2022年11月に開始し、機能のシンプルさで好評を得ている。
使い方は簡単で、毎日開けるドアなどにセンサを取り付けると、一定時間動きがない場合に限り、アプリへ通知する形で知らせてくれる。
ユーザー(子ども側)からは「これまで帰省前後など1年に数回くらいしか親のことを気にかけることはなかったけれど、利用してからは普段の生活の中で親のことを考える時間が増えた」といったポジティブな意見が寄せられている。
カメラではなく小型センサを使っているのも特徴だ。見守られる方(親側)はデバイスを意識することなく、導入前と変わらない生活を送ることができる。高齢単身者向け賃貸マンションなどからも引き合いがあるという。
「見守る方も気にしすぎることなく、お互いに適度な距離間でご利用いただける機能に落とし込んだサービスです」と語るのは、同サービスを開発した日本ビジネス開発 代表取締役 矢野雅也さん。矢野さんに開発の背景や今後の展望を聞いた。
「見守られる側のプライバシーを守るサービス」を作りたい
ひとり暮らしのおまもりが誕生したきっかけは、矢野さん自身がそれを必要としたことにある。離れてひとりで暮らす高齢の母がコロナ下以降、家に引きこもりがちになり、問題なく暮らしているかが気がかりになった。
矢野さんは「見守られる側のプライバシーを守りながら見守りができる」サービスを望んだが、世の中にその理想を満たすサービスはなかった。矢野さんの母も、主にカメラを活用する既存の見守りサービスを嫌がったという。そこで矢野さんは自ら開発する道を選ぶ。
需要の有無を確かめるため周囲にヒアリングをしたところ、矢野さんと同じような状況の人々がシンプルな見守りサービスを求めていることを掴み、開発に着手。日本ビジネス開発は、後述するようにIoT技術の開発も行っている。自社の技術で子どもの見守りに使用していたセンサとアプリを連携させる仕組みを高齢者の見守りに応用する形とした。
特徴は複雑になりがちな機能を徹底的に削ぎ落として、究極のシンプルを実現しただけではない。初期費用はかからず、月額費用は770円(税込)と気軽に使いやすい金額感となっている(※)。2023年12月には買い切りプラン(楽天/Amazon)も登場し、導入のハードルが下がると好評を得ている。キットが届いたらレンタル式のデバイスをドアに貼り付け(工事不要)、アプリと連携させたらすぐに使い始めることができる。
見守る側が導入しやすいようシンプル・安価を実現
「シンプルにした最大の理由は費用を下げたかったからです。開発にあたりアンケートを取ったところ見えてきたのが、導入を検討はするものの、検討で終わる方が多いことでした。子どもとしては親はまだ元気だし大丈夫だろう、親も自分はまだ問題ないだろうという思いがあるケースが多いです。
ただ、高齢の親がひとり暮らしをしているのを心配したり、ひとりにしていることを後ろめたく感じたりする方もいます。そんな方が月々いくらなら金銭的に大きな負担を感じることなく支払えるかと考えると、これくらいの金額ではないかと思うのです」(矢野さん、以下同)
止まらない物価高に上がらない賃金……。そんな状況では自分たちの生活もままならない。特に子どもを抱える家庭にとっては、子育てにもお金がかかる。そうなると、自分が面倒を見なければ生きていけない子どもに、まずは優先的にお金をかけようとするのは自然なことだ。
それゆえ、今は元気そうに見える親の見守りは「まだ先でいい」「もう少し検討する」となるのも無理はない。また、親が若いときの記憶がある子どもにとって、親の老いに向き合うのは心情的な辛さもある。
では、一般家庭への導入ハードルが比較的高いこのサービスをどう広げていくのか。矢野さんがマーケティングツールとして活用しているのが、同社が2018年秋より運営するWebメディア「Glimpse」だ。「生活を豊かにするモノが集まる場」として、新たなイノベーションが落とし込まれた製品やサービスを内製する記事で紹介している。
Glimpseは矢野さん自身をペルソナとして運営し、同世代や関心を持つユーザーが集まっているという。だからこそ、記事で紹介すると一定の反響がある。このほか、ひとり暮らしのおまもりサイト内にカテゴリとして設けた、開発秘話をはじめとしたコラムも特徴的だ。Web広告出稿による一時的な効果よりも、長く残る資産となっている。
コロナ下でのプレゼントキャンペーンで注目されるように
ここまで、主にひとり暮らしのお守りについてご紹介してきたが、同社のそのほかの事業についても触れていきたい。前出のGlimpseや2022年冬にリリースした歯列矯正メディア「アットスマイル矯正」などのWebメディアの運営や、IoTデバイス・小型家電の開発・販売までも行う。
これらの事業で蓄えた技術力は、ひとり暮らしのおまもりにも大きく関わっている。高い技術力を持ちながらも、同社が躍進したのはコロナ下真っ只中という近年のことだった。
コロナ下前、日本の正規代理店として販売活動を始めた海外製の家庭用スマートプロジェクタが思うように売れない日々が続いていた。コロナ下になって矢野さんがX(当時はTwitter)を見ていると、たくさんの保護者たちが、学校に行けない子どもたちが家で退屈していると投稿していた。
「全然売れていないから、困っている家庭に差し上げよう」。そう閃いた矢野さんはプレゼントキャンペーンを実施。すると大反響があり、同社やGlimpseが注目されるきっかけとなった。
「基本的には比較的新しいカテゴリにおいて、日々の生活を豊かにする、または日々の問題を解決するためのサービスを扱っています。一方で、『アットスマイル矯正』はこれまでわれわれがメインで扱ってきたハードウェアとはタイプが異なります。ハードウェアのような分かりやすい“モノ”を通しての体験ではなく、競合もたくさんある中でサービスを普及させることができれば、組織としての能力が向上すると考えてスタートしました」
そんな中で2023年9月に販売開始したのが、自社開発した「Adget Pocket Projector」である。コンパクトでおしゃれなデザインだと話題を集め、今では同社の看板商品のひとつになっている。
「日本製品を海外市場へ」の流れを思い描いている
最後に、会社としての展望を尋ねた。矢野さんは「社会課題の解決を主要な事業にしようとは考えていません」と話す。
ただ、これまで海外メーカーの国内正規代理店として機器販売を行う中で積み上げた利益を、ひとり暮らしのおまもりのような社会課題と向き合うプロダクトの開発資源に充てていくつもりだ。また、販売だけではなく自社ブランドの開発・展開にも引き続き力を入れる。
「これまで多くの海外製品を取り扱ってきて、明らかに日本の製品よりも優れたものは多い印象です。このことを私は率直に『悔しい』と感じています。
今は海外製品を日本市場に販売することが事業の主軸ですが、逆に日本製品を海外市場に持っていく、海外市場で販売する流れを実現したいと考えています。それもあって自社製品としてAdget Pocket Projectorを作りましたし、今年からは海外での販売開始を予定しています」
得意分野で利益を上げて、自分ごととして感じている社会課題と向き合う--。ひとり暮らしのおまもりというサービスから同社を知った筆者だが、その姿勢はとても理に適っていると感じられた。今後も多様な顔を持つ同社の動向を追いかけたい。