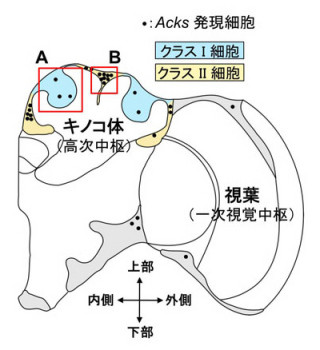奈良先端科学技術大学院大学(NAIST)とバイオジェット(沖縄県)は2月2日、沖縄で栽培される島バナナの茎から新しい酵母を単離し、その特性を解析すると共に、バナナの主要な香り成分である「酢酸イソアミル」を高生産する菌株の育種に成功したことを発表した。
同成果は、NAIST 研究推進機構 発酵科学研究室の髙木博史特任教授、同・磯貝章太特任助教、バイオジェットの共同研究チームによるもの。詳細は、「Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry」に掲載された。
泡盛は、沖縄県内の食品産業の柱の1つだが、近年は需要が減少しており、各酒造所では独自の商品開発や製造工程の改良による需要喚起を図っているという。泡盛の製造には黒麹菌と酵母が用いられており、それらが泡盛の風味や酒質に影響を与えることが知られている。特に、主要な香気成分高級アルコール、エステル類は醸造過程において、酵母のアミノ酸代謝によって生成されるものが多いため、泡盛の品質向上や差別化には、アミノ酸の生成量に特徴のある酵母の開発が重要とされている。
そうした中、研究チームではこれまで、多くの泡盛に用いられている汎用酵母やハイビスカスの花から独自に単離した酵母を親株にして、清酒の吟醸香およびパンのバナナ香の主要成分である酢酸イソアミルの含量が増加した株を取得することに成功していた。また、それらの株を用いて醸造した泡盛は香味性が向上しており、新里酒造、神谷酒造所、神村酒造、南島酒販、池原酒造などと共に、多数の商品化にも成功しているとする。
そこで今回の研究では、泡盛のブランド化戦略として、沖縄で広く栽培され親しまれている島バナナに着目。その茎からアルコール生産能の高い酵母を単離し、特性を解析すると同時に、泡盛醸造に応用する研究を実施することにしたという。
島バナナの茎から単離されたのは、高いアルコール生産能を有し、泡盛醸造が可能な野生酵母「35a14株」で、次世代シーケンサーを用いたゲノム解析の結果、同株は昔から酒類、パン類の製造に使用されている「サッカロマイセス・セレビシエ」に属しているものの、従来の泡盛醸造に広く用いられている酵母「101株」とは系統が異なり、沖縄独自の株であることが示唆されたとする。また、35a14株は泡盛の古酒に含まれる主要な香味成分である「バニリン」の前駆体「4-ビニルグアヤコール」(4-VG)を高生産する一方、酢酸イソアミルの生産量は低いことがわかったとした。
酢酸イソアミルはアミノ酸の一種である「ロイシン」の代謝中間体から合成されるため、ロイシンを高生産する酵母では酢酸イソアミルも多く産生することが期待できるという。そこで、35a14株に紫外線照射による突然変異処理を施した後、ロイシンのアナログである「5,5,5-トリフルオロ-DL-ロイシン」を含む寒天培地上で出現したコロニー内から、親株に比べて細胞内のロイシン含量が高い変異株「BNNL80株」が取得された。同株には「α-イソプロピルリンゴ酸合成酵素」の遺伝子にアミノ酸置換を伴う変異があり、ロイシンによるフィードバック阻害に対する感受性が低下し、ロイシンが高生産されることが考えられたとする。
さらに、BNNL80株を用いた泡盛の小仕込み試験が行われたところ、泡盛中の酢酸イソアミルは親株の35a14株の約35倍に増加していたとする一方、4-VG含有量は親株の特徴を維持しており、従来の101株の約4倍が示されたとした。
-

ピルビン酸からのロイシンおよび酢酸イソアミルの合成経路。BCAT:分岐鎖アミノ酸アミノ基転移酵素、DC:αケト酸脱炭酸酵素、ADH:アルコール脱水素酵素、AAT:アルコールアセチル基転移酵素 (出所:プレスリリース)
これらの結果を踏まえると研究チームでは、BNNL80株により101株に比べて酢酸イソアミルと4-VGの含量が高い泡盛の醸造が可能になったとするほか、BNNL80株で醸造された泡盛は、バナナの香りを含むフルーティーで豊かな風味を特徴としている。すでに2024年2月1日より「ZANPA島バナナ酵母」として比嘉酒造より販売が開始されたという。
なお、研究チームでは、今回の研究手法は酵母だけでなく、有用な産業微生物の分類や育種にも応用が可能だとしており、今後、得られた知見をほかの酒類(清酒、ビール、焼酎など)やパン類の製造に用いる酵母の開発に活用し、今回の研究成果を広く普及させたいと考えているとする。さらに、髙木特任教授らはロイシン、プロリン、リジンなどの機能性アミノ酸を微生物で高生産させる育種技術を「アミノ酸機能工学」と命名し、微生物の高機能開発や微生物による有用物質の生産に応用できる技術としての確立を目指していくとしている。
,A@アミノ酸機能工学|