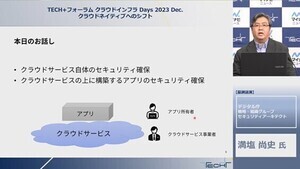「大人になってからの学び」に注目が集まっている。リスキリングやリカレントなど、自らが携わる業務に必要なスキルの体得は、今やビジネスパーソンに欠かせない取り組みとなりつつある。
DX実現やデジタル人材の育成を進めたい企業としても、従業員が新たな技術に適応するための学習は推奨しているはずだ。しかし、実際どのように従業員の学びを促進・支援し、組織のDXに還元するかというノウハウを確立している企業は多くない。
「業務効率化を目的としたDXは進んでいるが、ビジネスを前に進める“攻めのDX”が実現できている企業はごく少数」――そう語るのは、数々の大手企業のDX人材育成やキャリア開発を支援するトレノケートホールディングスで代表取締役社長を務める杉島泰斗氏だ。
杉島氏は「DXをかなえるにはマネジメント層の意識が大事」と話す。DXを進めるために、社内のデジタル人材を増やすためには、それを先導する人々から変わっていくことが求められるというのだ。
本稿では、DXが“できる企業”と“なかなか進まない企業”の特徴から、マネジメント層が持つべき視点について明らかにしたい。
DXが“ボヤっとする”のは目的がないから
業務効率化を目指したデジタル化は、言わずもがな進んでいる。しかし真のDXとは、新たなビジネスの創出など、変革を伴うものだ。それを踏まえた上でより高度なDXを進めるためには、システム担当やIT専門職以外の現場人材のITリテラシーを高める必要があると杉島氏は言う。
「ユーザー企業においてもITリテラシーの高い人材が求められていて、知識を持った上で自社に合ったITを導入しなくてはいけません。弊社で行っている研修でも、初歩的な研修からスタートするケースが多いです」(杉島氏)
とはいえ、企業規模や業態によってもDXの進め具合やそもそもの必要性は千差万別。実際は、ITの知識やスキルを蓄えるだけにとどまり、肝心のDX は“絵にかいた餅”になってしまう企業も少なくないそうだ。
とりあえずDX関連のeラーニングを導入したものの、習熟度が上がらず「従業員にDXを進める気がない」と判断してしまう企業が多いという。
さらに、こうしたDXプロジェクトに本腰を入れようと、比較的能力の高いエース人材にかじ取りを任せるケースもある。ただ、エース人材はそもそも日常業務が忙しく、結果的に業務とDXプロジェクトの両立ができず頓挫してしまうのもよくあることだ。
杉島氏はその理由を「目的がボヤっとしているから、DXが成熟しない」と話す。
トレノケートが研修を行う企業の中には上層部から「DXを進めなさい」と指示が出される企業もあるそうだが、あくまでDXは手段だ。企業がかなえたい姿の背中を押すものであり、目指すゴールがはっきりしていなければ、DXも失敗する。
「マネジメント層がゴールを描くことが一番重要なんです。そうすれば、充てるべき人材や必要な資材が見えてきますから、そこにデジタルを当てはめてあげればいいと思います。ゴール設定が明確で、そこに向かってPDCAを回している企業は、DXが進みやすい印象を持っています」(杉島氏)
「意外とできる」と実感できればハードルが下がる
「ゴールを描いてからそのためのDXを当てはめる」ためにマネジメント層が取り組むべきは、自身のITリテラシーの向上だ。杉島氏は、DX成功企業の共通点として「うまくいっている企業は社長が積極的にリスキリングをしている」と語る。では、マネジメント層が皆リスキリングすれば良いように思うが、それは必ずしも容易な話ではないようだ。
杉島氏は、その理由として、以下の3点を挙げる。
・ITの有効性に気付いた人は自発的に学習するが、そもそもITに興味がない層も多い
・ITで何ができるようになるかがイメージできない
・専門用語が難しすぎて理解できない
こうした問題の解決策として、ITへのハードルを下げることは有効である。例えば、トレノケートが支援したとある建設会社では、ITリテラシー研修を導入したものの、やる気がある人とない人でリテラシー格差が顕著になるという現象が起きた。そこで、その研修のほかにIT用語の解説を手書きの4コマ漫画にして社内に配布したところ、一気に全体の理解が進み、格差が解消されたという。
こうしてハードルを下げて理解を促す方法の他に、ユニークな研修として“ショック療法”も1つの手段だ。
「トレノケートが提供している2日間の研修では、実際にデータベースを触らせて、プログラミングをしてもらったりするんです。そうすると、まだITを理解していない状態からでも『意外とできる』と実感してくれる人がほとんどでした。できることが見えると、一気にハードルが下がっていきます」(杉島氏)
これまで“食わず嫌い”でITに触れてこなかった人でも、「自分はできる」という実感を持てれば、ITに向き合う姿勢も変わり得る。必ずしも荒療治がである必要はないが、まずやってみることが一気に“ITアレルギー”を克服する突破口になることもあるのだ。
DXはすぐに辞めない、楽しむマインドを持つ
DX支援やデジタル人材の育成にも、上述のように企業に合わせてアプローチの仕方が異なる。もしかしたら、一つのやり方ではうまくいかないこともあるかもしれない。杉島氏は「DXは1、2年で成果の出るものではない」と語る。
「DXは、取り組みが全てうまくいくとは限りません。失敗してしまうこともあると思いますが、すぐに辞めず5年、10年のスパンで取り組むと良いでしょう。取り組みに対して評価や改善をする必要があるので、マネジメント側の体力が必要です」(杉島氏)
続けて杉島氏は「せっかく取り組むなら、楽しんでやってみた方がいい」と話す。マネジメント層が取り組みを楽しむことで、そのポジティブな空気が社内に波及して現場のモチベーション向上へとつながるのだ。これを実現するには、やはり明確なゴールを設定することが欠かせない。
「DXを学ぶにしても、なぜこれをすべきか、と言うところが腹落ちしている方が学習効率が高くなります。ゴール設定へ向かう楽しさを感じてほしいので、まずはマインドセットから整えてみましょう」(杉島氏)