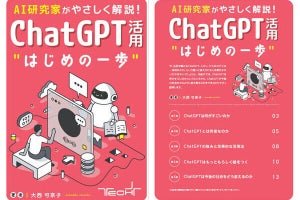2022年から2023年にかけて世界に衝撃をもたらした生成AI。多くの企業が生成AIの活用を模索する中、すでにさまざまな取り組みに着手しているのがSBIグループだ。とはいえ、AI活用にはまだ課題もある。同社はそれらの課題にどう対処し、どのような考え方でプロジェクトを進めているのか。
11月30日に開催された「DataRobot Launch Event 2023~Fall」にSBIホールディングス 社長室ビッグデータ担当 部長 兼 SBI生成AI室長 佐藤市雄氏が登壇。「生成AI活用最前線 生成AIで金融ビジネスを変革する」と題し、SBIグループにおけるAI活用の歩みと、生成AI活用に向けた具体的な取り組みの内容について語った。
AI活用の自走化を目指すSBIグループの取り組み
講演冒頭、佐藤氏は「1年前の11月30日は驚くべき日になった」と切り出した。
言うまでもなくChatGPTのことである。2022年から2023年にかけて、AI業界はChatGPTをはじめとする生成AIの話題でもちきりだった。多くの企業がAIに関心を持ち、導入に向けて動いた。
そうした中で、いち早くAIに着目していたのが佐藤氏だ。氏はChatGPT登場の10年も前の2012年、SBIグループのデータ活用における横断的組織を設立。2023年にはSBI生成AI室を設立し、室長に就任した。
SBIグループは、AIやデータ活用で何を目指しているのか。
まずはAI活用そのものの高度化だ。ビジネスにおける多くの意思決定場面においてAIを活用することで、顧客提供価値とサービス競争性を高めていく狙いがある。
そして、さらに重要なのが「AI活用を自走する組織化」である。
「CoE組織や持株会社がAIを活用するのではなく、SBIグループ全体が常にAIを活用し、イノベーションを起こしていくことを目指しています」(佐藤氏)
SBIグループ組織内で本格的にAIプロジェクトがスタートしたのは2015年のことだった。当時主流だったのは生成AIではなく予測AI。そこから毎年のようにプロジェクト数は増加しており、2021年度にはコアとなる金融事業でのAI自走化、2022年度には資本業務提携先の地方銀行のAI自走化、2023年度には金融事業を超えてAI自走化の拡大を成し遂げてきた。
そして2024年以降、佐藤氏はこれまでに培ってきた予測AIに生成AIを加え、ハイブリッドで高度な自走化を目指すという。
「生成AIを使ったプロジェクトといっても、一足飛びにできるものではありません。私は生成AIは予測AIの延長線上にあると考えています。AI戦略や人材育成、データ分析、AIガバナンスなど、すべて予測AIの土台の上に積み上がってきたものであり、生成AIの展開においても、その経験やフレームワークは生かされているからです」(佐藤氏)
AIプロジェクトの選定は「潜在価値」を重視
では、具体的にSBIグループは生成AIにどう取り組んでいるのか。
2023年の前半は、生成AIが何に使えるのかを模索していた時期だったと佐藤氏は振り返る。
「アイデア出しを従業員にお願いして、たくさん出してもらいました。ただ、課題も見えてきました。例えばエンジニアが出したアイデアは技術的には実現可能ですが、なかなか現場のニーズには合致しないものが多いのです。一方で現場から出てくるアイデアは、生成AIの理解が不十分で空想的なものが多くありました」(佐藤氏)
そこで佐藤氏が実施したのが、事業部メンバーの参加するワークショップだ。現場の意見を取り込んだ生成AIテーマを議論することで、実現可能かつ現場のニーズに即したテーマが70以上も生まれたという。
このテーマの絞り込みにおいて重視すべきなのが「潜在価値」だ。
潜在価値とは、手堅く目先の利益を求めるのではなく、ポテンシャルを重要視する考え方である。もちろん、会社としてリソースをかける以上は利益の概算を提示する必要はある。だが、既存ビジネスのように高い精度でしっかりとした数字を出す必要はない。潜在価値を計算で求める場合、主要因となる項目が計算式の中に入っていれば他の項目は大雑把な精度でも構わないのだ。
もっとも、70以上のテーマが生まれたことで新たな悩みの種も出てきた。実際に開発を行うエンジニアの不足である。
「とはいえ、それでもAI活用は進める必要があります。そこで、できるだけ早く開発サイクルを回すために導入したのが、DataRobotの提供する生成AIソリューションでした」(佐藤氏)
DataRobotの生成AIソリューションを活用することで、コーディングレスのGUIベース開発が可能になる。そのため、データの準備からナレッジベースの構築、生成モデル構築、そして本番運用に至るまで、開発と現場が一体となり高速でPDCAサイクルを回すことができるのだ。結果としてエンジニア不足も補えるというわけだ。
こうした生成AIソリューションの活用により、すでにSBIグループ内では多数のAIプロジェクトが走っている。
その一つが、金融商品照会チャットボットだ。金融商品に必須となる「数値によるソート」を生成AIで行うサービスで、Webアプリケーションとして顧客向けに提供されている。
社内向けには法務文書の探索と要約に生成AIが使用されている。というのも、法務の業務は膨大な文書を調査する必要があり、多大なコストがかかる。そこにAIを活用するのだ。
コールセンターでもAIを活用し、通話記録の自動生成を行っている。これまでは人手で時間をかけて作成していたが、AIを活用することで省力化に成功した。
2024年以降はさらにプロジェクトを増やし、開発のスピードを上げていくという佐藤氏。そのために重要なのが「ガバナンスを正しく効かせる」ことだという。
「今、AIはすばらしいエンジンを手に入れました。(そのインパクトは)馬車の時代から自動車の時代に移り変わったようなものです。ただ、自動車が性能を発揮するにはサーキットの整備が必要になります」(佐藤氏)
サーキット整備とは、つまりガバナンスを整えることだ。ガイドラインの制定や予測AIを活用したリスク監視により、データの安全な運用やリスクにつながる回答の阻止を行う。それにより初めて、真に革新的な生成AIベースの金融サービスを生み出せるのだ。
予測AI×生成AIによるアプローチ
生成AI活用における安定性と安全性を維持するため、SBIグループではAI基盤の構築を急いでいる。
現在、構築が進んでいるのがAzure OpenAIと、DataRobotのソリューションを組み合わせた環境だ。これにより、現場のメンバーが安全にAIを利用できるのだという。
「運用を続けるうちに新しい問題も出てきますが、それらを全て自前で解決しようとは思っていません。それは私たちがやりたいことのメインではないからです。そこはDataRobotのようなパートナーの力を借りて解決していきます」(佐藤氏)
予測AIと生成AIを掛け合わせることによる問題解決アプローチも検討している。例えば何かしらの質問が寄せられた場合、生成AIに通す前にまず予測AIで内容を分類し、適切な質問のみを生成AIに投げる。さらに生成AIが作り出した回答も、アウトプットの前に予測AIを通し、その信頼度を予測。これにより、リスクのある回答のアウトプットを避けるという仕組みである。このように、予測AIと生成AIを組み合わせることで、AIが持つリスクをできる限り低減した運用が可能になるのだという。
こうしたAI活用を推進するためには、組織体制と人材の両方が必要となる。
佐藤氏がリーダーを務める社長室ビッグデータ担当は持株会社の社長室直下に属する組織だが、グループ内の事業会社においてもCoE組織の育成を担ってきた。今後はSBI生成AI室が主導して、同様の動きを生成AIについても実践していくと佐藤氏は構想を語る。
「特に生成AIはボトムアップの力が必要です。そのため、グループ各社にはどんどん権限委譲を行い、実践で経験を積み、AIを使っていくんだ、という企業文化をつくっていきます」(佐藤氏)
さらに佐藤氏は、今後のAI活用の構想についても語った。
「生成AI活用はSBIグループ内で閉じるわけではありません。地域金融機関と連携する取り組みとして『SBI地域生成AILab(SBI-REGAIL)』を立ち上げ、生成AI勉強会を開催したり、金融機関からの出向者を募集したりして、地域金融機関をサポートしていきます」(佐藤氏)
これまでに積み上げてきた予測AI技術の知見を生成AI活用にも活かし、多くのプロジェクトを進行させているSBIグループ。AI活用で課題になることの多いエンジニア不足やリスク対応といった点への対処法は、金融業界はもちろん、いずれの業界の企業においても大いに参考になるのではないだろうか。