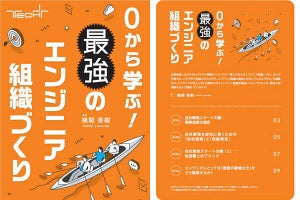中央集権的な管理機関を必要とせず、参加者が対等に総合監視/協力をすることで、信頼性を維持する「ブロックチェーン」。2010年代前半から金融業界を中心に注目され、トレーサビリティやサプライチェーン管理の領域で活用が期待された。しかし、実際に導入・運用している企業は少ない。
ブロックチェーンのコンセプト自体は非常にエキサイティングだが、ビジネス導入では克服すべき課題がある――。こう指摘するのは大手コンサルティング会社EYのグローバル ブロックチェーン リーダーであり、Ethereum(イーサリアム)の標準化団体 Ethereum Enterprise Alliance(EEA)のボードメンバーも務めるポール・ブロディー(Paul R. Brody)氏だ。では、今後、ブロックチェーンがエンタープライズ市場で普及するためにはどのような課題を克服する必要があるのか。話を訊いた。
「プライベート・ブロックチェーンは失敗した」と言い切る理由
IT専門調査会社のガートナー ジャパンが2023年8月に公開した「日本における未来志向型インフラテクノロジーのハイプ・サイクル:2023年」によると、ブロックチェーンは「幻滅期」から「啓発期」に移行しているという。
もともとブロックチェーンは、暗号化資産「ビットコイン」の基盤技術として考案され、発展してきたという経緯がある。取引記録(ブロック)を時系列順にチェーン状に連結することで、改ざんが困難でセキュアな取引履歴の保存を可能にする技術だ。現在、エンタープライズ市場においては、資産管理や炭素会計など、限られた業務範囲でのユースケースを増やしている段階である。
ブロックチェーン導入を阻害する課題として挙げられるのが、「技術的な複雑性」や「規制の不確実性」、「導入コストがかかりすぎて投資の回収が見込めない」といったことだ。中でもブロディー氏は企業が最も懸念する課題として「ビジネス上のプライバシー」を挙げ、次のように指摘する。
「企業はブロックチェーンを活用して(受発注や請求、支払いなどの)ビジネス・トランザクションを自動化したり、資産をデジタルトークンに変換したりすることに抵抗はありません。しかし、“契約”というビジネスの根幹を担うプライバシー情報を、基本的に誰でも見られるパブリック・ブロックチェーン上に公開することには抵抗があるのです」(同氏)。
こうしたことから、かつてエンタープライズの領域では、特定の管理者が管理し、限定されたユーザーのみが利用できる「プライベート・ブロックチェーン」が主流になると言われていた。しかし、プライベートであったとしても、そこに参加しているコンペティターには自社の契約情報が見えてしまう。そうした“ビジネスの流れ”を共有することはマイナスであると判断する企業が多かったため、プライベート・ブロックチェーンは衰退している。
ブロディー氏は「プライベート・ブロックチェーンは失敗しています」と言い切る。その理由としては、プライベート・ブロックチェーンを構築するネットワークが非常に高価であったことと、参加するコミュニティメンバーの合意形成ができず、ガバナンス統治ができていないことが挙げられるという。同氏は「仮にプライベート・ブロックチェーンが存続できるとすれば、政府管轄の中央銀行がスタンダードを策定したデジタル通貨の運用といった限定的な領域でしょう」と見解を示した。
ブロックチェーン普及に立ちはだかる「3つの壁」
今後、ブロックチェーンがエンタープライズ市場で普及するには、プライバシーに対応するソリューションの増加が必須となる。ガートナーがブロックチェーンを啓発期としたとおり、技術に対する市場の理解と現実的なユースケースが増加すれば、普及は加速するとEYは予想している。
同社ではエンタープライズ市場で主流になるブロックチェーンとしてEthereumを挙げる。同市場には「IBM Blockchain」や「Hyperledger Fabric」、「R3 Corda」といったブロックチェーン・プラットフォームが存在する。ブロディー氏はEthereumが主流になる根拠を次のように説明する。
「技術業界の歴史を紐解くと、圧倒的に標準に収斂する傾向があります。例えば、モバイル、デスクトップ、メインフレーム、ネットワーク機器などのプラットフォームを見ると、1つから2つの標準規格が市場の80%から90%を占めています。Ethereumは(ほかのブロックチェーンと比較し)多様な業界で広範囲に利用されていますから、ブロックチェーン・プラットフォームでも同じことが起こると予測しています」(同氏)。
とはいえEthereumがさらに普及するには、プライバシーを含めた3つの課題を克服する必要があるとブロディー氏は説明する。
1つ目は拡張性だ。EYではグローバル企業の大多数がEthereumを利用する場合には1日に約400億件のトランザクションを処理する必要があると試算している。ただし、これは2023年末時点で実現可能だという。ブロディー氏は「少なくとも40億人まで利用するロードマップはすでに完成しています」と語る。
2つ目はユーザビリティである。Ethereumが登場した当初の実装は、専門知識とスキルを必要としていた。例えばブロックチェーンを応用し、契約の成立や条件判定を自動認識する「スマートコントラクト」の開発には、「Solidity」などの専門的なプログラミング言語の理解と、スマートコントラクトに起因する脆弱性対策を講じるスキルが必要だった。ただし、ブロディー氏は「今後、この“ハードル”は下がります」と断言し、以下のように説明する。
「Ethereumが登場した初期段階は、Eコマースのそれと似ています。当初企業は独自のEコマース環境を構築しなければならず、それには技術的な知識や開発スキルを持った担当者が必要でした。しかし、現在はクラウド事業者などが提供するサービスを使えば、誰でも簡単にオンラインストアを開設できますよね。同様に、今後はEthereumベースのアプリケーションやサービスを簡単に利用できるサービスが登場すると考えています。実際、EYでは数年前から(Ethereumを簡単に導入・活用できる)取り組みを継続しています」(ブロディー氏)
仕組みを知らなくてもブロックチェーンを活用できる環境を
では、最大の課題であるプライバシーに関してはどのようなソリューションがあるのか。
EYでは1つの解決策として「ZKP(Zero-Knowledge-Proof:ゼロ知識証明)」コンパイラ(ソフトウエア)の「Starlight」を無償提供している。ZKPとは、一方の当事者が特定の情報を知っていることを、その情報を明かすことなく他方の当事者に証明する技術を指す。ZKPコンパイラを利用したアプリケーションを構築すれば、「特定のルールや手続きといった一般的なビジネスロジックは公開するが、個々の契約内容は見られない」といったことが可能になる。
ブロディー氏は「Starlightを活用すれば、ブロックチェーンの原理や機能を理解しなくても、ZKP(技術を包含した)アプリケーションを構築できます。EYとしてはStarlightを無償のパブリックドメインソフトとして提供することでEthereum導入企業を支援し、(ブロックチェーン)市場を活性化させたいと考えています」と語る。
さらにブロディー氏は、Starlightのようなブロックチェーン導入のハードルを下げるソリューションは、ビジネスの透明性と公平性を実現する一助になると主張する。
「大企業であれば、自社でブロックチェーン・アプリを開発・運用できますが、中堅・小規模企業では難しいでしょう。EYがStarlightをパブリックドメインソフトウエアとして提供する理由はここにあります。つまり、技術や人材といったリソースが限られた組織であっても、ブロックチェーンを活用した競争的で公正かつ安全な取引を可能にしたいのです。究極的にはEコマースと同様に、ブロックチェーンの仕組みを知らなくても取引が行える環境を目指しています」(同氏)。