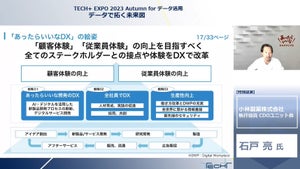「データ活用にチャレンジしたものの、どのデータも中途半端で使えないという“残念過ぎる現実”を突き付けられた企業もある」。そう語るのは、元電通マクロミルインサイト 代表取締役社長で、現在は事業開発、組織開発の統合コンサルティングを提供するZoku Zoku Consultingの代表を務める中野崇氏だ。同氏はその理由を、ビジネス基礎スキルが不足しているために漠然とデータの蓄積や分析を行ってしまうことだと説明する。
11月6日~17日に開催された「TECH+ EXPO 2023 Autumn for データ活用 データで拓く未来図」に中野氏が登壇。価値のあるデータを蓄積するために必要な「データ活用企画」と、それを正しく行うために必要な「ビジネス基礎スキル」について解説した。
「TECH+ EXPO 2023 Autumn for データ活用 データで拓く未来図」その他の講演レポートはこちら
データの蓄積は明確な目的を持って行う
講演冒頭で中野氏は、「データ活用の基本的な流れは、問題の解決のためにデータを収集し、集計して解析、そして最終的に結果を解釈すると考えがちだが、重要な要素が2つ抜けている」と指摘した。その2つとはデータ収集の前にデータ活用の企画を考えること、そして解釈して終わらせるのではなく、それを問題解決のアクションにつなげることだ。
さらに同氏は「これでもまだ不十分」だと続ける。仮にアクションを起こしても解決しなければ、別のアクションや別の解釈を検討すべきであり、使ったデータが違っていたのであればデータ活用企画から考え直すべきである。こういったことを何度も行って問題の解決につながって初めて、データ活用が成功したと言えるのだ。そこで重要になるのが、最初にデータ活用企画を考えておくことである。
活用前に不可欠なデータ活用企画
データ活用企画とは、ビジネスの問題解決に向けてデータをどのように活用し、どんなアクションにつなげるのかを整理した計画のことを指す。特に考えておく必要があるのが、データ活用の目的だ。ビジネスの現場には、売上がなぜ伸びないのか、退職者がなぜ増えているのかなど、データを一目見ただけでは原因が見えない事象も少なくない。データ活用に取り組む前には、これらの問題をデータで明らかにし、新しいアクションや意思決定につなげるという明確な目的をあらかじめ持っておくべきである。
次に必要なのが、ビジネスとデータについての問題と課題を整理しておくことだ。問題とは在りたい姿と現状のギャップを指す。問題は探せばいくらでも出てくるので、その中で優先順位の高い問題選定とその解決方法を考えることが課題となる。例えば、ビジネスでの売り上げ未達成という問題には商品力不足や人材の質、競合要因などがあり、この中のどれを解決すべきかという課題を設定する。データについても理想と現状のギャップ、つまり問題(わからない事)を整理し、知るべきことは何か=データの課題つまり課題を設定しておくことが重要となる。
この他にもちろん、データをどのように集め、どう分析するか、そして分析結果をどのように解釈して、どんなアクションを実行するかという仮説を立てておくことも必要であり、全体の予算やスケジュールもここで考えておかなければならない。これら全てを分析の前にしっかり考えておくことが、データ活用企画なのである。
データ活用企画の具体的な考え方
続いて中野氏はデータ活用企画の考え方について具体例を挙げて説明した。例えば、法人営業において「新規顧客の獲得数の実績」が目標に届かなかった場合、データ活用の目的は営業改善策を見つけることだ。しかし、このままでは問題も目的も抽象的なので、さらにこれらを分解して具体化する必要がある。問題を分解するには、以下の方法が考えられる。
保有顧客リストを基にした営業活動の場合は、保有顧客リストの作成や確認、その中で営業が対応すべき有効顧客リストの抽出、それに基づいて行われる商談、さらに次につながる有効商談、そして見積提出、受注といったプロセスに分解できる。
その後、それぞれのプロセスの数字をデータとして集めれば、次のプロセスへの移行率が出てくる。これによってどのプロセスに問題があるのかが可視化され、その要因を特定する。ここで、解決すべき問題=課題が明らかになるというわけだ。
この際に重要なのが、例えば、受注率が低いのであれば、納期や価格、提案力といった失注要因になりそうなものをあらかじめ「現状仮説」としてリストアップしておくことだ。仮説があれば、集まったデータから要因をすばやく特定できるためだと中野氏は説明する。
さらに現状仮説で挙げたそれぞれの要因について、低価格化、納期短縮といった採るべき行動を「アクション仮説」として考えておけば、集計後にすぐアクションを実行できる。したがって、「この両方の仮説を立てておくことが重要」(中野氏)なのだ。
よりデータ活用の精度を高めるには、「比較という観点も必要」だと中野氏は語る。例えば、商品ごとの失注要因を比較することで、共通する要因を特定できる。そうすれば、短中期課題だけでなく、会社全体としての抜本的改善が必要な長期課題も見えてくるという。
比較軸は、年齢や性別などの個人属性のほか、パーソナリティ、キャリア志向などの価値観、企業文化やビジネスモデル、利益率などの企業属性などさまざまなものがあるが、問題発見につながりやすい比較軸はどれかを考えて、ここでも仮説を立てて絞り込むことが重要になるそうだ。
データ活用に必要なビジネス基礎スキルとは
「こういったことを考えながらデータ活用を成功に導くには、分析の実務スキルよりもビジネスの基礎スキルのほうが重要になります」(中野氏)
ではデータ活用に必要となるビジネス基礎スキルとはどんなものなのか。まず分析の専門家ではないビジネス系や事業系の人材には、データ活用企画で考えるべき内容を理解したうえで、問題を発見し、課題を設定する力や仮説を考える力が必要になる。データの集計、可視化能力については、一般的なExcelやPowerPointレベルの簡易的なもので良いと同氏は言う。一方、分析の専門家は、社内外にどんなデータがあるかというデータバリエーションを理解し、専門ツールを活用できる高度な集計・分析力が求められる。
これらのスキルの中で中野氏が最も重要だと挙げるのが、適切に問題の発見と課題の設定ができる力だ。そのために知っておくべきなのが、問題をどう分解するかのパターンだという。
例えば、売上が問題になっている場合、売上は数量×単価や、既存顧客+新規顧客といったように、複数の方法で分解できる。費用なら固定費+変動費、利益なら売上-費用に分解できる。また、受注数なら商談数×受注率になるし、仕事処理数(生産性)なら労働時間×処理スピードというように量×質に分解できる。生産性やコストパフォーマンスなら対応件数÷労働時間といった割り算だ。
ここでポイントになるのは、分解する方法によって必要なデータが変わることである。あらかじめどういう分解を行うかを想定しておけば、どんなデータが必要になるかも考えられる。1つでも必要なデータが抜けてしまえば、正確な分析はできない。そのために、分析の専門家は分解パターンを複数知っておくことが重要なのだ。
最後に中野氏は、データを蓄積する際には、まずデータ活用企画を考えてから始めることが不可欠だと重ねて強調した。データ活用企画を考え、目的を明確にし、データを蓄積するというステップを繰り返すことで、ようやく問題解決につながるデータを活用できるようになる。同氏は改めてこの順序をしっかりと理解するよう促した。
「データ活用に必要なビジネス基礎スキルはすぐに高められるわけではありません。個人としても組織としても中長期的課題としてぜひ取り組んでほしいと思います」(中野氏)